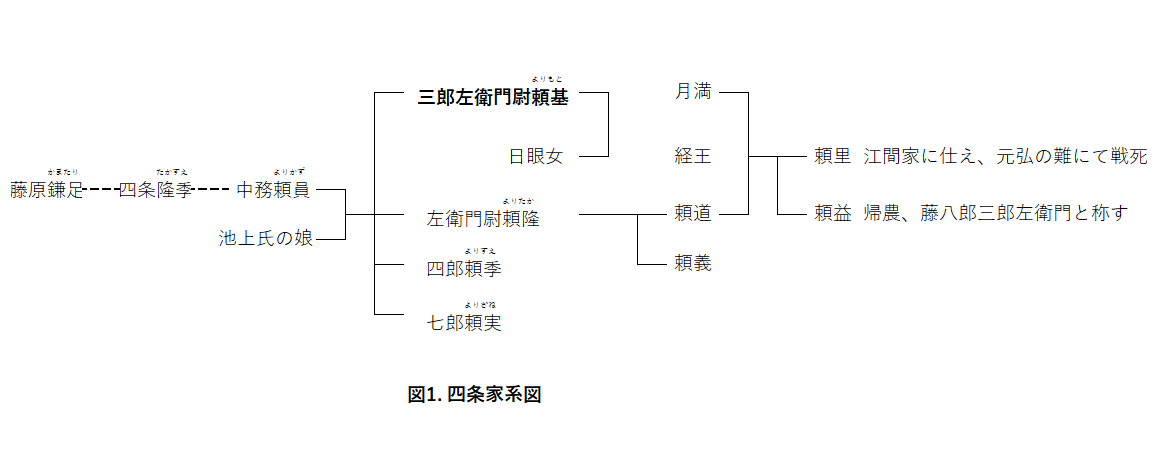
四条金吾(1230年頃〜1300年)の正式な名称は、四条中務三郎左衛門尉頼基といいます。
四条金吾殿は、北条氏の支族である江馬家に仕えた武士であり、武術に秀で医術にも通達していました。康元元(1256)年、二十七歳の時に、池上兄弟や工藤吉隆殿などと前後して、大聖人様に帰依したと伝えられています。以来大聖人様の外護に努め、文永八(1271)年の竜の口の法難では、殉死の覚悟で大聖人様のお供をしています。
ここでは、四条金吾の略伝を下記の流れで説明します。
<四条金吾略伝>
1.四条家について
1.1.家系と地位
1.2.家族構成
2.日蓮大聖人と頼基の信心
2.1.頼基の入信
2.2.竜口法難と佐渡流罪
3.主君江馬氏と四条家
3.1.江間光時について
3.2.実践の人・四条金吾
4.頼基の受難時代
4.1.鎌倉の宗教界と僧侶
4.2.同僚の迫害
4.3.主君の下状と領地問題
4.4.夫人(日眼女)の信心
5.善医としての頼基の活躍
5.1.主君の病気
5.2.耆婆大臣と阿闍世王
5.3.大聖人に薬を献上
6.晩年と熱原法難
7.賜書
四条金吾(1230年頃〜1300年)は、詳しくは四条中務三郎左衛門尉頼基と称する。四条とは姓である。後に述べるが、頼基が晩年を送ったといわれている山梨県南巨摩郡南部町内船には、今も後裔と称して、四条姓を名乗る家がある。
四条家の由来は定かではないが、内船の旧家・四条蔦次郎家に系図が伝えられていたといわれる。その信憑性については、研究を残すが、参考としたい。
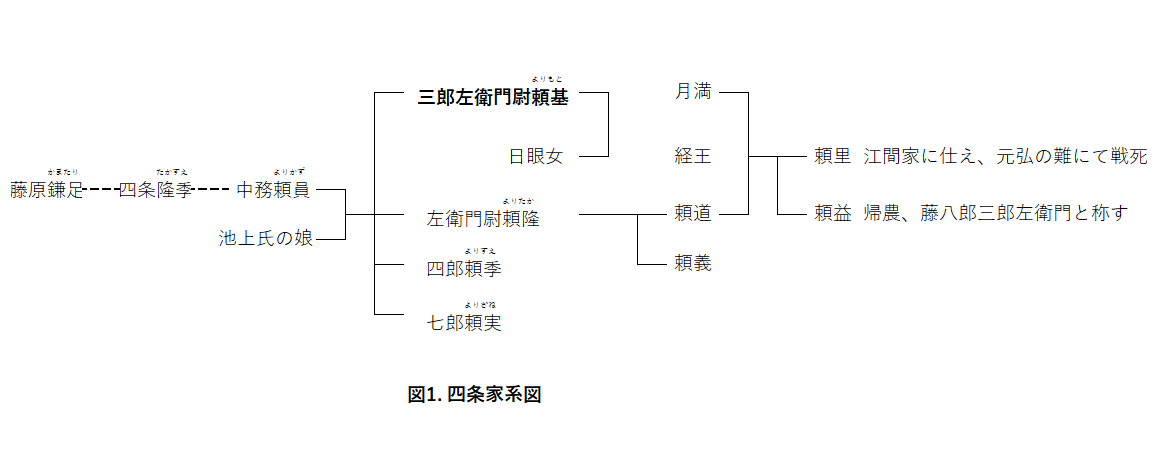
四条金吾の先祖は、聖徳太子が活躍した紀元600年代の藤原鎌足だといわれ、その鎌足から数えて18代目の孝季が初めて「四条」という性を名のった。この系図によると、さらに孝季から5代目の四条中務頼員が、頼基の父にあたる。母は池上氏の娘といわれ、兄弟は頼基を入れて、少なくとも四人はいたと考えられる。これら頼基の兄弟・家族等については、後に述べる。
中務とは官位で、父の頼員が第二代執権北条義時の次男・名越朝時に仕え、中務省の少丞に任じられていたところから、中務と称されていた。中務省とは律令制度による中央官制、すなわち二官八省のうちの第一で「なかのまつりごとのつかさ」と称し、天皇に待従し、詔勅の施行・国史の監修・諸国の戸籍・僧侶の名籍・女官の統制など宮中における一切の政務を掌っていた。
この省には卿一人・大輔一人・少輔一人・大丞一人・少丞二人・大録一人・少禄三人・史生二十人・侍従八人・そのほか二百人近い職員が置かれていた。このうち卿は天皇に陪従し、詔勅・叙位等に関する任務で、輔は卿を補佐する。また丞は宮内の取り締まりや、公文書案の審査などを行っていた。位階については、当時の資料で北畠親房の著になる職原抄によれば少丞は従六位上に相当する。ただし、標注職原抄には、すでに九世紀初め頃から、中務省が有名無実となるつつあることが述べられている。
さらに、鎌倉時代に入ってからは、幕府の政権下における朝廷の権力は次第に薄れ、ほとんどなくなってきたといってよい状態であったから、いずれも官名だけを残し、実際の職務にたずさわったわけではない。また一般に、位より官の方が重視されていたが、官位がすでに有名無実な状態であったことから、従六位上という位も、ほとんど形式的なものと考えられて、特別な権限はなかった。
次に中務三郎左衛門尉の「三郎」とは、通称と思われる。「左衛門尉」とは、二官八省とは別に、軍事面を扱うものに衛門府という官職の一つがあった。令制において衛門府・左右衛士府・左右兵衛府が設けられ、大同三(0808)年に衛門府は左右衛士府に併合され、外令の左右近衛府を加えて六衛府と総称された。その後、弘仁二(0811)年に至って、左右衛士府は左右衛門府と改められ、ここに六衛府の制度が定まったのである。その任は、宮中の警備や護衛、また巡検して非違を査察し、不法をただしたり、人や物の通行許可の手形を司るなどでった。
令制においては、これらの諸の官職を督・佐・尉・志の四等官にわけている。これは唐の制度にあらったもので、官名によって用いる名は異なるが、呼び名は全て同じである。
「左衛門尉」と称するのは、左衛門府の尉官という意味である。頼基は、名越朝時の子・光時に仕えこの左衛門尉に任ぜられていた。ただし大尉であるか少尉であるかは明らかではない。
大宝令に定められた尉の位階は、大尉が従六位上、少尉は正七位上にあたる。しかし、先に述べた「中務」が有名無実となっていたように、この左衛門尉の位も、特別な権威があったとは思われない。ただし、頼基が父子二代にわたって江間家に仕えていたことや、医術にもすぐれていた点から考えて、その地位は安定していたものと考えられる。
また「左右衛門」は、唐制の「金吾」にあたる。よって四条金吾の呼び名は、唐の官名を用いた通称である。さらに「金吾」についてのべるならば「金」とは刀剣・兵器を意味し、この兵器をもって「官門の外を護る官衙をさす。「吾」とは禦、すなわち金革をとって防ぎ守るの意である。また漢書補注によれば「金吾」とは、不詳を避ける馬の名であり、これに因んで天子が出行する折などに、非常を防ぐため先導する役目を「金吾」と呼んだといわれている。
父・頼員は承久の乱の後、北条氏の一門の名越朝時に仕えていた。やがて寛元三(1245)年、朝時が没したあとは、その子・光時を主君として仕えた。しかし、翌年、光時は執権時頼追放の陰謀に加担しているとの嫌疑をうけた。光時は自ら薙髪し、伊豆の江間へ流罪に処された。この時、家臣はことごとく主君・光時を捨て去ったが、頼員だけは最後までただ一人残って悲運な主君に従ったのであった。
その後、光時は許されて鎌倉に戻ったが、家督をその子親時にゆずることになる。こうした不運な主君の下で、頼員は常に変わらぬ忠誠を貫き、やがて、建長五(1253)年三月二十六日に没していった。法名を頼山とよぶ。
頼基の母は池上氏の娘であるといわれ、詳細は不明であるが、文永七(1270)年七月十二日没している。
文永八(1271)年七月十二日の四条金吾殿御書に、
「今月十二日の妙法聖霊は法華経の行者なり日蓮が檀那なり、いかでか餓鬼道におち給ふべきや。定んで釈迦・多宝仏・十方の諸仏の御宝前にましまさん。是こそ四条金吾殿の母よ母よと、同心に頭をなで悦びほめ給ふらめ。」(御書470頁)
と述べられているところから、頼基と共に大聖人に帰依していたことがわかる。この母の命日の七月十二日には、頼基は毎年必ず大聖人のもとへ追善供養を願っている。
頼基の兄弟に関しては、あまり詳細に知ることはできない。しかし、大聖人のお手紙より拝するならば、兄弟は頼基の他に少なくとも三人はいたようであり、また妹もいたと思われる。
兄弟の順は明らかではないが、先にあげた系図(図1)によると、左衛門尉頼隆、四郎頼李、七郎頼實が知られている。
ただし、崇峻天皇御書には、
「殿の兄とは」(崇峻天皇御書、1172頁)
とあり、また四条金吾殿御書に、
「御をとどどもには」(九思一言事、1198頁)
とあることから、頼基は長男ではなかったこと、さらに末子でもなかったことが考えられる。
その他、兄弟については、種種御振舞御書に、
「左衛門尉兄弟四人馬の口にとりつきて」(種種御振舞御書、1060頁)
とあり、とあり、文永八(1271)年の竜の口の法難のおり、居合わせた兄弟たちが大急ぎで、裸足で大聖人のもとへ駆けつけたことから、みな大聖人に帰依していたのではないかと思われる。しかしこの法難以降、大聖人門下に対する迫害はしだいに激しくなり、弟子たちの中には、とらわれたり、牢に入れられたりした者が少なくなく、さらに信仰を続けることは非常に困難な状態にあった。頼基自身も、法難のときは主君に庇護されてことなきを得たが、その後、主君に法門を説いてからは、主君より怨まれ、同僚からも狙われる日々が続き、ついに屋敷や領地を没収されるなどの数々の難がおそいかかった。
こうした迫害が、他の兄弟たちに影響を及ぼさないわけがなかった。とくに頼基の兄は、
「竜象と殿の兄とは殿の御ためにはあしかりつる人ぞかし。」(崇峻天皇御書、1172頁)
とあるように、人肉を食う怪僧・竜象房と手を組み、頼基を圧迫していたと思われる。
だが頼基は大難のさ中、常に大聖人の指導を受けながら、敢然と信仰を貫いた。しかし他の兄弟たちは、数々の迫害にともすれば信仰の火も消えかけ、しだいに頼基から遠ざかりはじめたのである。大聖人のお手紙には、
「たのもしき兄弟なし。」(不可惜所領の事、1162頁)
「兄弟にもすてられ、同れいにもあだまれ、きうだちにもそばめられ」(所領抄、1287頁)
等々の御文があり、兄弟たちの様子がうかがわれる。
また大聖人は、頼基から離れていこうとした兄弟たちの仲を早くから心配され、細々とした指導を与えられている。文永十(1273)年のお手紙には、
「兄弟も兄弟とおぼすべからず、只子とおぼせ。子なりとも梟鳥と申す鳥は母を食らふ。破鏡と申す獣の父を食らはんとうかゞふ。わが子四郎は父母を養ふ子なれども悪しくばなにかせん。他人なれどもかたらひぬれば命にも替はるぞかし。舎弟等を子とせられたらば今生の方人、人目申す計りなし。」(呵責謗法滅罪抄、718頁)
とあり、また建治三(1278)年には、
「御をとどどもには常はふびんのよしあるべし。つねにゆぜにざうりのあたいなんど心あるべし。もしやの事のあらむには、かたきはゆるさじ。我がためにいのちをうしなはんずる者ぞかしとをぼして、とがありとも、せうせうの失をばしらぬやうにてあるべし。又女るひはいかなる失ありとも、一向に御けうくんまでもあるべからず。ましていさかうことなかれ。涅槃経に云はく「罪極めて重しと雖も女人に及ぼさず」等云云、文の心はいかなる失ありとも女のとがををこなはざれ。此賢人なり、此仏弟子なりと申す文なり。此の文は阿闍世王の父を殺すのみならず、母をあやまたむとせし時、耆婆・月光の両臣がいさめたる経文なり。我が母心ぐるしくをもひて、臨終までも心にかけしいもうとどもなれば、失をめんじて不便というならば、母の心やすみて孝養となるべしとふかくをぼすべし。他人をも不便というぞかし。いわうや、をとをとどもをや。もしやの事の有るには一所にていかにもなるべし。此等こそとゞまりゐてなげかんずれば、をもひでにとふかくをぼすべし。かやう申すは他事はさてをきぬ。双六は二つある石はかけられず、鳥は一つの羽にてとぶことなし。将門さだたふがやうなりしいふしやうも一人にては叶はず。されば舎弟等を子とも郎等ともうちたのみてをはせば、もしや法華経もひろまらせ給ひて世にもあらせ給わば、一方のかたうどたるべし。」(九思一言事、1198頁)
と述べられ、細かいところまで配慮をされている。
また頼基に与えられた御書の中に「夜廻の殿原は」、「夜めぐりの殿原」と述べられているところが数か所あり、前後の関係から頼基の兄弟たちをさすのではないかとの説がある。しかし、これらの御文がすべてが皆兄弟のことをさすとは断定しがたい。当時の警護の者たちの中にも、多分に頼基に心を寄せ、信心をしていた者もあるのではなかろうか。あるいは、迫害の中にある頼基にとって、心にはあわなくても警護の者と心を通じさせることは、むしろ大切な事であったであろう。
したがって大聖人は、
「よるは用心きびしく、夜廻りの殿原かたらひて用ひ、常にはよりあはるべし。」(不可惜所領の事、1162頁)
「いかに申すとも鎌倉のえがら夜廻りの殿原にはすぎじ。いかに心にあはぬ事有りとも、かたらひ給へ。」(崇峻天皇御書、1172頁)
等と述べられたのでだろう。いづれにせよ、推論の域を出ないが、頼基の兄弟たちが鎌倉の警護、すなわち夜回りをつとめていたとも考えられることを付しておく。
妹については、名は不明だが、
「妹等を女と念(おも)はゞなどか孝養せられざるべき。」(呵責謗法滅罪抄、718頁)
「我が母心ぐるしくをもひて、臨終までも心にかけしいもうとどもなれば、失をめんじて不便というならば、母の心やすみて孝養となるべしとふかくをぼすべし。」(九思一言事、1198頁)
とあることから、一人または二人以上の妹たちがいたと思われる。妹たちが頼基とともに信仰に励んだかどうかは不明であるが、「失をめんじて」(九思一言事、1198頁)、また、「女るひはいかなる失ありとも」(九思一言事、1198頁)等の御文から、他の兄弟たちと同様、紛動され信心がぐらついていたとも考えられる。
これらの兄弟や妹たちが、その後どのようになったかは明らかではないが、図1-1の系図によると、左衛門尉頼隆は、頼道、頼義の二子をもうけている。頼義は後に出家し日義と号し、甲州満沢村に一寺を創設した。また頼道は、藤太郎次郎左衛門尉といい頼基の娘・月満御前と結婚、頼里、頼益の二子をもうけた。頼里は江間家に仕えたが、元弘三(1332)年、北条氏滅亡の際に殉死したという。頼益は、藤八郎三郎左衛門といい、甲州の内船に住み帰農し、六十歳で没したということである。
頼基の妻・日眼女については、
「夫婦共に法華の持者なり」(四条金吾女房御書、464頁)
とあるように、夫とともに大聖人様に帰依し、生涯変わらない純真な信心を貫いていたと思われる。
なかでも、文永八(1271)年、大聖人様が佐渡へ流罪されたとき、翌九年の春、夫の金吾を佐渡の大聖人様のもとにつかわし、迫害のきびしい鎌倉の地で、留守家族を守りきったのでした。この時のことを、大聖人様は、
「はかばかしき下人もなきに、かゝる乱れたる世に此のとのをつかはされたる心ざし、大地よりもあつし、地神定んでしりぬらん。虚空よりもたかし、梵天帝釈もしらせ給ひぬらん」(同生同名御書、596頁)
と、日眼女の信心を最大にほめられています。
四条金吾と日眼女のあいだには、月満御前・経王御前という二人の娘がいたと言われている。
しかしながら、月満御前は、
「若童生まれさせ給ひし由承り候」(御書462頁)
という記述と、同年同月付の『四条金吾女御書』にある、
「懐胎のよし承り候ひ畢んぬ」(御書464頁)
との記述が、時期的に合わないことなどから、対告衆は四条金吾ではなく、それ以外の鎌倉在住の檀越と推定されます。
経王御前は、
最古の写本である『本満寺録外』の宛名が「経王御前」となっていることや、『経王御前御書』と『経王御前御返事』の内容からは四条金吾へ宛てたと特定できる記述が見られないことから、対告衆は四条金吾ではなく、経王御前という孝子を授かった壇越に宛てたものと推定されます。
ゆえに、四条金吾と日眼女のあいだには、月満御前・経王御前という二人の娘がいたと断言できない。
また文永十(1273)年にしたためられた訶責謗法滅罪抄には、
「わが子四郎は父母を養ふ子なれども悪しくばなにかせん。」(訶責謗法滅罪抄、718頁)
とあり、「四郎」と称する子供がいたとも思われるが、
「とのは子なし」(不可惜所領の事、1161頁)
とあるので、四条家の跡を継ぐ男子がいなかったというようにも考えられる。
日蓮大聖人と頼基の最初の出会いが、いつ、どこであったか、また頼基がどのような経路で、信仰の道に入ったかは不明である。頼基が大聖人からいただいたお手紙は、今日わかっているものでは、文永八(1271)年以降のものと推定されるものばかりである。
ただ弘安四(1281)年四月二十八日付けとされる椎地四郎殿御書に、
「四条金吾殿に見参候はば能く能く語り給い候へ」(椎地四郎殿御書、1556頁)
とあり、頼基の名前がでている。
ところで椎地四郎と頼基の関係については、弘安三(1280)年十二月、頼基にあてた四条金吾許御書に、
「しゐぢの四郎がかたり申し候御前の御法門の事うけ給わり候こそよにすずしく覚え候へ」(八幡抄、1523頁)
とあるように、両者の間柄は、信仰という絆でかなり密接に結びついていたことがうかがえる。
したがって、弘長元(1261)年当時、すでに頼基は入信していたことは確かであり、しかも椎地四郎殿御書の内容からして、かなり強信者の一人として活躍していたようである。
弘長元(1261)年四月二十八日といえば、伊豆流罪の約二週間前である。すでに大聖人に対する国家権力の圧迫は強まっており、大聖人は来るべき難を敏感に察知されていたと考えられる。
前述の椎地四郎殿御書の中にも、大難がなければ法華経の行者ではないと明かされ、さらに、法華経の一文一句でも語る人は如来の使いであると、妙法流布に務めることがいかに偉大であるかを教えている。
これは、どんな難であろうと、如来の使いとしての使命を果たすべきであるという、信心を持つものの姿勢を強調されたといえよう。このことを、頼基に会ったならば、よくよく語りなさいと指示されているのであるから、頼基が門下の中でも中心者の一人として活躍いていた様子がうかがえる。
したがって、日蓮大聖人が建長五(1253)年の夏に鎌倉入りをされ、弘長元(1261)年の伊豆流罪に至る間に、頼基は、日蓮大聖人に出会い、門下となり、さらには伊豆流罪の頃には、信仰もかなり進んでいたとといえよう。
ところで、大聖人と頼基の出会いについてはいくつか考えられる。もとより資料がないから、あくまで大聖人の御書を通した考察や、想像の域を出るものではないが、いくつか述べてみる。
その一つには、頼基の入信は建長八(1256)年頃と推定されている。建長五(1253)年の春、日蓮大聖人が弘法の第一歩を鎌倉の地に印した年は、執権・北条時頼が大伽藍「巨福山建長寺」を完成させた年でもあった。そしてこの建長寺に、宋から渡来した禅僧・蘭溪道隆を住まわせた。道隆が建長寺に入るのにつづいて、京都にいた禅僧・円爾弁円(聖一国師)が副寺の職につき、寿福寺に住んだ。道隆は建長寺仏殿梁牌銘に「皇帝万歳を祈る」ことを記し、また同牌銘に将軍家の安泰や平和をうたって、鎌倉幕府の信任をかったのであった。時頼の帰依によって力を得た道隆は、その弟子・弁円とともに武士階級の上部の中に次第に禅を弘めていった。
時頼、時宗の参禅を目の前にして、また当時の鎌倉幕府の風潮として、それに連なる者もかなりあった。四条金吾もその例にもれず、建長寺を訪れて道隆の門に参禅したと思われる。そして、大聖人が、禅宗は天魔波旬の法なりと説くのを聞いて憤慨し、松葉ヶ谷に出かけていったが、かえって、大聖人の智解と道理に服し、同じく参禅していた仲間の荏原義宗・工藤吉隆・池上宗仲・宗長の兄弟を誘って、共々に大聖人の信者になったといわれる。
いま一つは、頼基が名越一門であることから、名越家と大聖人の関係から頼基の入信を推定することができる。
大聖人は、立宗宣言後、安房国東条郷の地頭・東条景信の厳しい追手を逃れて鎌倉に渡り、名越の松葉ヶ谷に草庵を結んだ。
だが、いかなる手ずるで松葉ヶ谷に草庵を結んだかは不明である。当然、宗教運動を展開するにあたって、地の利や交通の便などを考慮したうえで、名越の地を選定されたことと思われる。
しかし、その場所が幕府の所在地から、あまりにも近い場所にあり、幕府草創の頃ならともかく、北条執権政治がほぼ確立され、社会的秩序が整っていた当時、一介の無名の僧が草庵を結びえた背景には、なんらかの力添え、肩入れがあったと推定される。松葉ヶ谷の草庵跡と称される場所は、現在では三か所あって、正確な位置はわからない。しかし、北条一族の有力者であった名越家の邸宅の近くにつくられたことは確かであり、このことは注目すべきことである。
名越家は、三代執権・北条泰時の弟である朝時の代から名越に住んでいたことから、名越家と称されていた。そして朝時の代に、和田義盛の乱(1213年)で功をあげ、和田一族が滅亡してより、その領地を領土としたが、そこに安房国長狭郡が含まれていた。
大聖人が生まれた小湊も、修行に励み立宗宣言の第一声を放った清澄寺も、長狭郷の内である。そして、大聖人から「領家の尼」「名越の尼」「大尼」などと呼ばれたこの女性は、長狭郷の領家、つまり名越一族である。朝時の妻が、夫の死後出家して大尼といわれたのだともいわれ、あるいは正室ではなく側室ではないか、また名越一族の誰かの室ではないかなどはっきりはしていない。いづれにしても孫の嫁・新尼とともに暮らしていたらしい。そして、大聖人の両親にかなり恩をかけていたようである。
清澄寺大衆中にも、
「領家の尼ごぜんは女人なり、愚癡なれば人々のいひをどせば、さこそとましまし候らめ。されども恩をしらぬ人となりて、後生に悪道に堕ちさせ給はん事こそ不便に候へども、又一つには日蓮が父母等に恩をかほらせたる人なれば、いかにしても後生をたすけたてまつらん」(清澄寺大衆中、947頁)
といわれているし、新尼御前御返事にも、
「領家は……日蓮が重恩の人なれば扶けたてまつらんために……」(新尼御前御返事、765頁)
とあるから、大聖人および両親は、領家になんらかの恩を受けていることが考えられる。
この恩に対して、大聖人は、領家の所領(清澄寺、二間寺を含む)に、東条郷の地頭・東条景信が侵略の手を伸ばした時、領家の味方となって、二寺を領家にもどされたのである。その結果、地頭・東条景信は大聖人を深く怨んだようで、大聖人が東条郷に立ち入ることを禁じ、ついに立宗宣言の時、大聖人を追撃したのである。
これについては、清澄寺大衆中に、
「東条左衛門景信が悪人として清澄のかいしゝ等をかりとり、房々の法師等を念仏者の所従にしなんとせしに、日蓮敵をなして領家のかたうどとなり、清澄・二間の二箇の寺、東条が方につくならば日蓮法華経をすてんとせいじょうの起請をかいて、日蓮が御本尊の手にゆいつけていのりて、一年が内に両寺は東条が手をはなれ候ひしなり。」(清澄寺大衆中、947頁)
とあり、善無畏三蔵抄に、
「文永元年十一月十四日西条華房の僧坊にして見参に入りし時、(中略)爾の時に日蓮意に念はく、別して中違ひまいらする事無けれども、東条左衛門入道蓮智が事に依って此の十余年の間は見奉らず。但し中不和なるが如し。」(善無畏三蔵抄、444頁)
の文などから、この事件が立宗宣言以前ということが考えられる。(なお、この事件については、小松原法難の前に起きたとする説もある。)
領地を奪われずにすんだ領家は喜び、それは大聖人に対する信頼、尊敬から、妙法の信仰へと進転していったようである。後の文永八(1271)年、竜口の法難に際しては、退転し、大聖人から厳しく指摘されてはいるが、立宗前後は、かなり名越の領家と大聖人の間は密接であったと考えられる。
ゆえに、建長五(1253)年四月二十八日、大聖人が立宗宣言され、四箇の格言に念仏を破折されて、遺恨をむき出しにした東条景信によって追われた時、鎌倉に脱出された大聖人に対して、領家たる名越家が、援助の労を惜しまなかったことが推測できるのである。大聖人は、領家の手ずるで、名越の地・松葉ヶ谷に草庵を結んだと思われる。
早くから名越家の従者であったのが四条家である。頼基も主命をうけて草案におもむき、そこで頼基の生涯を決する、大聖人との出会いがあったと考えられる。
やがて、妙法の信者として新しい人生の門出をなした頼基は、同僚や友人を誘って松葉ヶ谷を訪れたのであろう。鎌倉地方の門下の中心として、大聖人から深く信頼され、活躍した頼基の生涯から考えて、大聖人が鎌倉入りされた早々、草庵建設の時に、いち早く信者になったと考えても不思議ではない。
こうして縁故関係を通じながら、頼基を中心とした、活発な布教活動が繰り広げられ、妙法の輪は次第に拡大していったのであろう。
文永八年(1271年)二月頃から六月にかけておそった大旱魃は、全国的に国土を荒廃させた。民衆は水飢饉から食糧難に責められ、さらに疫病にと苦悩の底に沈んでいった。
こうした状況に対し、幕府は極楽寺良観に雨乞いの祈禱を命じた。この知らせを聞いた大聖人は、良観に次のように申し入れた。
「七日の内にふらし給はゞ日蓮が念仏無間と申す法門すてゝ、良観上人の弟子と成りて二百五十戒持つべし、雨ふらぬほどならば、彼の御房の持戒げなるが大誑惑なるは顕然なるべし。」(頼基陳状、1131頁)と。
この申し入れに喜んだ良観は、六月十八日から七月四日までの間、弟子百数十人を集めて祈雨の法を行じた。その結果は、
「此に両火房上より祈雨の御いのりを仰せ付けられたり云云。此に両火房祈雨あり。去ぬる文永八年六月十八日より二十四日なり。此に使ひを極楽寺へ遣はす。年来の御歎きこれなり。『七日が間に若し一雨も下らば、御弟子となりて二百五十戒具に持たん上に念仏無間地獄と申す事ひがよみなりけりと申すべし。余だにも帰伏し奉らば、我が弟子等をはじめて日本国大体かたぶき候ひなん』云云。七日が間に三度の使ひをつかはす。然れどもいかんがしたりけむ一雨も下らざるの上、頽風・飆風・旋風・暴風等の八風十二時にやむ事なし。」(下山御消息、1144頁)
と明らかであり、良観はその面目を失ったのである。
この一件により良観は、大聖人を深く怨み、七月八日に浄光明寺行敏を通し、大聖人に対決を申し入れた。これに対し大聖人は返書をしたため、公場対決を要求した。良観らは是非なく訴状を問注所へ差し出し、幕府はこの訴状を大聖人に渡した。大聖人はこの訴状に対し、一つ一つ明確に論駁され、もはや良観らは、再び反駁することができなかった。
しかし、
「さりし程に念仏者・持斎・真言師等、自身の智は及ばず、訴状も叶はざれば、上郎尼ごぜんたちにとりつきて、種々にかまへ申す。」(種種御振舞御書、1057頁)
とあるように、法論をもって大聖人に対することができないことを知ると、良観はしきりと裏面から幕府の有力者や、尼御前たちを動かし、大聖人を抑圧しようと画策しはじめた。そしてついに、幕府の政治や軍事面の実験を握っていた平左衛門尉頼綱を動かしたのである。
九月十日、大聖人は評定所に呼び出され、尋問を受けた。しかし大聖人は、少しも憶することなく、
「理不尽に失に行はるゝほどならば、国に後悔ありて、日蓮御勘気をかほらば仏の御使ひを用ひぬになるべし。梵天・帝釈・日月・四天の御とがめありて、遠流死罪の後、百日・一年・三年・七年が内に自界叛逆難とて此の御一門どしうちはじまるべし。」(種種御振舞御書、1057頁)
と逆に平左衛門尉を諌めたのである。
さらに九月十二日、大聖人は書状をしたため、
「抑貴辺は当時天下の棟梁なり。何ぞ国中の良材を損ぜんや。早く賢慮を回らして須く異敵を退くべし。世を安んじ国を安んずるを忠と為し孝と為す。是偏に身の為に之を述べず、君の為、仏の為、神の為、一切衆生の為に言上せしむる所なり。」(一昨日御書、477頁)
と、再び平左衛門尉を諌めたのである。しかし、この書状に溢れる大聖人の至誠も、所詮、通じることはなかった。逆に平左衛門尉はその日のうちに大聖人を捕らえようと迫ったのである。
十二日の夕刻、平左衛門尉は松葉ヶ谷の草庵にただ一人住まわれている大聖人のもとへ、武具に身を固めた数百人もの兵士を率い押し寄せてきた。その様子は諸御書にみられるが、種種御振舞御書には次のようにある。
「文永八年太歳辛未九月十二日御勘気をかほる。其の時の御勘気のやうも常ならず法にすぎてみゆ。了行が謀反ををこし、大夫律師が世をみださんとせしを、めしとられしにもこへたり。平左衛門尉大将として数百人の兵者にどうまろきせてゑぼうしかけして、眼をいからし声をあらうす。大体事の心を案ずるに、太政入道の世をとりながら国をやぶらんとせしににたり。たゞ事ともみへず。日蓮これを見てをもうやう、日ごろ月ごろをもひまうけたりつる事はこれなり。さいはひなるかな、法華経のために身をすてん事よ。くさきかうべをはなたれば、沙に金をかへ、石に珠をあきなへるがごとし。さて平左衛門尉が一の郎従少輔房と申す者はしりよりて、日蓮が懐中せる法華経の第五の巻を取り出だして、おもてを三度さいなみて、さんざんとうちちらす。又九巻の法華経を兵者ども打ちちらして、あるいは足にふみ、あるいは身にまとひ、あるいはいたじきたゝみ等、家の二三間にちらさぬ所もなし。日蓮大高声を放ちて申す。あらをもしろや平左衛門尉がものにくるうを見よ、とのばら、但今ぞ日本国の柱をたをすとよばはりしかば、上下万人あわてゝ見へし。」(種種御振舞御書、1057頁)
さて、数百人してやっと大聖人を捕らえた平左衛門尉は、一往、公式には武蔵守宣時の預りとして、宣時の領国である佐渡へ遠流ということに裁決を下した。しかし内密には竜口の刑場で斬首する手筈になっていた。そのため、大聖人はいったんは宣時の預かりとして過ごし、その日夜半になってから、再び多くの兵士にとりかこまれ竜口へと向かわれた。
途中、若宮小路の鶴岡八幡にさしかかったとき、
「八幡大菩薩に最後に申すべき事ありとて」(種種御振舞御書、1059頁)
と馬から下りられ、
「いかに八幡大菩薩はまことの神か」(同、1059頁)
と大音声を放って叱咤されたのである。
さらに一行が由比ヶ浜に出て、御霊社の前にさしかかった時、大聖人は、
「しばしとのばら、これにつぐべき人ありとて」(同、1059頁)
といって、護送の列を止められた。そして、大聖人はお供していた童子の熊王丸を呼ばれ、長谷の頼基のともに、この急を告げさせた。
熊王丸の知らせを受けた頼基の驚きは、いかばかりであったろう。さしも気丈な頼基も、すっかり度を失い、とるものもとりあえず、裸足のまま飛び出した。毎月十二日は頼基の母の命日である。考心の厚い頼基のことである。この日も恐らく兄弟して、母の追善供養をしていたものか、たまたま居合わせた兄弟たちも、頼基のあとに続き、大聖人のもとへ駆けつけていった。
やがて一行に追いついた頼基は、夢中で馬上の大聖人にとりすがった。大聖人は、
「今夜頚切られへまかるなり、この数年が間願ひつる事これなり。」(同、1059頁)
と、静かに確信あふれる言葉で仰せになった。法華経のゆえに、頸の座にのぞまれることを、喜びとされている大聖人の厳然たるお姿に頼基も今はただ大聖人と共に殉死しようと覚悟を定め、泣く泣く大聖人の馬のくつわにとりすがって、刑場へとお供をしていったのである。この時の頼基の様子は、後に大聖人が佐渡あるいは、身延等で認められた御書にいくつかみられる。
「文永八年の御勘気の時、既に相模の国竜口にて頚切られんとせし時にも、殿は馬の口に付きて足歩赤足にて泣き悲しみ給ひ、事実になれば腹きらんとの気色なりしをば、いつの世にか思ひ忘るべき。」(殿岡書、1501頁)
「去ぬる十二日の難のとき、貴辺たつのくちまでつれさせ給ひ、しかのみならず腹をきらんと仰せられし事こそ、不思議とも申すばかりなけれ。日蓮過去に妻子・所領・眷属等の故に身命を捨てし所いくそばくかありけむ。或は山にすて、海にすて、或は河、或はいそ等、路のほとりか。然れども法華経のゆへ、題目の難にあらざれば、捨てし身も蒙る難等も成仏のためならず。成仏のためならざれば、捨てし海・河も仏土にもあらざるか。(中略)
かゝる日蓮にともなひて、法華経の行者として腹を切らんとの給ふ事、かの弘演が腹をさいて主の懿公がきもを入れたるよりも、百千万倍すぐれたる事なり。日蓮霊山にまいりて、まず四条金吾こそ、法華経の御故に日蓮とをなじく腹切らんと申し候なりと申し上げ候べきぞ。」(四条金吾殿御消息、478頁)
竜口の法難という最大の事件の時に、大聖人のそばで、大聖人と共に殉死の決意で行動したのは、数多い門下の中で頼基ただ一人であった。
前述の御文のように、その昔弘演は主君・懿公の恥をかくすため、わが腹をさいて主君の肝を入れ、死んでいったという。こうした例をあげるまでもなく、臣下や武士は主君を大事にしていた。己れの生命は、常に主君と共にあったともいえる。したがって、主君のため、お家のためには、武士であるならば進んで命を捨てることが是とされていたのである。
だが、今ここに武士である頼基が、まさに命を捨てんとしたのは、主君ならぬ法華経の御故であり、大聖人の御故に我が命を捨てようとしたのである。
こうした頼基の姿こそ、不自惜身命の実践の姿である。また、仏法を守り切るという、烈々たる気概、気迫こそ今も変わらぬ大聖人の弟子としての精神である。
また、頼基が仏法のために命を捨てると決意した瞬間に、頼基自身の成仏、宿命の転換が決まったともいえよう。すなわち、
「頚切られんとせし時、殿はともして馬の口に付きて、なきかなしみ給ひしをば、いかなる世にか忘れなん。設ひ殿の罪ふかくして地獄に入り給はゞ、日蓮をいかに仏になれと釈迦仏こしらへさせ給ふとも、用ひまいらせ候べからず。同じく地獄なるべし。日蓮と殿と共に地獄に入るならば、釈迦仏・法華経も地獄にこそをはしまさずらめ。」(崇峻天皇御書、1172頁)
と。頼基がもし地獄に堕ちるのなら、ともに地獄に堕ちようとの一節を拝した頼基はいかばかりか感激にむせんだことであろう。
さて、いよいよ竜口の頸の座にすわられた大聖人の姿をみて、頼基は、
「只今なり」(種種御振舞御書、1060頁)
と絶句し泣き伏してしまった。しかし、大聖人は、
「不かくのとのばらかな、これほどの悦びをばわらへかし」(種種御振舞御書、1060頁)
とかえって頼基を叱咤し、激励されたのである。
まさに、何ものをも恐れぬ泰然自若としたお姿であった。御本仏としての御境涯は、いかなる権力、武力をもってしても、所詮こわすことはできなかったのである。
時刻はすでにあけて十三日の丑の刻(午前二時)であった。突然、
「江のしまのかたより月のごとくひかりたる物、まりのやうにて辰巳のかたより戌亥のかたへひかりわたる。十二日の夜のあけぐれ、人の面もみへざりしが、物のひかり月よのやうにて人々の面もみなみゆ。太刀取目くらみたふれ臥し、兵共おぢ怖れ、けうさめて一町計りはせのき、或は馬よりをりてかしこまり、或は馬の上にてうずくまれるもあり。日蓮申すやう、いかにとのばらかゝる大に禍なる召人にはとをのくぞ、近く打ちよれや打ちよれやとたかだかとよばわれども、いそぎよる人もなし。さてよあけばいかにいかに、頚切るべくわいそぎ切るべし、夜明けなばみぐるしかりなんとすゝめしかども、とかくのへんじもなし。」(種種御振舞御書、1060頁)と。
この竜口の法難の瞬間こそ、日蓮大聖人が上行菩薩として、迹の姿を開いて、久遠元初の自受用身としてあらわれた発迹顕本の時だったのである。
こうして、その夜の難を逃れた聖人はしばらくして、ひとまず依智の本間六郎左衛門重連の家に預けられることになった。大聖人と、なお、その身を案ずる頼基は、周章狼狽している役人たちと共に、依智を目指し道にまかせて進み、やっと十三日の昼ごろに本間六郎左衛門の屋敷に到着された。
本間邸に入られた大聖人の堂々たるお振舞いに、警護の者も、次第に大聖人に信伏する者も多くなった。一度は死を決意した頼基も、大聖人の悠々たるお姿や、本間家の家臣や警護の兵士たちが、むしろ信伏している姿に、ひとまず安心し、大聖人と別れて鎌倉に帰ったのである。
その後二十日あまりを依智で過ごされた大聖人は十月十日、流罪の地、佐渡に向かって出発された。
しかしこの間、迫害は門弟にまで及び、禁獄・所領没収・御内追放を受けた者もいた。さらに弾圧を恐れた人々の中には信仰を捨て退転する者もいた。
これらの弾圧は、おもに良観が暴徒を使って鎌倉各所に火を放ち、殺人強盗をなし、これを全て大聖人門下の仕業であると捏造したために起きたものであった。しかも、幕府側も機会を捉えて大聖人一門を壊滅させようと躍起になっていたのでこの弾圧がいかに激しかったかがうかがえるのである。
こうしたなかにあって、頼基は大聖人の身を案じ、鎌倉から何度も便りを出している。文永八年(1271年)九月二十一日付のお手紙の冒頭には、
「度々の御音信申しつくしがたく候。」(竜口御書、478頁)
とあることから、頼基が相変わらず大聖人をお慕いし守り切ろうとした心情がうかがえるのである。
大聖人が佐渡へその第一歩を下されたのは、文永八(1271)年十月二十八日、塚原の三昧堂に着かれたのは十一月一日であった。佐渡といえば、古来この地に流された流人のほとんどが病死している。承久の乱の順徳天皇等、数えあげればきりがない。当時、佐渡へ流されるということ自体、死罪にも匹敵する罪であったといえよう。
こうして、厳寒の孤島に、しかも五十歳の大聖人の、あまりにも峻烈な御生活がはじまったのである。そしてそれは、文永十一(1274)年三月に至るまで、二年数か月にわたったのである。
また、この地にも大聖人の命を狙う者がいた。しかし、地頭の本間六郎重連や阿仏房夫妻に守られながら、大聖人は直ちに人本尊開顕の書である開目抄の御執筆に入られたのである。
一方、大聖人の身を心から案ずる頼基は、大聖人の許を訪れてお見舞いしたいと思ったことであろう。しかし、武士として主君に仕える身で、長期の旅などできようはずがなく、そこで、文永九(1272)年のはじめ、大聖人の許へ使者をたて、数々の御供養の品を送ったのである。
大聖人は、二月に完成された開目抄をこの使者に託し、頼基に送られたのであった。種種御振舞御書には、
「去年の十一月より勘へたる開目抄と申す文二巻造りたり。頚切らるゝならば日蓮が不思議とゞめんと思ひて勘へたり。此の文の心は日蓮によりて日本国の有無はあるべし。譬へば宅に柱なければたもたず。人に魂なければ死人なり。日蓮は日本の人の魂なり。平左衛門既に日本の柱をたをしぬ。只今世乱れて、それともなくゆめの如くに妄語出来して、此の御一門どしうちして、後には他国よりせめらるべし。例せば立正安国論に委しきが如し。かやうに書き付けて中務三郎左衛門尉が使ひにとらせぬ。」(種種御振舞御書、1065頁)とある。
この“開目抄”について、大聖人は同年四月に富木常忍に与えられたお手紙に、
「法門の事は先度四条三郎左衛門尉殿に書持せしむ。其の書能く能く御覧有るべし。」(富木殿御返事、584頁)
とその重要性を述べられ、頼基を中心に教義の浸透をはかられている。
開目抄がいかに重大な書であるかは、いうまでもない。しかも筆紙も窮乏するなか、残る門下一同の遺言として認められた重大な御書を、有縁の中の最も有縁な弟子として、頼基は賜ったのである。このことからして、大聖人がいかに頼基を信頼されていたかがわかる。また頼基も、大聖人の信頼どおり、鎌倉にあって、迫害の激しい中を信者の中心となって活躍したのである。
このころ鎌倉幕府は、内外ともに騒然とした空気に包まれていた。外には蒙古の襲来が問題となり、内には北条一門の醜い同士打ちという内乱が起こったのである。
まさに前年の文永八(1271)年九月十二日、大聖人が平左衛門尉に向かって断言された自界叛逆難・他国侵逼難が現実となってあらわれてきたのである。
文永九(1272)年二月十五日に起こったこの内乱の首謀者は北条時輔であり、この時輔に江間光時の弟・教時・時章が加担していた。したがって光時も、謀反人の一族との嫌疑を受け、頼基の主君である江間家の命運は、まさに風前の灯であった。しかし、幸いなことに江間家に対する謀反の疑いも晴れ、頼基もことなきを得たが、幕府の動揺は激しかった。
騒動もようやく鎮まった文永九(1272)年の春、開目抄につづいて、頼基は富木殿といっしょに佐渡御書を受け取った。窮迫する御生活のなかにあって、御文にあふれる鎌倉の弟子や門下一同を心配される大聖人の誠心に、頼基は奮い立つにはおられなかったであろう。
鎌倉での騒動は鎮まったとはいえ、監視の眼は、なお厳しく、しかも江間家に仕える身であり、勝手な行動を起こすことは不可能に近かった。そのうえ、流罪地・佐渡までの長期間の旅路は、考えるだけでも並大抵のことではなかったが、頼基はそうした障害を乗り越え、ただ大聖人にお目通りしたい一念で、佐渡に向かったようである。
道中の険しさは日妙聖人御書で察せられる。
「相州鎌倉より北国佐渡国、其の中間一千余里に及べり。山海はるかにへだて、山は峨々海は濤々、風雨時にしたがふ事なし。山賊海賊充満せり。すくすくとまりとまり民の心虎のごとし犬のごとし。現身に三悪道の苦をふるか。」(日妙聖人御書、607頁)と。
こうして佐渡の一の谷についた頼基は、感涙の中に大聖人にお会いすることができたのである。大聖人のお喜びも、またひとしおであったと思われる。
そのことは後年、身延でしたためられたお手紙に、この時の様子が次のように述べられている。
「佐渡の島に放たれ、北海の雪の下に埋もれ、北山の嶺の山下風に命助かるべしともをぼへず。年来の同朋にも捨てられ、故郷へ帰らん事は、大海の底のちびきの石の思ひして、さすがに凡夫なれば古郷の人々も恋しきに、在俗の宮仕へ隙なき身に、此の経を信ずる事こそ希有なるに、山河を陵ぎ蒼海を経て、遥かに尋ね来たり給ひし志、香城に骨を砕き、雪嶺に身を投げし人々にも争でか劣り給ふべき。」(殿岡書、1501頁)と。
また、夫を佐渡へ送り出した日眼女に対しても、大聖人は直ちに感謝と激励の言葉を認められている。
やがて、大聖人から妻日眼女への手紙をたずさえ、名残を惜しみながら頼基は佐渡を後にした。
大聖人の御尊姿を、ひさびさに懐かしく拝し、鎌倉に帰った頼基は、新たな感情のなかにますます信心に励んでいったのであろう。大聖人からは追いかけるようにして、五月、感謝のお手紙をいただいている。その冒頭には、
「日蓮が諸難について御とぶらひ、今にはじめざる志ありがたく候。」(煩悩即菩提書、597頁)
とあり、実に頼基の終始一貫した変わらぬ至誠がしのばれる。
その後、御不自由な佐渡での生活を思いやり、少しでもお助けしようと頼基は何回となく大聖人の許へ使者をたて、御供養の品を送っている。こうして門下一同にとって最大の迫害の中、頼基は大聖人の留守を守りぬき、鎌倉の信者の中心として、活躍したのである。
江間氏(名越氏ともいう)は、四条金吾家代々の主君である。とくに日蓮大聖人のもとで実践第一の弟子として活躍した頼基にとっては、善知識となって、その生涯と信心に多大な影響をあたえてきたといえよう。ここでは、江間氏およびその一門である北条氏や鎌倉幕府などについて少々述べてみる。
日蓮大聖人の御在世すなわち十三世紀初頭は、源頼朝が鎌倉に幕府を創立して以来五十余年、承久の乱(頼朝の死後二十余年)などによって、政治の中心は京都から鎌倉に移っていた。天皇の即位、年号の改元すら幕府の許可
なくしては行うことができなかったという。
当時の鎌倉幕府の主は、わずか二歳の四代将軍・頼経であった。頼朝が没したあと、嫡子・頼家(二代将軍)、その弟・実朝(三代将軍)と源氏の嫡流が継いでいたが、有力御家人の
勢力争いにより、いずれも若くして暗殺され源氏はついに絶えてしまったのである。かわって、京都の貴族・藤原家から、名目上だが御家人を統一する意味で下った幼将軍が四代目を継いでいた。
したがって武家政治としての絶大な権力を掌中にしていたのは、有力御家人として執権職にあった北条一門である。
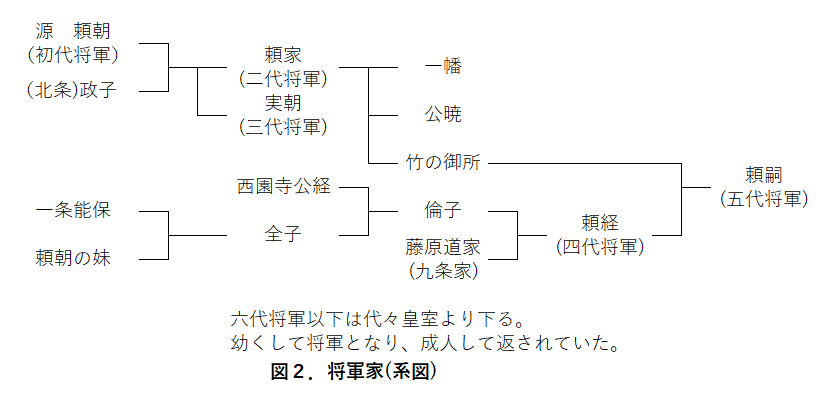
北条氏は、もともと伊豆の一土豪であったが、頼朝の旗揚げに真っ先に応じ、頼朝の妻・政子の外戚として、幕府創立の功績をなしてきたうえに、頼朝亡きあとは尼将軍
・政子の背後にあって、幕府内随一の勢力をもっていた。
四条家の主君・名越氏は、北条氏のなかでも有力な名家でありながら、実に悲運な一族であった。初代・朝時、すなわち江間光時の父は、二代執権・義時の次子であり、三代執権・泰時の弟である。
邸が鎌倉の名越にあったことから名越氏と称するようになり、その子・光時の代になってから、執権時頼への謀反のため、流罪となった場所が伊豆の江間であったから、江間氏と呼ばれたようである。
日蓮大聖人も御書のなかに「名越の公達」(頼基陳状、1136頁)とか「えまの四郎殿」(四条金吾殿御書、1197頁)などと一族を呼称されている。
朝時は一時女性問題によって、三代将軍・源実朝の勘気、また父・義時より義絶を受けて、駿河国(現在の静岡県)富士郡に蟄居したが、建歴三(1213)年五月、和田義盛の乱の折に許されて参加、敵将・朝比奈義秀と戦い、かなりの傷を受けながらも勇戦した様子が吾妻鏡にみえる。
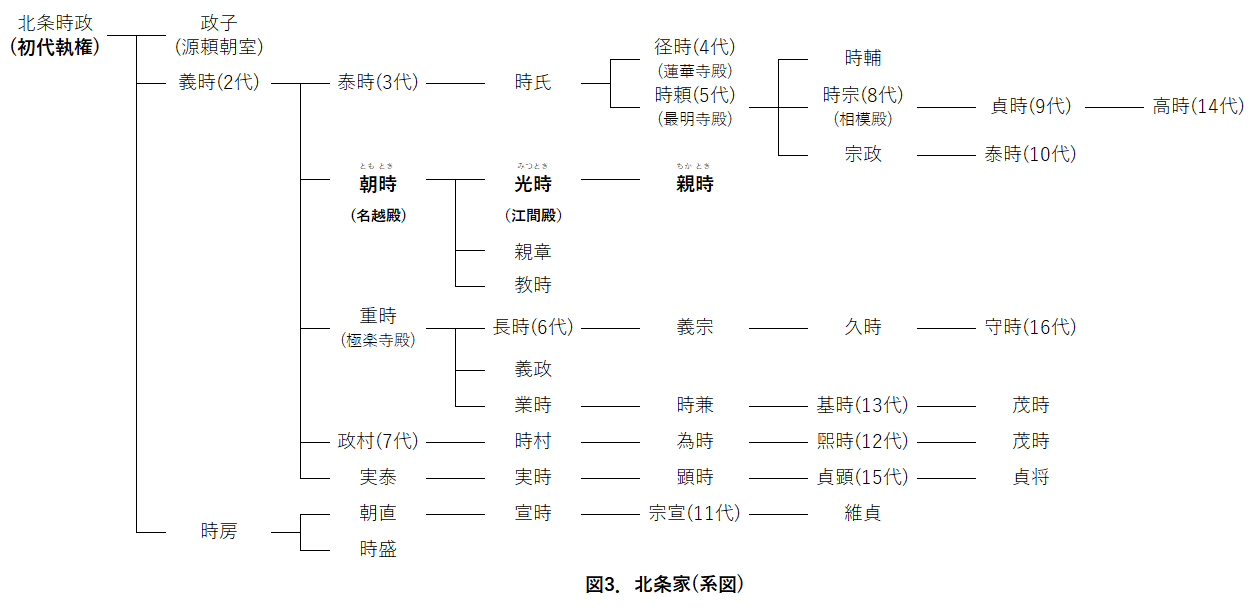
また、承久三(1221)年の承久の乱には、兄・泰時が東海道の総指揮官として出陣したのと共に、北陸道の大将軍として上洛している。すなわち、保歴間記(群書類従第二十六輯45頁)に「(承久三年)五月二日より当座の勢を差上せけり。東海道は義時が嫡子武蔵守泰時、北陸道は二男遠江守朝時、東山道は相模守時房(泰時舎弟)。三手に弐捨万八千騎上る」とある。そして、嘉禎二年(1236)年には評定衆になったが、仁治三(1243)年には出家していることが、北条九代記(続群書類従第二十九輯13頁)、鎌倉年代記裏書(歴史科大成十八・327頁)などに述べられている。
その長子・名越光時は嘉禎二(1236)年、父の官職を継いで式部丞に任じられ、父・朝時の出家した翌年寛元元(1243)年には越後守となって、四代将軍・頼経の近習として寵遇を蒙った。四代将軍・頼経が執権・義時によって、引退させられると共に、光時の執権への道も遠のき、そこで、得宗家(嫡流)に対する不満をもつ有力な御家人・三浦、千葉氏とともに前将軍・頼経を擁立する計画をたてたのである。しかし、事前に発覚し、光時は薙髪して謝罪、越後守などの所帯の職を収公されて伊豆の江間に流されたのであった。
名越家は有力な北条一門でありながら、鎌倉幕府の歴史のなかで、常にその一族が謀反人となって登場しており、その子孫は不運な立場を余儀なくされている。家系図をみてもわかるように、得宗家に次ぐ有力な立場にあり、初代・朝時は、父・義時からも愛されて、承久の乱には一軍の総大将として活躍しているにもかかわらず、執権・連署ともに、就任した者は一族では一人もいない。
名越家が不運な立場となったのは、次のような北条家のお家騒動が背景になっていたと考えられる。三代執権・北条泰時が病気になったのは、仁治三(1242)年五月九日であり、そのあとすぐ、五月十一日には朝時が出家している。泰時は闘病一カ月の六月十五日に没している。泰時の子・時氏はすでに早世しており、孫の経時が二十歳未満であったが、四代執権となった。この仁治三年(1242)年の記録については、幕府の記録を綴った吾妻鏡にはどういうわけか一年間ぬけている。だが、平戸記によると、騒動があった様子がうかがわれるし、また、泰時のあとについて、名越朝時が早々に出家し執権職を継がなかったことなど、かなり後継者争いがあったことが想像できる。つづいて起こったのが、四代執権経時の早々の病死だった。そして、五代目には実力者・北条時頼が
執権職を継いだのである。名越光時らによる時頼への謀叛は仁治三(1242)年からわずか四年後である。
保歴間記(群書類従第二十六輯49頁)に「同(寛元四年)四月十九日武蔵守経時死去す。舎弟・時頼。同閏四月江間越後守光時。(相模守朝時嫡子)将軍の近習として御気色吉りけるが、驕心有りて。我は義時が孫也。時頼は義時が参也、光時将軍の執らせんと企ける程に。将軍も光時に心を被寄けるにや。此事願て同七月八日光時遠流せらる。同十一日入道将軍も御上洛有けり」とある。
光時は伊豆の所領江間に蟄居したが、後に赦されて鎌倉に出ているようである。ただし、その後「関東往還記」の弘長二(1262)年七月十三日の条にあらわれるが、越後入道、法名蓮智という在家沙弥の身なので、江間家の当主ではなかったようである。北条氏得宗に対抗して公職を収公されたのであるから、当然といえよう。しかし、その子・親時は、その後、幕府に出仕するようになったようである。大聖人も、
「えまの四郎殿の御出仕に、御ともの…」(四条金吾殿御書、1197頁)
と述べている。
だが、江間氏にとって、再び得宗家叛逆の疑いをかけられる事件が持ちあがった。文永九(1272)年の北条時輔の二月騒動である。この内乱の首謀者である時輔は、八代執権・時宗の兄にあたっていたが、正室の子ではなかった。そのため執権職を相続されず、弘長元(1261)年に三代目の六波羅探題として京都に赴任した。父・時頼は、時宗の器量に早くから目をつけ、そのため時宗は相模太郎と呼ばれて家督相続を約束されていた。時輔は長男であるにもかかわらず、天下の実権も弟に奪われたゆえ、心中、常に穏やかではなかった。
この時輔に気脈を通じていたのが名越家の一族で、鎌倉の評定衆・中務権大輔教時であった。ゆえに時輔の乱が発覚するに及んで、教時は同罪とされ、その兄・名越民部大輔時章もその一味として強く疑われた。そして、時章は誅され、時輔も誅された。
このとき、教時・時章の兄であった江間光時も、謀反人の一人として疑われ同じく断罪に処せられるところであったが、疑いが晴れて、光時はまたしても一命をとりとめたのである。
すぐ下の弟・時章は断罪の後、関係がなかったことがわかったが、没収された領地、財産などは、そのままで、ついに返されなかったという。
天下の実権をわがものとして、武家政治の上にわが世の春をうたった北条一門にあって、一族中一人の花も咲かせることができなかった名越家は、また初代朝時より代々得宗家に反骨を呈してきた、宿命ともいうべき一族であった。
頼基は、数多い日蓮大聖人門下のなかでも、実践第一のひとであった。大聖人を徹底的に迫害し弾圧する絶対の権力・北条幕府の一門に仕えるという環境にあって、信心を貫きとおしたのである。頼基の主君・江間光時およびその子・四郎親時は、ともに大聖人迫害の元凶である極楽寺良観の熱心な信者であったから、その家臣の多くもまた主君とともに同じ信仰であった。ひとり頼基だけが主君と信仰を異にし、大聖人の仏法を信じていたのである。
その中にあって、しかも大聖人が国中から悪人と目され、国家権力による度々の迫害にあっていたにもかかわらず、頼基は確信に燃えて、主君に妙法を説いたのである。それは、文永十一(1274)年、大聖人が佐渡流罪から御赦免となって、元気に帰られた年のことである。
文永八(1271)年九月十二日の竜口の法難、続いて大聖人の佐渡流罪は、門下にとって、全く闇に閉ざされたも同然であった。すなわち、信心に対する疑妄はなくとも、御本仏たる大聖人が全く、赦免、帰還の見込みのない遠流の地・佐渡に流され、門下の弟子檀那もまた次々と所領をとられたり、所を追われたり、牢に入れられたりするなど、その弾圧は激しいものであったから、直接難を受けない信徒までもが、信仰に迷いを生じ、世間の目を恐れて、次々と脱落していったのである。
残って、健気に信心を続けていく人々にとって、流罪の身にありながら、遠く佐渡より弟子の身を案じて送られてくる大聖人の力強いお手紙が唯一の支えであった。更に、広宣流布への大情熱が御文の行間に躍動していて、ともすると難にくじけそうになる門下の人々を勇気づけられたのである。そののち、大聖人の御確信通り、佐渡流罪上前例のない処置となって、ついに文永十一(1274)年二月赦免状が下された。この事実は、門下の人々に信心への強い確信を与えたのである。
主君に対しても至誠一徹、そして純粋な信心を貫いてきた頼基は、ここで仏法の偉大さを痛感し、主君を折伏したのであった。涅槃経に「慈無くして詐り親しむは即ち是れ彼が怨なり。彼が為に悪を除くは、即ち是れ彼が親なり」とある。
頼朝は、不幸の因たる良観を信仰する主君に対し、悪を除き、正法に帰伏せしめていくことこそ、最高の主恩を報ずることと、敢然と折伏を実践したのであった。
しかしながら、頼基の誠意の折伏に対して、主君は耳をかたむけず、かえって、頼基を疎み、遠ざけるようになったのである。極楽寺良観への非常に熱心な信者であった主君であれば、いかに忠臣が至誠をつくしても、こと宗教に関しては、そう簡単に受け入れるわけにはいかなかったのであろう。
これに対して大聖人は、文永十一(1274)年九月十一日付けの主君耳入此法門免与同罪事に、
「一国こぞりて日蓮をかへりてせむ。上一人より下万民にいたるまで、皆五逆に過ぎたる謗法の人となりぬ。されば各々も彼が方ぞかし。心は日蓮に同意なれども身は別なれば、与同罪のがれがたきの御事に候に、主君に此の法門を耳にふれさせ進らせけるこそありがたく候へ。今は御用ひなくもあれ、殿の御失は脱れ給ひぬ。」(主君耳入此法門免与同罪事、744頁)
と指導されている。
日本国を挙げて、法華経の行者・日蓮大聖人に敵対し、大謗法を犯している、そのなかで、頼基は、心は大聖人と同じく、正法を護持しているとはいえ、身は謗法の主君に仕えているゆえに、仏法の厳しい道理に照らしてみれば、与同罪を免れることはできない。だが、頼基が主君を折伏したことは、与同罪をも免れ、成仏することができると、頼基が健気な信心を誉められたのである。
現在の民主主義の世の中ですら、被雇用人が雇用主を折伏することは難事である。まして当時は、身分制度のゆるぎない封建社会であり、かりにも臣下の身にある者が、主君に改宗を迫るなど、到底考えられぬことであった。しかも、当時の主君は、文字通り、一切の死活の鍵をにぎった主君であり、主君の意向は、臣下にとって絶対的な影響力をもっていた。ゆえに、頼基が主君を折伏することによって、主君の不興をかうことは、それこそ一族の死活問題から、一族滅亡にすらもつながる大問題と発展することは当然なのである。だが、頼基の一徹な信心と至誠は、あえてこの至難事をやりとげたのである。
しかも、主君耳入此法門免与同罪事の次の文は、
「此より後には口をつゝみておはすべし。」(同744頁)
とあって、主君への折伏は、これ以降は口を閉じて、とどめておきなさいといわれている。剛直一途な頼基が末法の修行にふさわしく、真剣な弘教を展開したことがわかる。折伏して、正法に帰依させることが、主君に対する最高の報恩であるとの道理は理解できても、それを実践に移すときは、それこそ並々ならぬ勇気が必要である。ゆえに、大勇猛心をもって、主君を折伏した頼基は、もっとも勇気ある実践の人であるといえよう。
この頼基のひたぶるな信心の実践力は、その人柄をよく物語っていた。
頼基は、大聖人からしばしば、
「御辺は腹あしき人なれば火の燃ゆるがごとし。一定人にすかされなん。」(四条金吾殿御返事、1179頁)
とか、
「殿は一定腹あしき相かをに顕はれたり。」(崇峻天皇御書、1171頁)
指摘されているように、非常に短気で直情径行であった。ゆえに性急な性格が言動にあらわれるためか、人から恨みを買ったり、とかく不祥事を招きやすく、何かと大聖人も心配されて、細やかな指導をされている。
たとえば、崇峻天皇御書において、かって崇峻天皇が短気な性格のため家臣に暗殺されたという事件の例を引いて諌め、また孔子の九思一言(九つ思いをいたしてその末に言をいだすことで、一言でも発するためには、それなりの思索と熟慮をしたこと)などを用いて注意されている。しかし、このような一途な性格であったからこそ、竜口の頸の座、あるいは佐渡訪問、また主家からの迫害の際にも至信の誠を貫き通すことができたともいえよう。これらの行為は、たんに形のみでできるものではない。頼基自身の生命の底から、ほとばしり出たものであり、頼基ならではの信心の発露であったのである。
主君・江間氏とは、いつ頃から主従の関係にあったか、はっきりわからないが、四条家の領地が伊豆にもあることから、北条家が伊豆の土豪であったころからの主従関係はなかろかと思われる。江間氏は、前項でも述べたように、北条一門の一人で、あるいは執権職か、それに次ぐ連署の座についたであろうほどの有力な一族であった。しかしながら、名越朝時の時代から北条一門のなかでは不遇な立ち場におかれていた。
さらに、江間光時の代になって、時頼への謀反、また時宗執権時代には、教時ら時光の弟たちが時輔の乱に加担したなどして、四条家にとって主君は代々日蔭の立ち場にあった。にもかかわらず、四条家では、父・頼員、左衛門尉頼基と父子二代とも、実に忠誠を尽くしてきた。
頼基陳情(建治三年六月二五日)に、
「頼基は父子二代命を君にまいらせたる事顕然なり。故親父中務某故君の御勘気かぶらせ給ひける時、数百人の御内の臣等、心がはりし候ひけるに、中務一人最後の御供奉して伊豆国まで参りて候ひき。頼基は去ぬる文永十一年二月十二日の鎌倉の合戦の時、折節伊豆国に候ひしかば、十日の申時に承りて、唯一人箱根山を一時に馳せ越えて、御前に自害すべき八人の内に候ひき。」(頼基陳状、1134頁)
と、大聖人も父子忠誠を述べている。
この文の「故親父中務某故君の御勘気かふらせ給いける時」とは、寛元四(1246)年、名越光時が四代将軍・頼経と謀って、四代執権・時頼に謀反しようとして事前に発覚・領地を没収され、伊豆の江間に流された時、数百人の臣下がことごとく逆境にある光時を捨て去ったのであるが、ただ一人頼基の父、頼員は忠心を微動だにせず、伊豆へ供したことである。
また次の文の「頼基は去る文永十一年二月十二日の鎌倉の合戦の時」とは北条時輔の乱をさす。ここに文永十一(1274)年と記されているが、啓蒙第三十三巻に「此合戦の事王代一覧将軍譜等には見えず」とあり、また古抄に「十一年とは写伝の誤りなるべし。九年に作るべし」とあることから、文永九(1272)年二月十二日の時輔の乱と考えられる。
江間光時は、この時も謀叛の渦中にあり、疑いをもたれて、自刃せねばならぬ身となった。
このとき、対基陳状の文のごとく、伊豆の領地という出先にあった頼基は、ただ一人馬箱根山を越え、主君とともに自害すべき八人の中に加わったのである。幸い、江間家に対する謀叛の疑いは晴れ、主従ともに事なきを得たのであった。
このようにして、父子二代にわたって、二度までも主君の危急存亡の際に、筋を曲げることなく、忠心を貫き通したのであった。しかも頼基の忠誠は、前述のように、武士として主従の範疇だけでなく、主君の生命全体をも救って、成仏させようとしたのである。
頼基陳状にも、
「頼基が今更何につけて疎縁に思ひまいらせ候べき。後生までも随従しまいらせて、頼基成仏し候はゞ君をもすくひまいらせ、君成仏しましまさば頼基もたすけられまいらせむとこそ存じ候へ。」(頼基陳状、1135頁)
とある。
同状の最後には、
「此くの如き厳重の法華経にてをはして候間、主君をも導きまいらせむと存じ候故に、無量の小事をわすれて、今に仕はれまいらせ候。頼基を讒言申す仁は君の御為不忠の者に候はずや。御内を罷り出でて候はゞ、君、たちまちに無間地獄に堕ちさせ給ふべし。さては頼基仏に成り候ひても甲斐なしとなげき存じ候。」(同1135頁)と。
詳細については後述するが、これらの文は主家からの迫害に対する頼基の示した忠心である。この主君に対する姿勢は、ついに同僚の卑劣な讒言にも、主君の怒りにもくずれることなく、人間としての勝利を勝ち取っていくことになるのである。
さて、主君江間氏と四条家との関は、名越朝時−江間光時−江間史郎親時の三代に、四条頼員−四条頼基の二代で主従関係を結んでいたようである。
父・頼員と名越朝時の関係は、代々の主従ということから、その関係が考えられるだけで、はっきりしない。江間光時と頼員は、寛元四(1246)年の伊豆供奉の御文のごとくである。
では頼基と主君の関係はどうであったか、江間光時が執権・時頼への謀反を起こして、伊豆流罪となった時は、前述の生年によれば、頼基は十七歳のごろであるから、父・頼員とともに伊豆供奉をしているかどうかはわからない。
江間光時は、寛元四(1246)年以来、この謀叛によって、領地、官位は没収され、出家しているから、隠居の身であり、江間家の家督は、その子・四郎親時が務めていたようである。建治四(1278)年正月二十五日の四条金吾御書にも、
「えまの四郎殿の御出仕に、御ともの」(四条金吾殿御書、1197頁)
といわれており、その様子がうかがえる。
だが、大聖人が頼基に与えられた御書をみると、建治三(1277)年十二月の崇峻天皇御書や弘安二(1279)年九月十五日に認められた四条金吾殿御返事などでは、「入道殿」と江間氏に対して呼称されている。したがって、江間光時が出家して入道となり、隠居という立ち場とはなっていたものの、名越・江間一門内では、かなり権力をもっていたのではなかろうか。ゆえに、文永九年(1272)年二月の自界叛逆難すなわち北条時輔の乱にあって、弟たちとともに疑われたものと思われる。
以上から、頼基が仕えていた主君は、光時および親時の両方であったろう。
ここで問題となるのは建治三(1277)年に執筆されている頼基陳状において、光時のことを「故君」と呼称されていることである。これ以降の御書に「入道殿」と度々呼称されていることは先に述べたが、子・四郎親時は壮年時代に入道となっている様子はない。したがって、「入道殿」とは光時のことになる。
また「故君」については、日興上人が書写された頼基陳状の未再治本(弘安元年・1278年)には「君ノ大方ノ御不審お蒙せ給て」とあり、再治本(正和五年)には「故君ノ御勘気カフヲセ有ケル時)とあることから、弘安元(1278)年は生存し、正和五(1316)年には没していたと考えられている。
当時の宗教界は、平安朝の後期よりしだいに本来の目的を失いはじめ、鎌倉時代にあっては、むしろ互いに勢力を争うという混乱の様相を呈していた。とくに比叡山をはじめとして、園城寺等の各寺院は、しだいに多くの僧兵をかかえはじめ、武力をもってその勢力を維持していた。彼らは互いに反目し、対立しあいながら、寺を守るためには、朝廷や法皇にまで直訴した。その手段として、神輿や神木を奉じ、大挙入京し、朝廷や法皇を威嚇し、市中をあばれまわり、血なまぐさい殺戮を繰り返したのである。
大聖人の幼年時代に限ってみても、嘉録二(1226)年には金峯山宗徒が蔵王堂の焼失を高野山衆徒らの仕業だとして入京を計り、安貞元(1227)年には比叡山延暦寺衆徒の訴えにより、念仏僧・隆寛等を遠流に処している。また翌年
は興福寺衆徒が多武峯を焼き、このため延暦寺衆徒が蜂起して、近江国の興福寺領を没収した。さらに嘉禎元(1235)年には、延暦寺衆徒、神輿を奉じて入京、興福寺の衆徒も蜂起するなど、あいついで起こっている。こうして叡山を中心とする仏教界は、本来の姿から逸脱し、民衆を忘れ、むしろ民衆を腐敗と混乱の中に巻き込んでいった。しかもこうした僧侶の動き
と前後して、火災や地震、河川の氾濫、さらに飢饉や疫病等の災禍の波は容赦なく民衆の上におおいかぶさってきた。
とくに寛喜二(1230)年の大飢饉は、翌年になってからさらに餓死者を続出させた。なかでも京都では餓死者が道路に充満していたという。こうした惨状を前にしても為政者はいたずらに迷信を信じ、災難対冶のために、真言密教などによる加持祈禱を行
なわせた。「史料綜覧」によれば寛喜二(1230)年九月二十七日「幕府、五壇法ヲ修シテ、天変ヲ祈禱ス」(吾妻鏡)。翌年四月十一日「幕府、五壇法、一字金輪ノ修法ヲ行ヒテ、天変ヲ祈禱ス」(吾妻鏡)。同五月四日「幕府、四角四堺鬼気祭等ヲ行フ」(吾妻鏡)。同
五月十七日「幕府、炎早並二疫疾ノ事二依リテ、鶴岡八幡宮二大般若経ヲ読誦セシム」(吾妻鏡他)等々、祈禱が国家的行事として盛んに行われたことがわかる。
そして、これらの祈禱は、僧侶と権力者の結びつきをより強くし、僧侶を増強させる結果ともなった。日本の浄土宗の開祖・法然(1133年〜1212年)が登場したのは、これより少し前であったが、同じように不穏な社会情勢の中にあった。彼は比叡山にのぼり仏法を学び、さらに黒谷の叡空のもとで念仏の行に打ち込み、専修念仏に到達した。そして彼は、念仏こそ誰でもが往生できる易行であり、弥陀の本願にかなったもっとも正しい教えであると、民衆の中に説いていった。
これまで往生を願っても、読経や書写、造搭など、実際には限られた一部の貴族にしかできなかった浄土教に対し、学問や財力などを必要とせず、弥陀の称名のみで往生できるという、もっとも単純化した法然の教えは、社会不安に戦(おのの)く多くの貴族や武士階級に接近し、さらに一般民衆の間にも大いに受け入れられ、非常な勢いで広まっていった。
しかし、これら新勢力の台頭に、叡山の衆徒や興福寺等の旧仏教が黙視する筈はなく、念仏の禁止を朝廷に激しく訴えたため、ついに承元元(1207)年、念仏の弾圧にふみきり、法然を土佐へ流罪すことを決定した。
やがて法然は没するが、念仏は、その後も既成宗教から再三にわたって弾圧がなされた。しかし、朝廷や貴族の中でも念仏に帰依する者が少なくなく、さらに多くの弟子によって、京都
、鎌倉をはじめ全国的に広まっていった。とくに建長年間から文応のころの鎌倉では、長楽寺の智慶・鎌倉新善光寺の道阿、北条長時の保護を受けて建立された浄光明寺の真阿、悟真
寺(後に光明寺と改号)の然阿良忠らがその勢力をふるっていた。
一方、法然とは別に新たな力を持ちながら芽生えたのが栄西(1141年〜1215年)による禅宗である。彼は建久二(1191)年、二度目の渡宋をおえて、臨済宗を受け、帰国後、まず博多を中心に活動をはじめたが、既成宗教は栄西が新しい宗派を興すことを快く思わなかった。とくに比叡山の反発は激しく、ついに建久五(1191)年に、禅宗禁止の宣旨が下った。
彼はこの迫害に対し、興禅護国論を著わし、弁駁につとめた、そののち、正治元年(1199年)に鎌倉に移っていった。
政治の中心地・鎌倉では、この年正月頼朝が没し、再び大きな変動期を迎えていた。こうしたなかをぬって栄西は、幕府の上層に近づいていった。そして将軍・頼家や、政子の帰依を受け、翌年の頼朝一周忌法要には、導師をつとめるまでになった。また政子の願いで寿福寺を建立、彼はその住持となった。さらに京都にも将軍・頼家の外護で建仁寺を建立、その住持となり、地位の安定を得ることができた。
また宋より帰国した道元(1200年〜1253年)は、京都にのぼり、坐禅を正行とする曹洞禅をひらいた。彼は興聖寺を建立、積極的な活動に入ったが、叡山の排撃を受けた。その後、越前(現在の福井県)に永平寺を建立、地方武士や農民の間に、禅の普及をつとめていたが、宝治元(1247)年に鎌倉にはいった。この時、執権・北条時頼以下数々の人が道元の下に授戒をしている。
さらに寛元四(1246)年、宋から臨済禅の僧・蘭渓道隆(1213年〜1278年)が渡来し、翌年、鎌倉の寿福寺にはいった。時頼は道隆を手厚くもてなし、建長寺を建立、道隆によって開山した。このように幕府の最高権力者たちが積極的に禅宗に帰依して保護したため、禅宗は
鎌倉で着実にその根を張っていった。
こうして鎌倉に新しい仏教が勢力を伸ばす一方、京都の既成宗教も、新しい権力を求めて鎌倉にはいってきた。すなわち、天台、真言の僧侶は、関東周辺の地に根を下ろし、寺院を経営し弘教
の活動をはじめた。またある者は鎌倉八幡宮、永福寺などの主要な寺院にはいり、幕府の要職にある人々に取り入り、信者を集め勢力を伸ばしていた。
奈良地方でおもに慈善救済で名を得ていた律宗では、建長四(1252)年、忍性(良観。1217年〜1303年)が東国弘通を目指し下ってきた。彼は疫病で倒れた病人や難民の救済事業を行ない、しだいにその名を高めていった。またその師・叡尊(1201年〜1290年)が鎌倉をおとずれた時、北条時頼、実時をはじめ、一門の多くが叡尊の名声をしたい、彼に帰依して授戒している。その後、叡尊が帰還したあと、忍性が北条一門の帰依をそのまま受け継いだ。さらに忍性は鎌倉・極楽寺に別邸をかまえていた北条重時に近づき、幕府の権力者と結び、正元元(1259)年には重時が極楽寺を移転造営するにあたり、土地の選定にたちあうほどであった。重時は忍性を極楽寺の開山とした。そして翌年、重時が没した時は、忍性は葬儀の導師をつとめたのである。
このように建長五(1253)年、日蓮大聖人が立宗宣言をされる頃の鎌倉は、真言密教による加持祈祷や念仏が広まり、さらに禅宗の道隆、律宗の忍性等がたくみに権力者と結びつき、彼等の帰依のもとに、自己の名声と力をほしいままにしていた時代であった。
そのほか、さらに叡山をおりた京都の僧侶たちもしだいに東へ下っていき、鎌倉に流れていく者も少なくなかった。彼れは、宗教の実態を知らない民衆につけこみ、外面は聖人のごとく振る舞いながら名声を得、たくみに権力者に取り入っていく者が多かった。
こうした中に竜象房という僧といた。洛中で人の骨肉を食い、叡山を追われた彼は、やがて鎌倉に現われ、忍性をたよっていった。そして、建治三(1277)年、鎌倉の長谷、桑ヶ谷で仏法を知っているもののごとく説法していた。そこへ大聖人の弟子、三位房が行き、竜象と問答し、完膚無きまでに折伏した。これが「桑ヶ谷問答」である。この竜三房との問答の場に、頼基が加わっていたことから、日頃法華宗の四条金吾と妬んでいた同僚や、忍性房側の大聖人に敵対するものたちが、大げさな讒言を行ない、そのため、頼基は同僚からの迫害、主君の怒りを受けて領地没収問題へと発展し、数年以上にわたる受難の日々が続くのである。
文永十一(1274)三月、大聖人は佐渡御赦免となり、鎌倉に帰られた。この年、頼基は後世を願うあまり、江間氏を折伏したのである。
その結果は、主君の不興をかうことになってしまった。
頼基が主君から疎んじられるようになったのを見てとり、公然と頼基に迫害を加えてきたのが、江間家に仕える家臣たち、すなわち頼基の同僚である。
当時の武士の世界は、主従という上下関係つまり武士各人が主君とそれぞれに主従の契りを結ぶことによって成立しているのであって、その家臣導師の相互関係はほとんどないのである。ゆえに戦いにおいても、とかく個人の勲功のみが主となっており、そのため主君の恩寵の競争が激しく、しばしば闘争に及んだことが歴史書誌にも見えるほどである。
もともと武芸にすぐれ、医道も心得、家臣のなかでも、とくに主君から信頼を得ていた頼基に対る嫉みがあったことは、当然であろう。
それに加えて、禍いしたのは、頼基の性格であった。前述のように、短気で、思ったことをすぐ行動にあらわす頼基の性格は敵をつくりやすかったのである。
さらにまた、こうした表面的な因のほかに、一方、当時の宗教界の策動が頼基にも大きく働きかけていたことこそ、迫害の要因といえよう。
その中心は、主君・江間氏が尊敬する極楽寺良観である。彼は鎌倉進出の宗教界のなかで、とくに執権連署といった要路者と結びつき絶大な力を誇示していた。だが、彼は、日蓮大聖人との雨乞いに負け、公場対決をさけて、もっとも卑劣な手段で、大聖人および門下の人々に迫害を加えてきたのである。このことについては、頼基陳状に詳しく述べられているので、少し長いが、ここにその文をあげておく。
「去ぬる文永八年太歳辛未六月十八日大旱魃の時、彼の御房祈雨の法を行なひて万民をたすけんと申し付け候由、日蓮聖人聞き給ひて、此体は小事なれども、此の次いでに日蓮が法験を万民に知らせばやと仰せありて、良観房の所へ仰せつかはすに云はく、七日の内にふらし給はゞ日蓮が念仏無間と申す法門すてゝ、良観上人の弟子と成りて二百五十戒持つべし、雨ふらぬほどならば、彼の御房の持戒げなるが大誑惑なるは顕然なるべし。上代も雨祈に付いて勝負を決したる例これ多し。所謂護命と伝教大師と、守敏と弘法となり。仍って良観房の所へ周防房・入沢入道と申す念仏者を遣はす。御房と入道は良観が弟子、又念仏者なり、いまに日蓮が法門を用ふる事なし、是を以て勝負とせむ。七日の内に雨降るならば、本の八斎戒・念仏を以て往生すべしと思ふべし、又雨らずば一向に法華経になるべしといはれしかば、是等悦びて極楽寺の良観房に此の由を申し候ひけり。良観房悦びないて七日の内に雨ふらすべき由にて、弟子百二十余人頭より煙を出だし、声を天にひゞかし、或は念仏、或は請雨経、或は法華経、或は八斎戒を説きて種々に祈請す。四五日まで雨の気無ければ、たましゐを失ひて、多宝寺の弟子等数百人呼び集めて力を尽くして祈りたるに、七日の内に露ばかりも雨降らず。其の時日蓮聖人使ひを遣はす事三度に及ぶ。いかに泉式部と云ひし婬女、能因法師と申せし破戒の僧、狂言綺語の三十一文字を以て忽ちにふらせし雨を、持戒持律の良観房は法華・真言の義理を極め、慈悲第一と聞こへ給ふ上人の、数百人の衆徒を率ゐて七日の間にいかにふらし給はぬやらむ。是を以て思ひ給へ。一丈の堀を越えざる者二丈三丈の堀を越えてんや。やすき雨をだにふらし給はず、況んやかたき往生成仏をや。然れば今よりは日蓮怨み給ふ邪見をば是を以て翻し給へ。後生をそろしくをぼし給はゞ約束のまゝにいそぎ来たり給へ。雨ふらす法と仏になる道をしへ奉らむ。七日の内に雨こそふらし給はざらめ。旱魃弥興盛に八風ますます吹き重なりて民のなげき弥々深し。すみやかに其のいのりやめ給へと、第七日の申の時、使者ありのまゝに申す処に、良観房は涙を流す。弟子檀那同じく声をおしまず口惜しがる。日蓮御勘気を蒙る時、此の事御尋ね有りしかば有りのまゝに申し給ひき。然れば良観房身の上の恥を思はゞ、跡をくらまして山林にもまじはり、約束のまゝに日蓮が弟子ともなりたらば、道心の少しにてもあるべきに、さはなくして無尽の讒言を構へて、殺罪に申し行なはむとせし」(頼基陳状、1131頁)と。
雨乞いの対決に敗北した極楽寺良観は、幕府の権力者に無数の讒言を構え、大聖人をなきものにしようとした。その上、弟子たちにも日蓮の弟子供は火つけをする、鎌倉においてはならないとふれまわせるといった手段で、弾圧を加え、純真な門下の人々を苦しませたのである。
このため、多くの弟子たちは権力者によって、法華経を持つがゆえに、あるいは牢に入れられ、所領をとられ、あるいは鎌倉に追い出されるなどされたのであった。
さらに文永十一年(1274年)、大聖人が佐渡から帰られ、身延の山へ入られると、今度は門下に対して圧力を加えてきたのである。それは、文永の終わりから建治年間を中心として、弘安に入ってまでのことで、池上、鎌倉、富士、甲斐などあらゆる所に陰険なかたちであらわれたのであった。
富士方面では、弘安二年に頂点に達した大聖人門下の最大の法難、熱原の法難の兆しがあれわれたのは建治のはじめである。日興上人の活躍によって、富士・駿河方面では当時、多くの人々が入信してきた。建治元年(1275年)の六月には駿河の熱原郷・滝泉寺の寺家、下野房日秀、越後房日弁、少輔房頼円など僧侶をはじめとして、多くの在家の人々が改宗入信したのであった。また七月に入って富士の加島における日興上人の弘教活動によって、その方面で入信者をみた。これに対して、同年六月には滝泉寺の院主など謗徒の迫害が起きたのである。
大聖人は「浄蓮房御書」や「異体同心事」を差し出され、
「返す返すするがの人々みな同じ御心と申させ給ひ候へ。」(浄蓮房御書、882頁)
「あつわらの者どもの御心ざし、異体同心なれば万事を成じ、同体異心なれば諸事叶ふ事なし」(異体同心事、1389頁)
と迫害のなかの門下への激励をされている。
一方、甲斐の国の、身延の草庵に近い下山の郷の地頭を下山兵庫光基といった。阿弥陀堂を建立し、その子・因幡房に朝夕の勤行に阿弥陀経及び念仏を唱えさせていた。ところが、大聖人の教えを聞いて、因幡房がついにその弟子となるにおよび、父・光基は驚き因幡房を叱責したのである。このことを聞かれ、建治三年(1277年)六月、因幡房日永の名で、父・光基あてに大聖人が認められたのが「下山御消息」である。
頼基における主君の下文に対して御代筆された「頼基陳状」と同じように、日永の名において認められているが、内容は、律、真言、念仏、禅など諸宗の教義への破折、大聖人の広布への実践活動と幕府の迫害に対する厳しい指摘、三諌していれられず身延へ入られたことを述べて、大聖人の仏法の正義を詳しく示されているものである。この下山御消息においても、頼基陳状と同様、良観房に対して厳しい批判がなされている。当時、多くの社会事業、慈善事業などをやって、名僧として一応世間の人々には仰がれ、権力者や、その女房にすっかり取り入っていた良観である。その信頼度、その言動に左右されるのは、社会の上層部ほど強かっただけに、門下や弟子への反響も大きく、宗教弾圧となっていたことがうかがえよう。
それゆえに、大聖人は門下の人々に長上に対する御代筆には、詳細に良観の邪義を示され、また厳然たる破折をされているのである。
一方、池上兄弟とその父との信仰上の対立も、建治のはじめからである。とくに兄右衛門大夫に対する父・左衛門の二度の勘当までにおよぶ信仰上の対立は、良観に使嗾(しそう)されたことが、兵衛志殿御返事などに明瞭に述べられている。
「良観等の天魔の法師らが親父左衛門の大夫殿をすかし」(兵衛志殿御書、1270頁)
このように、期せずして、大聖人身延入山後、各地におきた門下への社会的な弾圧は、鎌倉にあって信者の中心的存在であった頼基にも襲っていった。門下の中心であった頼基は、社会的立ち場でも、主君からは信頼され、武芸、医術にもすぐれているというだけに、その動きは、他の門下にも大きな影響力があったことは当然であろう。大聖人にさんざんその邪義を責められ、破折された良観房らは、頼基を圧迫し、正法から遠ざけることによって、鎌倉の大聖人門下の勢力を滅失できると考えたようである。四条金吾殿御返事に、
「良観・竜象が計らひにてやぢゃうあるらん。起請をかゝせ給ひなば、いよいよかつばらをごりて、かたがたにふれ申さば、鎌倉の内に日蓮が弟子等一人もなくせめうしなひなん。」(不可惜所領の事、1161頁)
と大聖人も述べられている。
だが、四条家は、父の代をはじめとして、主君江間氏へは、並々ならぬ忠誠を尽くし主君もまた厚い信頼をよせていた。ゆえに、文永八年(1271年)の法難に際しても、他の大聖人門下が、所領をとられたり、牢に入れられたりしたなかで、頼基一人、邸も領地も、自身の身にも、何事も起こらなかったのである。大聖人も、
「我が身と申し、をや・親類と申し、かたがた御内に不便といはれまいらせて候大恩の主なる上、すぎにし日蓮が御かんきの時、日本一同ににくむ事なれば、弟子等も或は所領を・ををかたよりめされしかば、又方方の人人も或は御内内をいだし、或は所領ををいなんどせしに、其の御内になに事もなかりしは御身にはゆゆしき大恩と見へ候。」(八風抄、1117頁)
と申されて、その恩を忘れてはならないことを強調されている程である。
そこで良観らの策謀は日頃、頼基を妬ましく思っている同僚の家臣たちにむけられたのであろう。主君が熱心な良観の信者であったから、当然、その家臣たちにも、主君にならって良観に帰依していった者も多かったのである。
また、当時の武士階級は宗教に帰依している者が多く、ある者は念仏者であり、ある者は禅宗であり、ある者は真言を持つというように、それぞれ熱心な信者であった。
したがって、彼らの目に映る法華経の頼基は、阿弥陀の敵であり、禅、真言の法敵である。武士としての対抗意識とともに、法敵という意識まで、良観らの策謀者たちに強くうえつけられた同僚の武士たちによって、ついに数年以上も頼基迫害が続いたのである。武家社会と他宗による結びつきこそ、頼基迫害の要因であったといえよう。
大聖人の文面からして、文永十一年(1274年)頃からはじまった迫害は、主君の御勘気の解けた後、弘安二年(1279年)頃まで続いたようである。とくに、弘安二年(1279年)十月二十三日に大聖人からいただいた御文によれは、
「先度強敵ととりあひについて御文給ひき。委しく見まいらせ候。さてもさても敵人にねらはれさせ給ひしか。」(剣形書、1407頁)
と、かなりの強敵に襲われたことがわかる。弘安二年十月といえば、富士方面での熱原の法難の直後である。良観らの策謀が執拗なまでに、門下の方々を苦しめていたことが歴然とするのである。同僚の家臣たちによる迫害のおおきなものは、主君への讒言であった。
はじめは頼基の忠誠に深く信頼をよせていた主君であったが、陰険なる讒言と、桑ヶ谷問答に連座したことが、仰々しく伝えられるにいたって、ついに陰謀にのせられてしまったのである。
そして、頼基陳状を大聖人に代筆させる因となったのが主君あらの下状が、家臣を通じて渡され、ついに、所領問題へと発展し頼基はその苦境に立たされたのである。
ところで、気短な頼基が、このような迫害にあいながらも、大事を起こさず、長期間に渡って、耐えぬいたのは、大聖人の弟子を思う、慈悲の指導があり、一方、大聖人を生涯唯一の師と信じ、その指導を受けて立った信心が頼基にあったからであろう。
文永十一年(1274年)頃から、弘安二年(1279年)頃まで続いた同僚たちのさまざまの迫害に対して、大聖人は実に細々と、日常生活の一つ一つについて指導されている。愛弟子を心から心配され、もともと敵を作りやすい頼基の性格をよく見抜かれて、あるときは厳しく、あるときはさとすがごとく諄々と弟子の身を思われる心が数々の御書のなかにあふれている。
文永十一年(1274年)九月の主君耳入此法門免与同罪事には、
「かまえてかまへて御用心候べし。いよいよにくむ人々ねらひ候らん。御さかもり夜は一向に止め給へ。只女房と酒うち飲んで、なにの御不足あるべき。他人のひるの御さかもりおこたるべからず。酒を離れてねらうひま有るべからず。」(主君耳入此法門免与同罪事、744頁)
と指導されている。主君を折伏した結果、主君との間が微妙になってきた頼基に対し、いち早く動き出した同僚たちの気配をみて、早速の大聖人の指導である。同僚との付き合いだからといって、決して酒宴などに気軽に同席しないように、酔って心にすきをつくらないようにとの、心からの御注意である。武芸者に対しては、尋常の手段では太刀打ちできないので、このように酒をすすめ、油断させて、すきを狙う者もいたであろう。
文永十二年(1275年)三月六日には、四条金吾殿御返事をいただいている。
忠誠心の厚い頼基が、真心こめて折伏したにもかかわらず、案に相違して不興をかってしまったことえの失望の気持ち、待っていたかのように同僚たちから露骨な迫害、さらに心ない讒言に心を動かしていく主君など、さすがに信心強盛で剛毅な頼基も弱気となったらしい。
「行解既に勤めぬれば三障四魔紛然として競い起る」との止観の文も、大聖人からよくきかされたことであろうし、頼基も難があり、魔の競い起ることも覚悟のうえであったろう。だか、余りにもきびしい圧迫の前に、さすがの頼基も、くじけそうになってきたのであった。そして、弁阿闍梨日昭に、
「持たん者は『現世安穏後生善処』と承って、すでに去年より今日まで、かたの如く信心をいたし申し候処に、さにては無くして大難雨の如く来たり候」(此経難持書、775頁)
と問うたのである。
大聖人は、
「まことにてや候らん、又弁公がいつはりにて候やらん。いかさまよきついでに不審をはらし奉らん。法華経の文に『難信難解』と説き玉ふは是なり。此の経をきゝうくる人は多し。まことに聞き受くる如くに大難来たれども『憶持不忘』の人は希なるなり。受くるはやすく、持つはかたし。さる間成仏は持つにあり。此の経を持たん人は難に値ふべしと心得て持つなり。」(同775頁)
と指導激励されている。
建治に入ると、圧迫は熾烈をきわめてきたようだ。
四条金吾殿御返事(衆生所遊楽御書)には、
「法華経を持ち奉るより外に遊楽はなし。現世安穏・後生善処とは是なり。たゞ世間の留難来たるとも、とりあへ給ふべからず。賢人聖人も此の事はのがれず。たゞ女房と酒うちのみて、南無妙法蓮華経ととなへ給へ。苦をば苦とさとり、楽をば楽とひらき、苦楽ともに思ひ合はせて、南無妙法蓮華経とうちとなへゐさせ給へ。これあに自受法楽にあらずや。」(衆生所遊楽御書、991頁)
と、信心の姿勢について、優しい文の中にも厳しい仏法の道理を示されている。
四条金吾殿釈迦仏供養事には、
「此の文御覧ありて後は、けっして百日が間をぼろげならでは、どうれひならびに他人と我が宅ならで夜中の御さかもりりあるべからず。主のめさん時はひるならばいそぎいそぎまいらせ給ふべし。夜ならば三度までは頓病の由申させ給ひて、三度にすぎば下人又他人をかたらひて、つじをみせなんどして御出仕あるべし。」(四条金吾釈迦仏供養事、996頁)
と。
また、同僚の讒言が領地問題に及んだとき、頼基はあまりの仕打ちに訴訟しようとした。これに対しても、大聖人は訴訟することの是非を、仏法の帰依するものの立ち場として諄々と説かれている。
「されば此の事御訴訟なくて又うらむる事なく、御内をばいでず、我れかまくらにうちいて、さきざきよりも出仕とをきやうにて、ときどきさしいでてをはするならば叶ふ事も候ひなん。」(八風抄、1119頁)
と。
建治三年(1277年)六月、桑ヶ谷問答に連座したことによって、さらに迫害を増してきた。ついに家臣たちの讒奏は、主君・江間氏を動かし、下文が下ったのである。
法華経を第一としていく生活基準ではなく、是非につけて主君の所存に相随うという起誓文を提出するように、さもなければ領地を没収との下文は、頼基を妬む同僚や、陰でそそのかしている良観らにとっては、まさに彼らの思い通りであった。公然と敵対してくる彼らに対し、どんな小さなところにも、細かい注意を怠らぬようにとの慈悲あふれる大聖人の指導が、建治三年の頃の手紙にはみられる。
「されば同じくはなげきたるけしきなくて、此の状にかきたるがごとく、すこしもへつらはず振る舞ひ仰せあるべし。」(不可惜所領の事、1162頁)
「かへすがへす奉行人にへつらふけしきなかれ。」(同1162頁)
「御よりあひあるべからず。よるは用心きびしく、夜廻りの殿原かたらひて用ひ、常にはよりあはるべし。今度御内をだにもいだされずば十に九は内のものねらひなむ。かまへてきたなきしにすべからず。」(同1162頁)
「御辺は腹あしき人なれば火の燃ゆるがごとし。一定人にすかされなん」(世雄御書、1179頁)
「吾が家にあらずんば人に寄り合ふ事なかれ。又夜廻りの殿原はひとりもたのもしき事はなけれども、法華経の故に屋敷を取られたる人々なり。常はむつばせ給ふべし。又夜の用心の為と申し、かたがた殿の守りとなるべし。吾が方の人々をば少々の事をばみずきかずあるべし。さて又法門なんどを聞かばやと仰せ候はんに、悦んで見え給ふべからず。」(世雄御書、1179頁)
と。
大聖人の御指導通り、信心ひとすじで難局を乗り切った頼基にとって、新段階がおとずれたのは、建治三年(1277年)の九月であった。当時流行していた疫病に主君が倒れ。医術の甲斐もなく、はかばかしくなかった。医術にすぐれていた頼基は、主君に召し出されて久々の出仕をしたのである。もともと信頼していた主君であったから、家臣の讒言で心を動かされたものの、病状にあって、旧情を思いやったのであろう。当然、家臣たちは、おもしろうはずがない。ゆえに大聖人は久々の出仕の報に接すると同時に、細やかな注意を与えられている。
「此につけても、殿の御身もあぶなく思ひまいらせ候ぞ。一定かたきにねらはれさせ給ひなん。すぐろくの石は二つ並びぬればかけられず。車の輪は二つあれば道にかたぶかず。敵も二人ある者をばいぶせがり候ぞ。いかにとがありとも、弟ども且くも身をはなち給ふな。殿は一定腹あしき相かをに顕はれたり。いかに大事と思へども、腹あしき者をば天は守らせ給はぬと知らせ給へ。殿の人にあやまたれてをはさば、設ひ仏にはなり給ふとも彼等が悦びと云ひ、此よりの歎きと申し、口惜しかるべし。彼等がいかにもせんとはげみつるに、古よりも上に引き付けられまいらせてをはすれば、外のすがたはしづまりたる様にあれども、内の胸はもふる計りにや有らん」(崇峻天皇御書、1171頁)
と迫害の強くなることを示され、頼基の短気が禍を起こしやすいこと、弟たちの身内を大切にしていけば、いざという時に役立つこと、また、主君の邸の出入りに対しては、言動から姿勢までも注意するようとの指導である。
「敵も二人ある者をばいぶせがり候ぞ。いかにとがありとも、弟ども且くも身をはなち給ふな。殿は一定腹あしき相かをに顕はれたり。」(同1171頁)
「御をとどどもには常はふびんのよしあるべし。つねにゆぜにざうりのあたいなんど心あるべし。もしやの事のあらむには、かたきはゆるさじ。我がためにいのちをうしなはんずる者ぞかしとをぼして、とがありとも、せうせうの失をばしらぬやうにてあるべし。」(九思一言事、1198頁)
と。あるいはまた、
「上よりへやを給ひて居してをはせば、其の処にては何事も無くとも、日ぐれ暁なんど、入り返りなんどに、定んでねらうらん。又我家の妻戸の脇、持仏堂、家の内の板敷の下か天井なんどをば、あながちに心えて振る舞ひ給へ。今度はさきよりも彼等はたばかり賢かるらん。」(崇峻天皇御書、1172頁)
とも申されている。
また、頼基の身寄りか、郎党か、いずれにしても、ゆかりのある者で、法華経のゆえに邸を取り上げられた者が頼基の邸に出入りをしていたらしい。
大聖人は弟たちを大事にしていけば、万一のとき身内というものは頼りになることを示されているとともに、これら同じく正法に帰依している者同士を、大事にしていけば、魔のつけ狙うすきがないことも強調されている。また、夜回りの殿原たちとも、よく知り合っておけば、いざという時に役立つとも教えられている。
「いかに申すとも鎌倉のえがら夜廻りの殿原にはすぎじ、いかに心にあはぬ事有りとも・かたらひ給へ」(崇峻天皇御書、1172頁)
「四人は遠くは法華経のゆへ、近くは日蓮がゆへに、命を懸けたるやしきを上へ召されたり。日蓮と法華経とを信ずる人々をば、前々彼の人々いかなる事ありとも、かへりみ給ふべし。其の上、殿の家へ此の人々常にかようならば、かたきはよる行きあはじとをぢるべし。」(崇峻天皇御書、1172頁)
と。
主君の病も、頼基の医術によって快方に向かっていった。
建治四年(1278年)一月二十五日のお手紙によると、頼基は再び出仕し、主君のお供など日々忙しく、一日・二日のひまもないとの報を大聖人に送っていることがわかる。身延にあっても、鎌倉の様子は大聖人のもとに訪れる門下の人々によって、逐一報告されていたことであろう。一度は、主君の御勘気にあって、自宅に籠り、苦境を耐え忍んだ頼基が、いま晴れやかに主君の供奉をしているその様子が、他のどの家臣より一段と立派であるとの評判を聞かれ、大聖人は心からのお喜びのお手紙を送られている。しかし、そのなかでも、以前にも増して敵がねらうことを指導して、油断してはならない。
「されば今度はことに身をつゝしませ給ふべし。」(九思一言事、1197頁)
と、細やかな注意を与えておられる。また、
「今年かしこくして物を御らんぜよ。」(九思一言事、1199頁)
とも述べられ、時ということも教えられている。
微に入り細をうかがった大聖人の指導によって、頼基は、ついに主君はかえした所領を元どうりいただくとともに、さらに三倍の領地をたまわったのである。
だが頼基を妬む同僚の何人かは、理不尽な手段で頼基の命を奪おうとした。しかし、強敵との取り合いについても、日頃の大聖人の指導を純真に実践した頼基は、何ごともなく、無事を大聖人に報告できたのであった。
「さてもさても敵人にねらはれさせ給ひしか。前々の用心といひ、又けなげといひ、又法華経の信心つよき故に難なく存命せさせ給ふ。目出たし目出たし。」(剣形書、1407頁)
と大聖人からは、信心ゆえの存命であるとの御書をいただいているのである。さしもの敵人も、この頃から影をひそめているようである。数か年にわたる、さまざまな批判、圧迫を受けた頼基も、大聖人の指導のまま、毅然と戦いぬき、ついに勝利を期したのであった。
頼基陳状(建治三年六月二五日)に、
「宮仕へをつかまつる者上下ありと申せども、分々に随って主君を重んぜざるは候はず。上の御ため現世後生あしくわたらせ給ふべき事を秘かにも承りて候はむに、傍輩、世に憚りて申し上げざらむは、与同罪にこそ候まじきか。」(頼基陳状、1134頁)
と。また、
「後生までも随従しまいらせて、頼基成仏し候はゞ君をもすくひまいらせ、君成仏しましまさば頼基もたすけられまいらせむとこそ存じ候へ。」(頼基陳状、1135頁)
と述べられているが、これこそ主君に対する頼基の忠誠を如実にあらわしたものであった。ゆえに極楽寺良観に傾倒している主君の後世を願って、折伏したことは、頼基の至誠のいたすところにほかならなかったのである。
ところが、耳を傾けるどころか、かえって頼基の主君に対する忠誠の心にまで疑惑を抱きはじめ、あらぬ讒言に紛動されて、だんだんと自分を疎んじていく主君に、頼基は大きな失望の念を抱かずにはいられなかった。
建治二(1276)年七月にいただいた四条金吾釈迦仏供養事(建治二年七月一五日)によると、頼基は父母の孝養のため、供養の品を身延に届けたが、それとともに、近況を報じ、当時の心境を書き送っている。それは、主君への失望、周囲の迫害にあって、主家を去ろうとの意志であった。
大聖人は、
「御消息の中に申しあはさせ給ふ事、くはしく事の心を案ずるに、あるべからぬ事なり。(中略)日蓮がさどの国にてもかつえしなず、又これまで山中にして法華経をよみまいらせ候は、たれがたすけぞ。ひとへにとのゝ御たすけなり。又殿の御たすけはなにゆへぞとたづぬれば、入道殿の御故ぞかし。あらわにはしろしめさねども、定めて御いのりともなるらん。かうあるならば、かへりて又とのゝ御いのりとなるべし。父母の孝養も又彼の人の御恩ぞかし。かゝる人の御内を如何なる事有ればとて、すてさせ給ふべきや。かれより度々すてられんずらんはいかゞすべき。又いかなる命になる事なりとも、すてまいらせ給ふべからず。上にひきぬる経文に不知恩の者は横死有りと見えぬ。」(四条金吾釈迦仏供養事、995頁)
また、
「申させ給ふ事は御あやまちありとも、左右なく御内を出でさせ給ふべからず。まして、なからんにはなにとも人申せ、くるしからず」(同996頁)
と、御自身の立場までひかれて、どんなことがあろうとも、決して主君のもとを離れてはならない。それが主恩に対する真の報恩であると厳しく指導されたのである。
続いて頼基への左遷問題が起きてきたのである。あまりの同僚たちの中傷が激しかったため、主君がこうした処置をとらざるを得なかったのか、あるいは主君自身の配慮によるものかは、不明ではあるが、越後の国への領地替え問題が持ち上がってきたのであった。
ただでさえ、周囲の圧迫から逃れたい。主君のもとを離れたいとしている頼基の心境を大聖人は心配され、早速指導のお手紙をつかわされている。建治二(1276)年九月六日の四条金吾殿御返事である。
妙法を信じ、末法の御本仏を信ずる、頼基に苦境に落ち込むわけがない。定業亦能転の経文もあるし、天台の釈にも、定業すらのばすことができると述べられている。ゆえに、主君のもとを去るという行動はとらず、慎んでいなさいと、あくまでも頼基が主君に仕えることを強調されている。そして一方、主君に対しては、
「主の御返事をば申させ給ふべし。身に病ありては叶ひがたき上、世間すでにかうと見え候。それがしが身は時によりて臆病はいかんが候はんずらん。只今の心はいかなる事も出来候はゞ、入道殿の御前にして命をすてんと存じ候。若しやの事候ならば、越後よりはせ上らんは、はるかなる上、不定なるべし。たとひ所領をめさるゝなりとも、今年はきみをはなれまゐらせ候べからず。」(有智弘正法事、1043頁)
といいきりなさいと指導され、主君との接し方についても詳しく教示されたのである。
逆境にありながら、頼基は大聖人の指示に従って、信心第一の戦いを続けていくうちに、所領問題をめぐって、さまざまな動きがでてきた。頼基が身延の大聖人のもとに報告かたがた使いを送ったのは、半年後のことであった。久々の報告に対し、事が所領問題だけに、折り返し大聖人から、御本尊の御下附とともに指導の手紙が届けられた。
四条金吾殿御返事(建治三年四月)が、その指導である。冒頭から、
「所領の間の御事は上よりの御文ならびに御消息、引き合せて見候畢んぬ。此の事は御文なきさきにすいして候。」(八風抄、1117頁)
と申されて、苦境に立っている頼基の立ち場をよく理解され、最善の道は、主恩に対して、あくまで仕えきっていくことこそ従者の立ち場であると、信心を根本として指導されたのである。
とくに主君の恩については、
「我が身と申し、をや・親類と申し、かたがた御内に不便といはれまいらせて候大恩の主なる上、すぎにし日蓮が御かんきの時、日本一同ににくむ事なれば、弟子等も或は所領を・ををかたよりめされしかば、又方方の人人も或は御内内をいだし、或は所領ををいなんどせしに、其の御内になに事もなかりしは御身にはゆゆしき大恩と見へ候。このうへはたとひ一分の御恩なくとも、うらみまいらせ給ふべき主にはあらず。」(八風抄、1117頁)
と指摘され、頼基の忠誠をうながされている。そして、法華経ゆえに邸をとられた人たち(頼基の邸に出入りしている夜回りの人々であるから、なんらかのゆかりのあった人々であろう)が、大聖人がひきとめたにもかかわらず、訴訟してしまったことが、本抄にもみえている。頼基自身も領地問題の同僚の仕打ちに対して、訴訟を企てたらしい。大聖人は、訴訟など起こしてはならない。主君のもとを去らず、鎌倉にあって、時々出仕をしていれば、やがて、必ず頼基の思うところとなることを示されたのである。
これは仕事と信心のあり方についての根本的な指導である。環境が悪いからといって、自らの生活の基盤を崩していくようなことがあってはいけない。逆境と取り組みぬいてこそ、自己の宿命転換があり、ひいては社会をも開いていくと教示されたのであった。大聖人の微に入り細をうがつ、大慈悲の指導に従った頼基は、生涯、忠誠の士としての栄誉を勝ちとる因を築いたのである。
建治三(1277)年六月九日、桑ヶ谷問答が起こった。京都の比叡山から追われた竜象房が、いつの間にか、鎌倉にあらわれ、極楽寺良観に取り入って、大仏の西の門、桑ヶ谷に道場を構えた。そして、仏法の実態を知らない民衆に対して低い説法をして、人々から釈尊のように尊ばれていたのである。
大聖人の門下である三位公日行は敢然と法論を挑んだ。その時、桑ヶ谷近くに邸をもつ頼基に同行を依頼したのである。武士として主君に仕える身の頼基は、三位公と同行できず、おくれて参加した。竜象房は、すでに法話を終えて、「この満座の中に、仏法のとで御不審のあるものは、なにごとでも申しなさい」と豪語している時だった。それに立ち上がったのが三位公である。しばらく三位公と竜象房とのやりとりが続いたが、たちまちに三位公の理路整然とした応酬に、竜象房は口を閉じてしまった。
三位公の正論を聞き、初めて目ざめた一座の人々は、歓声をあげて、立ち去ろうとする三位公に手を合わせて「今しばらく、御法門をしてください」と押し留めようとした程だった。
しかし、卑劣で奸智にたけた竜象房は、都合のよいように事の次第を良観を通して、上部へ報告した。
一方、日頃、頼基に怨嫉している同僚たちは、よい機会とばかりに主君に対して、頼基が法話の席に兵杖を帯して乱入し、悪口狼藉をはたらいて三位公を勝利に導いたと報告したのである。
六月二十三日付をもって主君・江間氏から、これについて下状が出された。六月二十五日、江間氏の重臣・島田左衛門入道、山城民部入道の二人が使者として頼基への下し状が届けられたのである。
その下状の内容は、
「竜象御房の御説法の所に参られ候ひける次第、をほかた穏便ならざる由、見聞の人遍く一方ならず同口に申し合ひ候事驚き入って候。徒党の仁其の数兵杖を帯して出入すと云云。」(頼基陳状、1126頁)
という、なんの根拠もない虚言をもって始まり、結論として法華経を捨て、大聖人に帰依せぬ由との起請文を出されたい。もし起請の提出を拒むならば、所領を没収するというものであった。
即日のうちに、事の顛末と、下状と、そして同時に、たとえ主君のために二か所の所領を全て失い、身命に及ぶようなことがあろうとも、法華経を捨てるなどという起請文は書かないとの、固い決意を述べた誓状を認めて、身延の大聖人のもとへ送った。
報に接した大聖人は、頼基の健気な決意、強盛な信心に感じられ、即刻、主君の下状に対する陳状(頼基陳状、建治三年六月二五日)を代作され、さらに激励のお手紙を認めて、頼基へ遣わされたのである。
激励のお手紙(建治三年七月)は、
「去月二十五日の御文、同じき月の廿七日の酉の時に来たりて候。仰せ下さるゝ状と、又起請かくまじきよしの御せいじゃうとを見候へば、優曇華のさきたるをみるか、赤栴檀のふたばになるをえたるか、めづらし、かうばし。三明六通を得給ふ上、法華経にて初地初住にのぼらせ給へる証果の大阿羅漢、得無生忍の菩薩なりし舎利弗・目連・迦葉等だにも、裟婆世界の末法に法華経を弘通せん事の大難こらへかねければ、かなふまじき由辞退候ひき。まして三惑未断の末代の凡夫いかでか此の経の行者となるべき。設ひ日蓮一人は杖木瓦礫・悪口王難をもしのぶとも、妻子を帯せる無智の俗なんどは争でか叶ふべき。中々信ぜざらんはよかりなん。すへとをらずしばしならば人にわらはれなんと不便にをもひ候ひしに、度々の難、二箇度の御勘気に心ざしをあらはし給ふだにも不思議なるに、かくをどさるゝに二所の所領をすてゝ、法華経を信じとをすべしと御起請候ひし事、いかにとも申す計りなし。」(不可惜所領の事、1161頁)
との書き出しのように、頼基の至信の姿を誉められたのである。
そして、頼基が、法華経を捨てるとの起請を書いたなら、彼らの思うつぼとなり、鎌倉中の大聖人の弟子たちは皆責め立てられ、一人も残らず失ってしまうことになるであろうと、さらに堅い決意をうながされている。
また、大聖人が代筆された頼基陳状について、三位房をつかわそうと思ったが、病がはっきりしないので代わりの僧に託した旨を述べられ、
「だいがくの三郎殿か、たきの太郎殿か、とき殿かに、いとまに随ひてかゝせて、あげさせ給ふべし。」(不可惜所領の事、1162頁)
と、誰かに清書してもらうようにいわれているのは、大聖人の深い配慮がうかがわれる。
ついで御文には、
「これはあげなば事きれなむ。」(不可惜所領の事、1162頁)
と申されて、この陳状書をひとたび主君に差し出せば、事件は落着するであろう。急いで差し出さないで、内々に内部を整え、また他の同僚たちにも、騒ぐだけ騒がせておいて、しかる後に差し出したならば、この陳状は結局、鎌倉方にも披露されて、北条執権のところにも差し出されるようなことになるであろう。そのようなことになれば、禍も転じて幸いとなり、事態も好転すると指導され、陳状提出の時期も指示されている。
そして、
「此の陳状、人ごとにみるならば、彼等がはぢあらわるべし。」(不可惜所領の事、1162頁)
と確信を述べられ、主君に対しては、
「只一口に申し給へ。我とは御内を出でて、所領をあぐべからず。上よりめされいださむは法華経の御布施、幸ひと思ふべし」(不可惜所領の事、1162頁)
といいきってくるよう指導され、かえすがえすも奉行人にはへつらう様子をみせないように指示され、
「此の所領は上より給ひたるにはあらず、大事の御所労を法華経の薬をもってたすけまいらせて給びて候所領なれば、召すならば御所労こそ又かへり候はむずれ、爾時は頼基に御たいじゃう候とも用ひまいらせ候まじく候」(不可惜所領の事、1162頁)
(通解:此の所領は上よりいただいたのではない、主君の病を法華経の良薬をもって助けた恩賞としていただいた所領であるから、それを召し上げるならば、主君の病も再びその身にかえっていくであろう。その時になって、頼基に詫び状をもってきても、役には立ちません)
と、きっぱりといいきることを教えられている。
この陳状は、いつ頃、また主君に差し出されたものか否かについては明らかではない。
また前述の建治三(1277)年七月に送られた激励のお手紙のあと、さらに同年に認められたお手紙、四条金吾殿御返事(告誡書)があるが、月日はわからない。その御書に、
「かまへてかまへて、此の間はよの事なりとも御起請かゝせ給ふべからず。」(世雄御書、1179頁)
とあることから、頼基陳状をつかわされた後、そう幾日もたっているものではないようである。同書の最後に、
「又今度いかなる便りも出来せば、したゝめ候ひし陳状を挙げらるべし。大事の文なれば、ひとさはぎはかならずあるべし」(世雄御書、1179頁)
とあるところからみれば、この時点では、陳状はまだ差し出されていなかったことがわかる。
その二ヵ月後、九月十一日付で認められた崇峻天皇御書によると、主君は疫病にかかり、種々の治療も利き目がなく、ついに頼基出仕となったのである。
もし陳状が差し出されていれば、大聖人の予言通り、ひとさわぎは当然あったであろうし、頼基が大聖人に報告しないわけがない。それらしき消息のないところをみると、陳状を出すまでもなく、頼基の主君を思う一念は通じたようである。
さらに四条金吾殿御返事において、
「仏法と申すは道理なり道理と申すは主に勝つ物なり」(世雄御書、1179頁)
とも申されている。
さらに崇峻天皇御書(建治三年九月一一日)には、
「御内の人々には天魔ついて、前より此の事を知りて殿の此の法門を供養するをさゝえんがために、今度の大妄語をば造り出だしたりしを、御信心深ければ十羅刹たすけ奉らんがために、此の病はをこれるか。上は我がかたきとはをぼさねども、一たんかれらが申す事を用ひ給ひぬるによりて御しょらうの大事になりてながしらせ給ふか。彼等が柱とたのむ竜象すでにたうれぬ。和讒せし人も又其の病にをかされぬ。」(崇峻天皇御書、1170頁)
と述べられている。
仏法の賞罰は厳然としている。この九月、鎌倉に疫病が流行し、竜象房は倒れ、頼基を讒奏した者も病に倒れてしまったのである。主君・江間氏は、頼基を敵と思ってはいまいが、一度讒言を取り上げてしまったため、病気なって、そのように長引くであろうとの大聖人の厳しい指摘である。
だからといって、油断してはならないと、頼基自身に対しても厳しい指摘をなされている。また、出仕に際しては、万事控え目にして、身辺をよくよく警戒して、しかもなお、主君の治療に対しては、薬をすすめると共に法華経に祈っていくことを教えられている。
「此につけても、殿の御身もあぶなく思ひまいらせ候ぞ。一定かたきにねらはれさせ給ひなん。」(崇峻天皇御書、1171頁)
と。せっかく頼基を退けたにもかかわらず、主君の病によって、再び出仕してくることを心よく思わぬ敵に注意することをうながされている。
そして、少しでも敵意をもたれぬよう留意し、権力者の女房たちが、主君の病気はいかがですかと問われても、腰を低くして、私などとても力が及ばないと辞退したのですが、奉公の身なのでやむなく御治療していますと、目立たぬ服装でいきなさいと細やかな注意を与えられ、
「そこばくの人の殿を造り落とさんとしつるに、をとされずして、はやかちぬる身が、穏便ならずして造り落とされなば、世間に申すこぎこひでの船こぼれ…」(崇峻天皇御書、1171頁)
と申されて、多くの人たちがおとしいれようとしても、おとしいれられないから、もはや勝利の身であるのに、短気など起こして、彼らにおとしいれられたなら、船を漕いで、岸に着く直前にひっくり返るようなものであると、仏法の勝利をあくまで実現できるよう指導されている。
大聖人の教え通り、仏に祈りながら、誠心の治療をつくした結果は、ついに主君の病を快方に向かわせた。主君も、頼基の至誠にふれ、軽率にも、家臣の讒言を用いて、忠臣をもう少しで失うことを、おそらくは悔いたであろう。
「人身は受けがたし、爪の上の土。人身は持ちがたし、草の上の露。百二十まで持ちて名をくたして死せんよりは、生きて一日なりとも名をあげん事こそ大切なれ。中務三郎左衛門尉は主の御ためにも、仏法の御ためにも、世間の心ねもよかりけりよかりけりと、鎌倉の人々の口にうたはれ給へ。穴賢穴賢。蔵の財よりも身の財すぐれたり。身の財より心の財第一なり。此の御文を御覧あらんよりは心の財をつませ給ふべし。」(崇峻天皇御書、1173頁)
厳しい大聖人の指導である。だが、頼基は大聖人の指導を実践し、ついに、「主の御ためにも仏法の御ためにも 世間の心ねもよかりけり」との御文を身で読み切ったのであった。
長い冬は春となったのであった。
建治四(1278)年一月、主君から召されて、四郎親時の出仕の随行者の内に加えられるようになった。
この知らせを受けた大聖人は、
「なによりも承りてすゞしく候事は、いくばくの御にくまれの人の御出仕に、人かずにめしぐせられさせ給ひて、一日二日ならず、御ひまもなきよし、うれしさ申すばかりなし。えもんのたいうのをやに立ちあひて、上の御一言にてかへりてゆりたると、殿のすねんが間のにくまれ、去年のふゆはかうときゝしに、かへりて日々の御出仕の御とも、いかなる事ぞ。」(九思一言事、1197頁)
と喜ばれ、これはひとえに諸天の加護であり、法華経の功徳であると述べられている。
主君を折伏したことによって不興をかって以来三年四ヵ月、主君から下状まで与えられた最悪の時から半年後のことであった。主君の態度が、去年の秋、頼基の誠心と治療によって、悪疫から回復してのち、大きく変化したことは想像に難くない。
大聖人はさらに申されている。
「其の上円教房の来たりて候ひしが申し候は、えまの四郎殿の御出仕に、御とものさぶらひ二十四五、其の中にしうはさてをきたてまつりぬ。ぬしのせいといひ、かを・たましひ・むま・下人までも、中務のさえもんのじゃう第一なり。あはれをとこやをとこやと、かまくらわらはべはつじぢにて申しあひて候ひしとかたり候。」(九思一言事、1197頁)
と。
この晴れがましい頼基の雄姿こそ、三障四魔、三類の強敵に打ち勝った“信心の勝利”そのものであった。
大聖人は、知らせを喜ばれるとともに、孔子の九思一言を引き、敵にすきをうかがわれぬよう、出仕のとき、帰宅の際、あらゆる夜半の行動などに諸注意を細かく与えられている。
さて、建治四(1278)年二月二十九日、改元されて、弘安元年となった。その年の十月、頼基は四条金吾殿御返事をいただいた。
本抄の、
「御所領上より給ばらせ給ひて候なる事、まことゝも覚へず候。夢かとあまりに不思議に覚へ候。」(所領抄、1286頁)
との御文から、主君に返上していた所領が、頼基に与えられたことがうかがえるのである。
しかも、頼基に与えられた領地の内容は、
「かの処はとのをかの三倍とあそばして候上、さどの国のものゝこれに候が、よくよく其の処をしりて候が申し候は、三箇郷の内にいかだと申すは第一の処なり。田畠はすくなく候へども、とくははかりなしと申し候ぞ。二所はみねんぐ千貫、一所は三百貫と云云。」(所領抄、1286頁)
といわれるように、新しい領地は、かって没収された「とのおか」の三倍の面積があるというのである。その三ヵ郷の一つを「いかだ」といわれているが、現在のどこにあたるかは不明である。佐渡の国のものがその所をよく知っているとあるから、佐渡という説もあるし、また翌閏十月二十二日のお手紙に、
「信濃より贈られ候ひし物の日記」(石虎将軍御書、1291頁)
と認められているから、新しい領地は現在の長野県にあったのでないかとも考えられる。
また「とのおか」については、現在、長野県飯田市に上殿岡、下殿岡という地名があるが、弘安三(1280)年のお手紙に、
「殿岡より米送り給び候。」(殿岡書、1501頁)
と認められているから、この領地は一度主君に召し上げられたが、再び賜ったものと思われる。
このようにして、頼基は大聖人の法門を信ずるがゆえに、鎌倉中の諸人や、同僚の家臣はいうに及ばず、公達にもよく思われていなかった。しかも、主君が知行を与えようとした時にも、度々辞退もしているので、その行為は同僚の目には奇異に映ったであろうし、主君にとっては無礼な行為と思われていたであろう。主君の御内にあって数十人の同僚からは冷眼視され、今や兄弟も離れ去ってしまったという逆境のなかにあって、このような所領増加ということは、実に不思議なことである。
さらに、弘安二(1279)年四月二十三日にいただいた陰徳陽報御書によれば、
「いよいよかない候べし。いかにわるくとも、きかぬやうにてをはすべし。この事をみ候に申すやうにだにもふれまわせ給ふならば、なをなをも所領もかさなり、人のをぼへもいできたり候べしとをぼへ候。さきざき申し候ひしやうに、陰徳あれば陽報ありと申して、皆人は主にうたへ、主もいかんぞをぼせしかども、わどのの正直の心に主の後生をたすけたてまつらむとをもう心がうじやうにして、すねんをすぐれば、かかるりしゃうにもあづからせ給ふぞかし。此は物のはしなり。大果報は又来たるべしとをぼしめせ。」(陰徳陽報御書、1362頁)
と申されている。
この御文中に「なをも所領も・かさなり」「此は物のはしなり大果報は又来るべし」と大確信にたって激励されているが、同年九月十五日にいただいたお手紙に、
「いくそばくぞ御内の人々そねみ候らんに、度々の仰せをかへし、よりよりの御心にたがはせ給へば、いくそばくのざんげんこそ候らんに、度々の御所領をかへして、今又所領給はらせ給ふと云云。此程の不思議は候はず。此偏に陰徳あれば陽報ありとは此なり。」(源遠長流御書、1390頁)
とあるように、現実の功徳の現証は続々と頼基にあれわれたのである。
大聖人は、これ以上の不思議はないし、ひとえに陰徳あれば陽報ありとはこのことであり、
「我が主に法華経を信じさせまいらせんとをぼしめす御心のふかき故か。」(源遠長流御書、1391頁)
と、頼基の健気な信心を心から誉められている。
さらに大聖人はお手紙で、
「今こそ仏の記しをき給ひし後五百歳、末法の初め、況滅度後の時に当たりて候へば、仏語むなしからずば、一閻浮提の内に定めて聖人出現して候らん。(中略)日蓮が心は全く如来の使ひにはあらず、凡夫なる故なり。但し三類の大怨敵にあだまれて、二度の流難に値へば如来の御使ひに似たり。心は三毒ふかく一身凡夫にて候へども、口に南無妙法蓮華経と申せば如来の使ひに似たり。過去を尋ぬれば不軽菩薩に似たり。現在をとぶらうに加刀杖瓦石にたがう事なし。未来は当詣道場疑ひなからんか。これをやしなはせ給ふ人々は豈同居浄土の人にあらずや。」(源遠長流御書、1392頁)
ともいわれ、また、
「兄弟にもすてられ、同れいにもあだまれ、きうだちにもそばめられ、日本国の人にもにくまれ給ひつれども、去ぬる文永八年の九月十二日の子丑の時、日蓮が御勘気をかほりし時、馬の口にとりつきて鎌倉を出でて、さがみのえちに御ともありしが、一閻浮提第一の法華経の御かたうどにて有りしかば、梵天・帝釈もすてかねさせ給へるか。仏にならせ給はん事もかくのごとし。いかなる大科ありとも、法華経をそむかせ給はず候ひし御ともの御ほうこうにて仏にならせ給ふべし。」(所領抄、1287頁)
ともいわれ、誰人も想像だにしなかった頼基の所領の加増は、竜口法難に際して、殉死の覚悟で大聖人にお供をした。その絶大なる福運によるものであるとたたえられ、また、末法の御本仏日蓮大聖人に対し佐渡や身延に訪れて、御供養をしたその功徳により、また、お供したその果報によって、必ず成仏することは疑いないと、その確信を誉められたのである。
大聖人が頼基の妻・日眼女に与えられたお手紙から察すると、夫・頼基の多難な信仰生活をひたすら励ましてその信仰をまっとうさせたのは、この夫人の陰の力が大きかったことがうかがえる。騒乱の鎌倉の地にあって、幼い子供を抱える身で、頼基をはるばる佐渡の大聖人のもとへ送り、あるいは、主君や同僚のたび重なる迫害のもと、信仰を貫く頼基を励まし続けるなど、内助の功を発揮した。
日眼女の出世については資料もほとんど見当たらない。ただ文永十二(1275)年正月の大聖人からの御消息によると、
「今三十三の御やくとて、御ふせをくりたびて候へば」(四条金吾殿女房御返事、757頁)
とあることから、この年、三十三歳を迎えていることがわかる。
ところで、日眼女は、月満御前が生まれる前日の、文永八(1271)年五月七日お手紙をいただいている。
「懐胎のよし承り候ひ畢んぬ。それについては符の事仰せ候。日蓮相承の中より撰み出だして候。能く能く信心あるべく候。たとへば秘薬なりとも、毒を入りぬれば薬の用すくなし。つるぎなれども、わるびれたる人のためには何かせん。就中、夫婦共に法華の持者なり。法華経流布あるべきたねをつぐ所の玉の子出で生まれん。目出度く覚へ候ぞ。」(四条金吾女房御書、464頁)
と。喜びであるとともに、不安を伴う出産を前にした日眼女に対する大聖人の慈悲溢れるおはからいであった。
翌日の五月八日、無事、女子が誕生した。それを知られた大聖人から、早速お祝いの手紙が届いた。
「若童生まれさせ給ひし由承り候。目出たく覚へ候。殊に今日は八日にて候。彼と云ひ、此と云ひ、所願しをの指すが如く、春の野に華の開けるが如し。然ればいそぎいそぎ名をつけ奉る、月満御前と申すべし。(中略)定んで十羅刹女は寄り合ひて、うぶ水をなで養ひ給ふらん。あらめでたやあらめでたや。御悦び推し量り申し候。念頃に十羅刹女・天照太神等にも申して候。」(月満御前御書、462頁)
と。大聖人は心から喜ばれ、月満と命名されたのであった。
頼基夫妻の家臣は妙法流布の種を継ぐ新しい生命の誕生に希望に輝いていた。だが、思いもかけない事件が起こった。同年九月十二日夜半、大聖人の斬首が熊王丸によって四条家に伝えられたのである。日頃の大聖人への迫害、不穏な鎌倉のなかにあって、かねてから、覚悟はあったのであろうが、頼基・日眼女のおどろきはいかばかりであったろう。はだしのままで大聖人のもとへ駆けつける夫を送り出し、日眼女は必死で、大聖人の無事を祈ったことであろう。御本仏として、厳然と諸天の加護を得て、竜口の頸の座でことなきを得た大聖人は、やがて流罪地・佐渡へと出発される。この法難の影響は大きかった。信仰で結ばれた同士の多くが、さまざまな弾圧のために退転していったのである。主君・江間氏の庇護でその難を逃れた四条家だったが、翌文永九(1272)年二月、鎌倉の地で北条時輔の乱が起こり、主君・光時が疑われたため、頼基もその災厄にまきこまれた。無事、難を逃れた頼基に胸をなで下ろす間もなく、日眼女は頼基を佐渡へ送り出すことになった。
幼い子を抱えて騒然とした時世に、頼りになる家人もいない中、留守をあずかるその覚悟は健気であった。佐渡の一の谷を訪れた頼基に託して、大聖人は日眼女に次の文を認められている。
「はかばかしき下人もなきに、かゝる乱れたる世に此のとのをつかはされたる心ざし、大地よりもあつし、地神定んでしりぬらん。虚空よりもたかし、梵天帝釈もしらせ給ひぬらん。」(同生同名御書、596頁)
と。この騒がしい時に、はるばる佐渡の国へ夫を遣わされたあなたの心に感謝するものです。諸天も必ずご存知であると日眼女の信心を誉められている。
こうするうちに日眼女は経王御前をもうけたようである。この経王御前は幼くして病気にかかったのであろか、日眼女は大聖人に病気平癒の御祈念をお願いしている。抵抗力の弱い、いたいけな幼児、しかし大聖人は子供は親にとっての信心の鏡であると指導されている。
「夫について経王御前の事、二六時中に日月天に祈り申し候。(中略)経王御前にはわざはひも転じて幸ひとなるべし。あひかまへて御信心を出だし此の御本尊に祈念せしめ給へ。何事か成就せざるべき。」(経王殿御返事、685頁)と。
文永十一(1274)年二月、全く異例の処置として、大聖人が佐渡から帰られたのである。再びお会いすることのできないものと覚悟していただけに、門下にとって、その喜びは大きかった。四条家とておなじであった。ところが、夫・頼基が大聖人の弟子となって二十年近くの歳月を迎えようとしているのに、この二・三年は苦しいことばかりが続いていた。頼基に対する迫害、それは同僚からの嫉み、さらに、主君・江間四郎親時からも露骨に現われてきた。同年五月、大聖人が身延へ入山されるとすぐ、佐渡よりの帰還に信心の確信にもえた頼基が主君を折伏したことによって起こってきた。事態は意外にも険悪な空気をはらんでいったのである。
翌文永十二(1275)年、日眼女は三十三歳を迎えていた。この年は世間でいう厄年にあたる。長い信仰生活を経てきた日眼女は、心に動揺はないはずであったが、一抹の不安がないとはいえなかったろう。やはり大聖人に伺ってみようと、御供養の品々とともに質問を認めたのである。早速大聖人から日眼女のもとへ御返事がとどけられた。
「さゑもんどのは俗のなかには日本にかたをならぶベき物もなき法華経の信者なり。これにあひつれさせ給ひぬるは日本第一の女人なり。法華経の御ためには竜女とこそ仏はをぼしめされ候らめ。女と申す文字をばかゝるとよみ候。藤の松にかゝり、女の男にかゝるも、今は左衛門殿を師とせさせ給ひて、法華経ヘみちびかれさせ給ひ候ヘ。又三十三のやくは転じて三十三のさいはひとならせ給ふべし。七難即滅七福即生とは是なり。」(四条金吾殿女房御返事、757頁)
と厄年など何を恐れることがあろうか。法華経は変毒為薬の法門であり、信心によって宿命転換することができるのであるから、それを実証してごらんなさいとの力強い、また慈愛のこもる指導であった。心の中にある不安は吹き飛んで、信心への強い確信と希望が湧いてくる日眼女であった。
大聖人は夫・頼基のことを、「さえもん殿は俗の中・日本には・かたをならぶべき者もなき法華経の信者なり」と誉められてはいるが、だが頼基は短気である。裏を返せばそれは誠実とも一本気ともいえるが、それが禍いするところが今後の人生においてないとはいえないのであった。
文永十二(1275)年三月、主君や同僚との軋轢で夫・頼基の晴れない心境を知る日眼女は信仰の心にも不安定なものがあったようである。そんな四条家の事態を察知した大聖人の弟子日昭はすぐさま大聖人にこの事を告げたのである。その答えが四条金吾殿御返事である。
「此の経をきゝうくる人は多し。まことに聞き受くる如くに大難来たれども『憶持不忘』の人は希なるなり。受くるはやすく、持つはかたし。さる間成仏は持つにあり。此の経を持たん人は難に値ふべしと心得て持つなり。」(此経難持御書、775頁)
と。
こうして、いよいよ頼基にとって、競い起る障魔との戦いが始まったのである。法華経の法門、変毒為薬をわが身に実証できるかどうか。「法華経の四条金吾」の名をあげるか否かは、ひとえに頼基のこれからの戦いにかかっているのであ
った。
それはなによりも日眼女が仏法を理解して、信仰を深め、頼基の力になることである。大聖人は日眼女を厳しく指導された。
折りしも、鎌倉に大火が起こった。さいわいに難を逃れた一家はその時の様子を大聖人に報告した。ほどなくして身延からの御返事が届いた。その中に日眼女の信心に対する厳しい
指摘があった。
「又女房の御いのりの事、法華経をば疑ひまいらせ候はねども、御信心やよはくわたらせ給はんずらん。如法に信じたる様なる人々も、実にはさもなき事とも是にて見て候。それにも知ろしめされて候。まして女人の御心、風をばつなぐともとりがたし。御いのりの叶ひ候はざらんは、弓のつよくしてつるよはく、太刀つるぎにてつかう人の臆病なるやうにて候べし。あへて法華経の御とがにては候べからず。よくよく念仏と持斎とを我もすて、人をも力のあらん程はせかせ給へ。譬へば左衛門殿の人ににくまるゝがごとしと、こまごまと御物語り候へ。いかに法華経を御信用ありとも、法華経のかたきをとわりほどにはよもおぼさじとなり。」(王舎城事、975頁)
と。
たとえ御本尊を信じても、法華経の敵に少しでも心を引かれるならば、その祈りには感応はないとの指導である。信仰には一分の妥協はないという大聖人の気魄が文面にあふれている。
大聖人の厳しい指導を受けた日眼女がそれまでの弱い信心を反省し、夫・頼基ともに苦境を切り開いていった過程は先に述べた通りである。
弘安二(1279)年、日眼女は、三十七歳を迎えようとしていた。三十七歳は女性の後厄にあたる。日眼女は厄除の祈念をこめて、教主釈尊の木像を一体造立すると、御供養といっしょに大聖人のもとへ送った。やがて大聖人から
、
「譬へば頭をふればかみゆるぐ、心はたらけば身うごく、大風吹けば草木しづかならず、大地うごけば大海さはがし。教主釈尊をうごかし奉ればゆるがぬ草木やあるべき、さわがぬ水やあるべき。」(日眼女釈迦仏供養事、1351頁)
との指導があった。どんな障魔も妙法の偉大な力の前には屈服していくことを確信して進んでいきなさいと日眼女を励まされたのである。そして最後に、日本国の女人があげて念仏の信者となっているなかで、あなただけが法華経を信じて釈迦像を造立するのは不思議といえば不思議である。
「二十九億九万四千八百三十人の女人の中の第一なりとをぼしめすべし。」(同1353頁)
と愛でられている。「女人の中の第一なり」とは、その夫の社会的地位ではない。まして、いま得た名誉でもない。ただ信仰を貫いたゆえであり、日眼女の精進を誉められ
たのであった。
頼基は、主君に忠誠を貫いた人物であると同時に、医術にもすぐれた技をもっていた。
建治三(1277)年の始め、それまでくすぶっていた疫病がしだいに勢いを増し、鎌倉の地をおそいはじめた。この流れは秋頃には、ついに頼基の主君・江間四郎親時にまで及んだ。もちろん家臣たちは八方手を尽くし、名医をよんで治療にあたったと思われるが、結果ははかばかしくなかった。
ところが、頼基が以前にも主君の病を治し、その功により所領を賜ったことなどもあったため、ついに謹慎中の頼基が召し出され、主君の病気をみることになった。
頼基は、こうした状況を大聖人に報告した。大聖人もこのたびの主君の病気については、頼基の
「御信心深ければ十羅刹たすけ奉らんがために、此の病はをこれるか。」(崇峻天皇御書、1170頁)
と述べられ、同僚がまだ頼基をおとしいれようとしているのであるから、以前にもまして、同僚を敬っていかなければならないと注意されている。また、同じく崇峻天皇御書には、
「若しきうだち、きり者の女房たちいかに上の御そらうとは問ひ申されば、いかなる人にても候へ、膝をかゞめて手を合はせ、某が力の及ぶべき御所労には候はず候を、いかに辞退申せどもたゞと仰せ候へば、御内の者にて候間かくて候とて、びむをもかゝず、ひたゝれこはからず、さはやかなる小袖、色ある物なんどもきずして、且くねうじて御覧あれ。」(崇峻天皇御書、1171頁)
などと、大聖人は、まことに細やかな指導を頼基に与えられている。
こうして大聖人の指示を受けながら、頼基は、一心に真心をこめて主君の病を治療したのであろう。その利き目があって、やがて病は快方へと向かい、さらに主君の勘気も、自然にとかれたのである。そして、翌年の建治四(1278)年正月、主君の出仕の供に加えられたのである。その時の様子については、
「えまの四郎殿の御出仕に、御とものさぶらひ二十四五、其の中にしうはさてをきたてまつりぬ。ぬしのせいといひ、かを・たましひ・むま・下人までも、中務のさえもんのじゃう第一なり。あはれをとこやをとこやと、かまくらわらはべはつじぢにて申しあひて候ひしとかたり候。」(九思一言事、1197頁)
とあり、武士の面目をほどこしたのであった。
このように、主君との危機を危く救ったのは、頼基の医術であったともいえる。
こうした頼基と主君の関係は、あたかも古代インドにおける名医・耆婆と阿闍世王との関係に類似しているといえる。
耆婆は、生まれながらにして治病の具をもっていたといわれ、医王の名をはせるほどの名医であった。彼は摩竭陀国の阿闍世王に、大臣として仕えた。この阿闍世王は提婆達多を師と仰いでいたが、耆婆は深く釈迦に帰依していた。したがって阿闍世王は、耆婆が仏弟子であることを快く思っていなかった。
むしろ阿闍世王は提婆達多にそそのかされて、釈迦に帰依していた父・頻婆娑羅王を幽閉し、そのうえ、母をも殺そうとした。この時、耆婆は阿闍世王を懸命に諌め、ようやく
思い留まらせることができた。しかし今度は、阿闍世王は悪像を放って釈迦を殺そうとするなど、ことごとく釈迦に敵対していった。
こうした阿闍世王の敵対行為の結果は、やがて厳然とあらわれたのであった。すなわち、阿闍世王が五十歳になった二月十五日、大悪瘡が全身にできてしまった。すでに名医・耆婆大臣の治療では及びもつかず、三月七日に死ぬことを予言されてしまった。その時になって、初めて阿闍世王は、自分の正法誹謗の罪を深く感じ、ついに耆婆大臣のすすめによって、釈迦の下に行き、仏に帰依したのであった。釈迦はこの時、阿闍世王のために涅槃経を説き、これによって、身の病はたちまちに治り、さらには
四十年もの寿命を延ばすことができたのである。こうして深く改心し、仏法に帰依した阿闍世王は、釈迦滅後には仏典の結集をはかるなど偉業を残している。
このように、仏法に帰依しない阿闍世王を主君と仰ぐ名医・耆婆の立ち場は、きわめて困難な状態におかれていた。そうした立ち場にありながらも、耆婆は阿闍世王を諌め、韋提希夫人(阿闍世王の母)を救い、最終的には阿闍世王を釈迦に帰依せしめたことは、耆婆がいかに強信者であり、同時にすぐれた忠臣であったかを物語るものである。
この耆婆大臣について、大聖人は頼基陳状(建治三年六月二五日)の中で、次のように述べられている。
すなわち、
「阿闍世王は提婆・六師を師として教主釈尊を敵とせしかば、摩竭提国皆仏教の敵となりて、闍王の眷属五十八万人、仏弟子を敵とする中に、耆婆大臣計り仏の弟子なり。大王は上の頼基を思し食すが如く、仏弟子たる事を御心よからず思し食ししかども、最後には六大臣の邪義をすてゝ耆婆が正法にこそつかせ給ひしか。」(頼基陳状、1133頁)
また、
「阿闍世王は仏の御かたきなれども、其の内にありし耆婆大臣、仏に志ありて常に供養ありしかば、其の功大王に帰すとこそ見へて候へ」(崇峻天皇御書、1170頁)
とある。
まさしく、鎌倉の武士、さらには名医・頼基の立ち場は、大臣・耆婆の立ち場に符号している。
大聖人は、頼基こそ鎌倉時代の耆婆なりとあえて先例を引かれ、苦境にあえぐ頼基を激励されたのであろう。こうした大聖人の信頼に、頼基もまた、どれほどか感涙にむせんだことであろう。そして、さらに法華経の頼基として、妙法の名医として生き抜くことを、深く心に誓ったことと思う。
一方、頼基は大聖人のもとへたびたび薬を送り、医学の面からも大聖人をお守りしていた。とくに、身延に入山されてからの大聖人は、しばしば持病のため、健康がすぐれず悩まれたようである。
弘安元(1278)年六月に頼基に与えられたお手紙には、
「将又日蓮が下痢去年十二月卅日事起こり、今年六月三日四日、日々に度をまし月々に倍増す。定業かと存ずる処に貴辺の良薬を服してより已来、日々月々に減じて今百分の一となれり。」(二病抄、1240頁)
とあり、頼基の薬を服されよくなられたことがうかがえる。またこのことは同じ日、兵衛志に与えられたお手紙の中にも、
「はらのけは左衛門どのの御薬になをりて候」(兵衛志殿御返事、1241頁)
とあり、大聖人も少なからず喜ばれたものと拝する。
こうして、大聖人の病は頼基から送られる薬により、一時はよくなったものの、まだ時折は病苦に悩まされていたようである。同年九月十五日の四条金吾殿御返事には、
「日蓮が死生をばまかせまいらせて候。全く他のくすしをば用ゐまじく候なり」(源遠長流御書、1392頁)
とあり、大聖人の頼基に対する非常な信頼がしのばれる。このお手紙をいただいて後、閏10月に頼基は直接身延を訪れお見舞い申し上げている。
医術に秀でた頼基が、大聖人の臨床で治療に最善をつくしたことはいうまでもない。その至誠と医薬により、大聖人の病も平癒し、数日間の滞在の後、頼基は身延をあとにした。頼基が無事鎌倉に着いた報に接し、大聖人がしたためられたお手紙には
、
「又身に当たりて所労大事になりて候ひつるを、かたがたの御薬と申し、小袖、彼のしなじなの御治法にやうやう験候ひて、今所労平癒し本よりもいさぎよくなりて候。弥勒菩薩の瑜伽論、竜樹菩薩の大論を見候へば、定業の者は薬変じて毒となる。法華経は毒変じて薬となると見えて候。日蓮不肖の身に法華経を弘めんとし候へば、天魔競ひて食をうばはんとするかと思ひて歎かず候ひつるに、今度の命たすかり候は、偏に釈迦仏の貴辺の身に入り替はらせ給ひて御たすけ候か。」(石虎将軍御書、1291頁)
とあるところから、大聖人の病がなおり、健康をとりもどされた御様子がわかる。あわせて、大聖人からこのうえなき感謝の言葉をもいただいている。
こうして、山中にこもられた大聖人の健康を気づかわれ、薬を差し上げ、お守りしつづけてきた頼基に対し、大聖人は、弘安二(1279)年、富木常忍の妻に与えられた書状の中で
、
「しかも善医あり。中務三郎左衛門尉殿は法華経の行者なり。」(可延定業御書、760頁)
と述べられている。
大聖人より「善医」との言葉をいただいた頼基は、どれほど喜ばしく、誇らしく思ったことであろう。このように、医学の面ですぐれた名をあげた頼基こそは、まことの法華経の行者といえよう。
しかし、こうして「善医」といわれるほどの医術を、武士の頼基がどのようにして体得したかは定かではない。あるいは、中務家の家系が、代々の医師であったかもしれないし、また頼基自身が、どこかで医学の修得をしたのであろう。
大聖人一門にとって建治年間は苦難の年であった。鎌倉の地において、頼基が主君から執拗な迫害を受けているとき、駿河地方の信者もまた同じく、信仰の故に国家権力における弾圧を受けながらも、力強い戦いを展開していた。
すなわち、日興上人の折伏によって大聖人の弟子となっていた下方熱原滝泉寺大衆、日秀・日弁・日禅および百姓たちに対して滝泉寺の院主代・平左近入道行智を中心に弥陀信仰の徒が、数々の圧迫を加えていた。だが、法論の上ではかなわないので、ついに政所の役人と結託し、弘安二(1279)年九月二十一日「熱原法難」の名で知られる大法難を惹き起こした。
駿河の地は得宗領である。北条氏の政治基盤であるこの地で、いったん事件が起これば強力な政治的弾圧が加えられることを熟知していた大聖人は、機会あるごとに心をあわせて信心に励むよう指導されていた。しかしながらついに事態は重大な局面を迎えた。
熱原法難の原因は滝泉寺申状に次のようにある。
「訴状に云はく、今月二十一日数多の人勢を催し、弓箭を帯し、院主分の御坊内に打ち入り、下野房は乗馬相具し、熱原の百姓紀次郎男、点札を立て作毛を苅り取って日秀の住房に取り入れ畢んぬ云云取意。」(滝泉寺申状、1402頁)と。
上の訴状は行智の作成したものだが、これが捏造された訴状であることはいうまでもない。行智の手によって仕かけられた事件である。行智は得宗領駿河を治めるために置かれた下方政所と結託していた。九月二十一日、日秀に手伝って大聖人門下の百姓たちが稲刈りを行っていたところに、行智らは寺中のみならず政所の下役人まで集め、武器をもって取り囲んだ。門下の人達は初めは耐えたが、ついに鎌などで応戦した。だが多勢に無勢、ついに百姓二十名は逮捕され、不当にも刈田狼藉の当事者として鎌倉に拘引されたのである。
事態を聞き知った大聖人は、法難の真最中に弟子一同に対して聖人御難事を差し出された。そして、
「余は二十七年なり。」(聖人御難事、1396頁)
と述べられ、大聖人が立宗以来二十七年にして一閻浮提総与の大御本尊建立という出世の本懐をとげられたことが示されている。
そして法難による動揺を考えられたのであろう。熱原の人々に対しては、
「彼のあつわらの愚癡の者どもいゐはげましてをとす事なかれ。彼等には、たゞ一えんにをもい切れ、よからんは不思議、わるからんは一定とをもへ。ひだるしとをもわば餓鬼道ををしへよ。さむしといわば八かん地獄ををしへよ。をそろしゝといわばたかにあへるきじ、ねこにあへるねずみを他人とをもう事なかれ。」(聖人御難事、1398頁)
と。大聖人の法難にあたっての弟子への指導は、厳しいものであった。
平左衛門尉の念仏称名の強要に屈せず、神四郎等(神四朗、弥五郎、弥六郎の三人)はひたすら題目を唱えつつ斬首されたのである。神四郎等はわずか入信一年にしてこの法難に立ち向かったという。聖人御難事は、最後に、
「さぶらうざへもん殿のもとにとゞめらるべし。」(聖人御難事、1398頁)
とあるように、別しては頼基に与えられたものである。当時の信者の第一人者として、頼基は大聖人の指示を受け、捕らえられている神四郎たちの激励、大聖人門下の人々への指導など、活躍したことが想像される。
頼基の手当てと投薬によって、一時、小康を取り戻された大聖人ではあったが、もはや余命いくばくもないと思われた御様子が池上兄弟、上野殿母御前へ宛てた御消息に述べられている。
「日々の論義、月々の難、両度の流罪に身つかれ、心いたみ候ひし故にや、此の七八年が間年々に衰病をこり候ひつれども、なのめにて候ひつるが、今年は正月より其の気分出来して、既に一期をわりになりぬべし。」(八幡宮造営事、1556頁)
また、
「今年は春よりこのやまいをこりて、秋すぎ冬にいたるまで、日々にをとろへ、夜々にまさり候ひつるが、この十余日はすでに食もほとをどとゞまりて候」(上野殿母尼御前御返事、1579頁)
と。医者であった頼基が大聖人のお身体を気づかい、その回復に尽力したことはいうまでもない。弘安五(1282)年九月ごろになると大聖人の御病気は進み、身延の山中では養生もできないので、頼基は常陸の湯へとお供した。だが池上に着くと大聖人は再び起たれず、ついに入滅されたのであった。
その時の頼基の心は断腸のおもいであったろう。御葬送において池上宗仲とともに幡を捧げたことは周知の通りである。また大聖人の遺骨を身延の地に埋葬し、この傍に端場坊をつくって喪に服したという説もある。
晩年、頼基は四条家の領地といわれる甲州内船(現在の山梨県南巨摩郡南部町内船)に移り、余生を送ったのである。大聖人の身にふりかかった大難にお供した頼基は、その晩年もまた大聖人をお護りし続けたのである。頼基の没年代については正安二(1300)年説と永仁四(1296)年説とがあるが、前者をとっておく。いずれにしても七十歳前後で他界と考えられる。
頼基は実践の人であった。大聖人の御入滅の二年前、すなわち弘安三(1280)年十月にいただいた御消息には次のように述べられている。
「何となくとも殿の事は後生菩提疑ひなし。何事よりも文永八年の御勘気の時、既に相模の国竜口にて頚切られんとせし時にも、殿は馬の口に付きて足歩赤足にて泣き悲しみ給ひ、事実になれば腹きらんとの気色なりしをば、いつの世にか思ひ忘るべき。それのみならず、佐渡の島に放たれ、北海の雪の下に埋もれ、北山の嶺の山下風に命助かるべしともをぼへず。年来の同朋にも捨てられ、故郷へ帰らん事は、大海の底のちびきの石の思ひして、さすがに凡夫なれば古郷の人々も恋しきに、在俗の宮仕へ隙なき身に、此の経を信ずる事こそ希有なるに、山河を陵ぎ蒼海を経て、遥かに尋ね来たり給ひし志、香城に骨を砕き、雪嶺に身を投げし人々にも争でか劣り給ふべき。」(殿岡書、1501頁)と。
御本仏日蓮大聖人より、このように誉められたように、その一途な性格とはいえ、誠に強盛な信心を生涯貫いた四条金吾頼基であったのである。