
南条時光(1259年~1332年、以下、時光と略称する)は、正元元年(1259年)、駿河国富士郡上方庄上野郷(静岡県富士宮市の一部)の地頭南条兵衛七郎の次男として誕生した。
時光の生涯は、鎌倉幕府の中期から後期にある。それは北条氏執権政治の安定期から、やがて内管領へ権力が移行し、幕府の支配体制である御家人制の崩壊、蒙古襲来以後の経済的破錠などが表面化していく激動の時代であった。
時光は、幼少のころ父母について入信し、大聖人が身延に入山されてからはたびたび参詣をして、数多くの御供養を捧げて報恩の誠を尽くすなど、生涯、純真な信仰を貫いた鎌倉武士であった。大聖人も時光に期待されて指導に心をくだかれたことは、時光およびその一族が賜書を多数(60編あまり)戴いていることからも拝することができよう。
いま、時光の事績を概略すると次のようになろう。
第一に、身延山中におられる日蓮大聖人のもとへたびたび参詣し、また数々の御供養を捧げていること。
第二に、大聖人が出世の本懐である本門戒壇の大御本尊を御図顕になる機縁となった熱原法難に際し外護の活躍をしたこと。
第三に、大聖人滅後、謗法の地となった身延を離山された日興上人を自邸にお招きし外護申し上げたこと。
第四に、自領の上野郷内の大石ヶ原を寄進し、大石寺の開基檀那としてその建設と維持発展に尽力したこと。
さらに、晩年には入道し大行と称し、先立って没した妻・乙鶴の菩提を弔うために自邸を妙蓮寺とするなど、時光は富士大石寺の開基檀那としての任を全うし、日興上人に先立つこと一年、正慶元年(1332年)5月1日、74歳の生涯を終えた。
ここでは、時光の略伝を次の3点に分けてのべている。
第一に、南条家の家系や社会的地位、家族構成などを考察し、
1.1.本貫の地
1.2.社会的地位
1.3.家族構成
1.4.時光の所領
第二に、時光の信仰、とりわけ、熱原法難、大石寺創建における時光の功績について述べ、
2.1.日興上人との道契
2.2.熱原法難の経過
2.3.熱原法難での時光
2.4.時光の病気
2.5.大聖人御入滅
2.6.身延離山と大石寺建立
2.7.時光の晩年
2.8.時光の子孫
第三に、大聖人への御供養と、与えられた御書について一覧する。
南条時光の父・兵衛七郎の
南条から
律令制下の田方郡には、新居、小河、直見、佐婆、鏡作、茨城、依馬、八邦、狩野、天野、吉妾、有弁、久寝の13郷があり、北条と南条は
「吾妻鏡」の文治五年(1189年)六月六日の条には「北条(時政)殿の御願として、奥州(藤原泰衝)征伐の事を祈らんがために、伊豆国北条の内に伽藍の営作を企てらる…名づけて
同じく、建保三年(1215年)正月八日の条には北条時政が六日「北条郡において卒去す」と記述されていることから、田方郡にあった北条が、時政の死去までに北条郡となっていたと思われる。さらに年代が下って暦応二年(1339年)四月五日付の「足利直義寄進状案」に「寄進 伊豆国円成寺。同国北条五箇郷(原木・中条・山本・南中村・肥田)…」(「北条寺文書」『静岡県史料』1輯295頁)とあるところから、鎌倉時代末期に原木・中条・山本・南中村・肥田の五郷が成立しており、南条はいずれかの郷に入っていたようである。
南条が苗字本貫の地であったことは、その姓から知ることができる。当時は、居住地の名を頭において呼称する習慣があった。例えば北条家は桓武平氏の流れであるが、北条を本領としていたから北条氏を名乗り、さらに北条一族でありながら、その居住地名によって名越・金沢・江間氏などと称したのがそれである。日蓮大聖人から兵衛七郎の賜書が南条兵衛七郎殿御書であり、時光の賜書のあて名にも「南条殿」を使用されているものが5通ある。
とくに、
「
また日興上人の「弟子分本尊目録」に「南条兵衛七郎の子息七郎次郎平の時光」とあるように、時光は平氏の流れである。
北条氏が同じ平氏であることから、南条家は北条氏の同族か支族でなかったかと思われるが定かでなない。
ここで、当時の幕府の公式記録である「我妻鏡」に登場する南条姓のものを挙げてみよう(括弧内の数字は我妻鏡の収録巻)
南条次郎(15) 南条平次(18) 南条七郎二郎(27) 南条七郎三郎(27)
南条七郎左衛門尉時員(21・25・26・31・32)
南条兵衛尉(31)
南条太郎兵衛尉(31) 南条兵衛次郎経忠(31)
南条八郎兵衛尉忠時(33・46)
南条平四郎(33)
南条左衛門四郎(44)
南条兵衛六郎(46)
南条左衛門二郎(46)
南条左衛門尉頼員(47・48・49)
このなかで、七郎左衛門尉時員は承久三年(1221)五月、承久の乱の時に、北条泰時に従って上洛したことが記されている(承久三年5月22日の条)。また嘉禎二年(1236)12月19日の条にも将軍入御のため北条泰時が新第に移った時、御家人達が周囲の家屋を構えているが、七郎左衛門時員も家屋を構えた一人であることが記されている。
ところで「吾妻鏡」から挙げられた南条姓の人々をみると、名前から父の兵衛七郎とつながりがあると思われるのは兵衛尉、太郎兵衛尉、八郎兵衛尉忠時、兵衛六郎等である。
しかし、これらの人々が兵衛七郎とどのような関係があったかは不明であるが、南条一族としての何らかのつながりはあったと思ってさしつかえあるまい。
兵衛七郎は、鎌倉幕府の御家人であり、上野郷の地頭に補任されている。また御内人(北条氏得宗家被官)であったとの説もある。
文永二年(1265年)三月八日に兵衛七郎が病死した。その後、長男の七郎太郎が死去したこともあり、次男であった時光が家督を継いで惣領となり、後に任官して左衛門尉であったことは、延慶二年(1309年)二月の譲状で「左衛門尉時光」と自署していることから明らかである。
官については、律令制度の二官八省とは別に、軍事面を扱う衛門府、右衛士府、左衛士府、右兵衛府、左兵衛府の五衛府が設けられ、後にそれらの併合、変更があって左右衛門府、左右兵衛府、左右近衛府の六衛門府と称された。父の兵衛七郎が左衛門府のうち
しかし、武士の台頭による朝廷の実権の低下によって、鎌倉時代の中期には実際に職務にたずさわったわけではなく、官名のみが残ったようである。また任官といっても、本人が直接に朝廷から受けるのではなく、幕府が御家人の分をまとめて上奏し受領していた。
鎌倉幕府は治承四年(1180年)八月、源頼朝が伊豆国で挙兵後、文治元年(1185年)十一月朝廷から守護・地頭設置の勅許を得て、頼朝が軍事警察権を握る日本国総守護、総地頭となってから、その基盤が確立したといわれる。したがって、守護、地頭は幕府を支える重要な職であった。
とくに守護には御家人のなかでも有力な関東武士が選ばれ、その国の治安警察権の行使を主な職務としていた。
地頭の職権は領地内の管理権・警察権・徴税権がまとめられたようである。また地頭は任地に居住していることが多く、未開発の土地を開発していく開発領主の側面ももっていた。
また、時光が御家人であったことは、時光から次男の左衛門次郎時忠への譲状のなかに幕府からの御家人に対して使われる「御下文」「御

日興上人の弟子分帳の「南条兵衛七郎の子息七郎次郎平の時光」(歴全一巻92頁)の御記述から、兵衛七郎が平氏の流れであることがわかる。また七郎の名前から七男であったと思われる。「吾妻鏡」に記される南条兵衛六郎などとつながりがあると思われるが定かではない。
兵衛七郎に与えられた御書で現存するものは、文永元年(1266年)12月13日の南条兵衛七郎殿御書であり、そこに認められた内容から兵衛七郎について知る以外にない。
「御所労の由承り候はまことにてや候らん。世間の定なき事は病なき人も留まりがたき事に候へば、まして病あらん人は申すにおよばず」(御書321頁)
この御文から、恐らく当時、安房国におられたと思われる大聖人に、病気である旨の手紙を出したことがわかる。
兵衛七郎の入信は、恐らく鎌倉で大聖人にお会いして教化されたことによるのであろう。
大聖人は建長五年(1253年)四月、清澄寺で立教開示し、文応元年(1260年)七月十六日に、立正安国論による第一回の国主諌暁によって松葉ヶ谷の襲撃、伊豆伊東への流罪と法難にあわれ、弘長三年(1263年)二月、御赦免になって鎌倉に帰られた。翌文永元年(1264年)の秋に十二年ぶりに故郷の安房に帰られ、
「日蓮
と御母妙蓮の病を治されたのである。
したがって、兵衛七郎の入信は大聖人が鎌倉におられたであろう弘長三年(1263年)二月から文永元年(1264年)秋までの期間であろうと推定される。また、文応元年(1260)から弘長元年(1261年)の間であろうとの説もある。
当時の御家人には奉公の義務があった。内容は京都の内裏や院の御所の諸門を警固する京都大番役、京都市中の警衛にあたる篝屋番役、また鎌倉での将軍御所や幕府の諸門を警護する鎌倉大番役、そのほか平時の軍役、社寺の修造役、公事等である。このなかで鎌倉大番役は東国御家人特有の課役であり、遠江、駿河、伊豆、相模、武蔵、上総、下総、安房、常陸、下野、上野、信濃、甲斐、陸奥、出羽の十五ヶ国に住む御家人がこれにあたった。
鎌倉大番役でも、常時鎌倉にいるのは北条一門や御内人などであり、それ以外の御家人は常は補任された領地にいて、一、二年に一度、一ヶ月から二か月ぐらい鎌倉に出て勤務したようである。
したがって兵衛七郎は、弘長三年から文永元年の間ごろ、鎌倉大番役の時に大聖人にお会いしたのであろう。ただ、入信の経緯や動機などは不明である。
兵衛七郎はもと念仏の信徒であった。
「但
大聖人は兵衛七郎が法華経に帰依しても、入信が浅く念仏への執情を断ち切れないでいるのを、教・機・時・国・教法流布の先後の宗教の五義を説かれて、念仏は権教であり法華経こそ釈尊の本懐の教えであることを御教示され、
「いかに申すとも、法華経を
「但一度は念仏、一度は法華経
と不退転の信仰に立脚するように御指導をされている。
「もしさきにたゝせ給はゞ」(同書326頁)
の御文から、この御書をいただいた時は兵衛七郎の病状はすでにかなり悪化していたようである。翌文永二年(1265年)三月八日、兵衛七郎は死去した。法号を行増という。
兵衛七郎が念仏を完全に捨て去り、成仏の相を現じたことは、後年の南条家への書状に、
「法華経にて仏に
「故親父は武士なりしかどもあながちに法華経を尊み給ひしかば、臨終正念なりけるよしうけ給はりき」(上野殿御返事、744頁、文永11年11月11日)
とあり、また後家尼御前に、
「故聖霊は此の経の行者なれば即身成仏疑ひなし」(上野殿後家尼御返事、336頁、文永2年7月11日)
とお述べになっていることからも明瞭である。
兵衛七郎は屋敷に近い
「
時光の母(以下、母御前と称する)は、大聖人からは「上野殿御家尼御前」「上野殿母尼御前」「上野殿母御前」「上野尼御前」などと呼ばれているが、夫の兵衛七郎が死去した後に尼となったものであろう。賜書に、
「
とあるように、母御前は松野六郎左衛門入道の娘である。
松野六郎左衛門入道は、駿河国庵原郡松野に住んでおり、生年は不明だが、弘安元年(1278年)11月に死去している。松野一族に与えられた御書で現存するものは十三編にのぼっており、その内容から一族は純真な信仰を続け、たびたび大聖人に御供養をさしあげていることがうかがえる。
「子息多ければ孝養まちまちなり」(同)
とあるように、松野六郎左衛門入道は子供が多かったようである。六老僧の一人蓮華阿闍梨日時もその子とされる。第五十九世日亨上人は「この母御前(時光の母)は年配より見て持師の姉ではなく叔母であろう」(全伝7頁)とされているが、ここでは、他の資料の記述に従って六郎入道の次男、時光母御前の弟としておく。
母御前が兵衛七郎に嫁したのがいつかは不明だが、系図にあるように五男四女の多くの子供に恵まれている。
夫を亡くした時には懐妊しており、これが七郎五郎であった。弘安三年(1280年)九月五日に七郎五郎が死去した時、末子であっただけに、母御前の悲嘆は並々ならぬものであったようで、大聖人からたびたび励ましの御言葉を賜わっている。
「
「二人の
このほか大聖人が御入滅まで母御前に送られた御書のなかでは必ず七郎五郎の死去についてふれられて、母御前を慰められている。
弘安四年(1281年)十二月八日の上野殿母御前御返事には温かい人柄が伝わってくるような御書である。
「
身延に入山されて八年、すでに御身体も弱まり、食事も進まなくなられた大聖人を心配して白米や健胃剤となる「
こうした純真な信仰を続ける母御前は熱原法難の時にも、時光とともに外護の働きをしたことであろうことはまちがいないと思われる。
弘安七年(1284年)五月十日に死去し、夫の兵衛七郎と同じ高土の地に葬られた。法号を妙法という。
兵衛七郎の長男であり、時光の兄である。御書のなかにも七郎太郎について述べられている個所がなく、文永十一年(1274年)八月十日に水死したと伝えられているのみで、詳細は不明である。墓は下之坊の前の水田の中にある。
時光の弟である。長男の七郎太郎と同じく、御書のなかに記述がなく詳細は不明である。ただ弘安三年(1280年)十月二十四日の上野殿母御前御返事に、
「二人(時光と五郎)の
とあることから、弘安三年にはすでに二人とも死亡していたようである。
兵衛七郎の末子である。
上野殿母御前御返事(弘安三(1266年)年十月二十四日)に、
「故上野殿には盛んなりし時
とあるように、文永二年(1265年)三月、兵衛七郎が死去した時に、母が懐妊していた子である。
「此の子すでに平安なりしかば」(同1512頁)
と仰せのように、大きな事故もなく成長していった。
七郎五郎は兄の時光に似て信仰心の篤い人柄の良い青年となっていた。
弘安三年(1266年)九月六日の上野殿御返事には、
「
「此の六月十五日に見奉り候ひしに、あはれ肝ある者かな、男なり男なりと見候ひしに」(同1496頁)
弘安四年(1267年)一月十三日の上野尼御前御返事には、
「故五郎殿はとし十六歳、心
弘安四年(1267年)十二月八日の上野殿母御前御返事には、
「
これらの記述から、七郎五郎は豪胆で、かつ容貌もすぐれ親孝行の子であったようである。大聖人は、弘安三年(1280年)六月月十五日、時光とともに身延に参詣した七郎五郎の姿を、
「あはれ肝ある者かな、男なり男なり」(上野殿御返事、1496頁)
とめでられ、時光とともに日興上人のもとで広宣流布の戦いに活躍するであろうことを期待されていたにちがいない。
しかし人間の寿命は推し量りがたいものであり、大聖人に御目通りしてから三ヵ月後に、七郎五郎は急逝した。その原因は明らかではない。
大聖人は七郎五郎の死去の報を聞かれ直ちに筆をとられた。
「南条七郎五郎殿の御死去の御事、人は生まれて死する
七郎五郎の死を悼む御書は、この上野殿御返事をはじめ、十数件に及んでいる。
一人の人間に、そのうえ十六歳の若き信徒の死を、これほどまでに心に留められ惜しまれているのは、多くの信徒のなかでも、七郎五郎ただ一人である。
墓は富士妙蓮寺の後方にある。
時光の姉の蓮阿尼は新田五郎重綱に嫁した、新田家は本領が陸奥国(宮城県)
第五十九世日亨上人の「富士日興上人詳伝」(760頁)によれば、蓮阿尼は多くの男子に恵まれ、そのうち四男の四郎信綱は大聖人からの賜書・新田殿御書(1470頁)もあり、大聖人の御本尊を授与されるほとの強信者であった。日興上人の弟子分帳にも「新田四郎信綱は、日興第一の弟子なり、仍って申し与うる所、
また、五男の五郎(後の日目上人)は「御伝土代」(富要五巻13頁)に述べられているように、文永十一年(1274年)十五歳の時に日興上人に
日興上人は「日興跡条条事」(元弘二年(1332年)十一月十日)で次のように日目上人を讃えている。
「右、日目は十五の歳、日興に値ひて法華を信じて以来七十三歳の老体に至るも敢へて違失の義無し。十七の歳、日蓮聖人の所(甲州身延山)に詣りて御在生七年の間常随給仕し、御遷化の後、弘安八年より元徳二年に至る五十年の間、奏聞の功他に異なるに依って此くの如く書き置く所なり。」(御書1883頁)
次男の頼綱もまた時光の娘を妻とし、日目上人から唯授一人の血脈相承を授けられた第四世日道上人はその子である。日道聖人は十七歳で日目上人の弟子となり、重須談所で日興上人に給仕され、正慶元年(1332年)には新六の一人に数えられている。
法号妙一は、駿河国富士郡上方庄
「石河新兵衛入道道念は、日興第一の弟子なり。仍って申し与うる所、件の如し。但し嫡家孫三郎伝領す」(歴全一巻92頁)
「南条兵衛七郎の女子、石川新兵衛入道後家尼殿に日興之を申し与う」(歴全一巻93頁)
道念と妙一の子供が孫三郎源能忠であり、文永六年(1298年)、日興上人の移られた重須談所(後の北山本門寺)の開基檀那となっている。
駿河国富士郡阿原口(静岡県富士宮市阿原口)に住んでいた豪族と思われる人に嫁した。阿原口御前には、鬼鶴、乙鶴の二人の娘がいたが、阿原口御前が時光より先に死去したので元弘元年(1331年)十一月十八日に所領の一部を譲っている。
「
中之御前、法号妙華について行実は不明であるが、妙蓮寺過去帳では、元亨二年(1322年)三月二十三日死去したと記されている。
日亨上人は「この夫人は或いは松野家より来られたではあるまいかと思う」(全伝22頁)と推されているが、妻の乙鶴・法号妙連について確かな記録はない。
賜書に「南条殿女房御返事」(弘安元年五月二四日)があり、
「
とあることから、時光とともにたびたび御供養されていたことがうかがえる。
弘安三年(1280年)八月二十六日の上野殿御返事(1494頁)によると、既に女子一人、男子一人がおり、生まれた男子を大聖人から日若御前と命名していただいていることから、時光に嫁したのは建治年間と思われる。
系譜によると九男四女に恵まれ、そのうち二人の娘が大石寺第四世日道上人、第五世日行上人の母となっている。妙蓮寺過去帳によると、時光に先立つこと十年、元亨三年(1323年)八月十三日に死去している。時光は翌年元亨四年(1324年)三月、二十家阿闍梨日華師に寄せて上野郷堀之内の自邸を妙蓮寺として妻の菩提を弔っている。
弟子分帳に、「駿河国富士上方成出郷給主南条平七郎の母尼は、越後房の弟子なり、仍つて日興之を申し与う」(歴全一巻93頁)とあることから、平七郎は富士郡上方庄成出郷の給主であることがわかる。
給主とは給人のことで、幕府から所領の恩給を受けた者をいう。一般に給田の大きさは一町から三町程度であった。
大聖人から建治二年(1276年)十二月に「本尊供養御書」を、弘安元年(1278年)七月七日に種々物御消息を賜っている。
南条家縁故の人ではあるが、血縁関係は不明である。
弟子分帳に九郎太郎の人物を見つけることはできない。
賜書には、建治二年(1276年)九月月十五日、弘安元年(1278年)十一月一日)の九郎太郎御返事がある。
建治二年(1276年)の九郎太郎御返事には、「いゑの芋一駄」を御供養したことに対して、
「
と仰せになっていることから駿河国の人であること。また、弘安元年(1278年)の九郎太郎御返事には、
「これにつけても、
と述べられていることから、兵衛七郎の一族であったと思われる。
日亨上人は「九郎の文字から考えると七郎の弟の子ではなかったか、時光の従弟にあたる人ではなかったかと思う」(全伝23頁)と述べられている。
現存する古文書から見ると時光の所領は四ヵ国五ヵ所に分散していた。
一、駿河国上方庄上野郷
一、相模国山内庄舞岡郷
一、伊豆国南条南方武正名
一、丹波国小椋庄もりとし名
一、駿河国蒲原庄関島
駿河国冨士郡上野郷と相模国舞岡郷の一部は、延慶二年(1309年)二月二十三日、惣領の左衛門次郎時忠への譲状(富要八巻23頁)がある。
伊豆国南条武正名は、延慶二年(1309年)二月二十三日、時光から左衛門三郎への譲状(富要八巻24頁)がある。
丹波国小椋庄内の一部は、元亨元年(1321年)七月二十五日、時光から惣領の左衛門次郎時忠への譲状(富要八巻26頁)がある。
駿河国蒲原庄関島は、阿原口御前が時光より先に死去したので、元弘元年(1331年)十一月十八日、娘の鬼鶴御前の譲状(富要八巻26頁)がある。
他の郷でもそうであろうが、上野郷が現在のどの地域になるか、それを明確にする史料は今のところみあたらないが、上野郷は「静岡県富士宮市上条・下条・精進川一帯、すなわち現在の日蓮正宗総本山富士大石寺ならびに同本山妙蓮寺などのたっている地域」(日蓮大聖人檀那列伝10頁)と推定されている。
この地域は東西南北に、約三キロにわたる。また、この地域は、稲作の限界にあたるといわれ、南の低地には水田地域もあるが、北は田畑になり、決して豊饒とはいえない。
この小郷の地頭である時光が、大聖人に御供養を続け、大石が原を寄進したことは、ひとえに時光の純真な信仰にあったことを忘れてはいけない。
父の南条兵衛七郎が死去した文永二年(1265年)、時光は七歳の少年であった。
兵衛七郎の死後、大聖人の佐渡流罪が御赦免となり身延に入山される文永十一年(1274年)までの間の時光一族への賜書がないので、この間の時光一族の行実は不明である。しかし、文永十一年五月十七日に大聖人が波木井に到着され、六月十七日に庵室が完成された後、日興上人が甲斐、駿河方面に弘教に出られるようになって大聖人の身延後入山が伝わってきたのであろう。母御前が七月に御供養を捧げていることから、兵衛七郎の死後も一家は純真に信仰を続けていたと思われる。
この年、時光は十六歳になっており、この時には
この時代の武士の成年式は
母御前に書状が送られてからしばらくして、時光は鎌倉で御目通りした大聖人をお慕いして、御供養をたずさえて身延に登った。
大聖人はさっそく、文永十一年七月二十六日に、書を認められ、
「
と、幼かった時光が鎌倉で会ったことをよく忘れないでいたと喜ばれ、
「
と、若き時光が父の兵衛七郎の姿も心もよく似ていると慈愛のこもった御文を
さらに、文永十一年十一月十一日には、
「故親父は武士なりしかどもあながちに法華経を尊み給ひしかば、臨終正念なりけるよしうけ給はりき。其の親の跡を
と、兵衛七郎が生きていれば、いま時光が跡を継いで純真に法華経を信じていることをどれはどか喜ばれるであろうと時光を励まされている。
文永十二年(1275年)一月下句、大聖人は、
「さては故
と、兵衛七郎が死去した時に鎌倉から上野郷まで墓参に下向されたことを回想されている。さらに身延後入山の時には富士郡の信徒に会うことができなかったので、
「此の御房は正月の内に
とお弟子・日興上人を代理として墓参させる旨を述べられている。
時光が日興上人に値ったのはその時が初めてではなかったであろうが、これまでは時光が年少であったのでこの墓参がその後の生涯にわたる師弟の
日興上人は寛元四年(1246年)三月八日、甲斐国巨摩郡大井庄
大聖人が身延入山後、二十九歳の日興上人は縁故をたどって甲斐、駿河へと弘教の戦いを展開された。
日興上人の弘教がいかに広範に展開されたかは、それが発端となって、熱原法難が起こったことや、弟子分帳に記されている六十五人のうち「日興の弟子」とされているのは、甲斐国十二人・駿河国十七人・伊豆国三人・相模国一人の三十三人にのぼっていることなどから、その一端がうかがうことができよう。
日興上人と時光とが師弟として結ばれたこの墓参は、そのまま大石寺開創の淵源となるものであった。のちに日興上人は大聖人から付嘱を受けられて本門弘通の大導師となられ、身延山久遠寺の別当につかれる。だが、地頭の謗法により身延を捨てて大石寺を建立され、時光は開基檀那となるのである。この道契から十六年後の正応三年(1290年)のことである。
熱原法難は、日蓮大聖人が出世の本懐である本門戒壇の大御本尊を御建立になる機縁となった重大な意義をもった法難であった。
法難は、文永十一年(1274年)六月、大聖人が身延に庵室を構えられてから、日興上人が甲斐・駿河へと弘教されていったことが発端となった。
もともと日興上人は甲斐国
日興上人は、有縁の四十九院や岩本実相寺の住僧を教化し、さらに付近の在家の人々にも布教されていった。そのため、寺内の僧や信徒が続々と日興上人の弟子になっていく状況に対して、弘安元年(1278年)四十九院の
「四十九院の内・日蓮が弟子等居住せしむるの由・其の聞え有り、彼の
と法華経を邪義であるとし、追放の理由に大衆等の評定を名目としたのである。
建治元年(1275年)には熱原郷の滝泉寺に折伏弘教は広がり、寺僧の下野房、越後房、少輔房、三河房等が日興上人の弟子となった。それに驚いて、滝泉側は六月頃から迫害を始めた。
当時の滝泉寺院主代は北条一門の平左近入道行智であった。この行智の悪行は滝泉寺申状(弘安二年十月中旬)に詳しい。
「凡そ行智の所行は、法華三昧の
そうした僧侶にあるまじき行状と滝泉寺の興廃を嘆いた人々に、日興上人の訴えた正法正義は、乾いた大地に水が吸い込まれるように浸透していったといえよう。
その時に大聖人は、弘安二年八月、熱原の人々に異体同心で法難にあたるよう、
「はわき房・
と御教示され、
「日蓮が一類は異体同心なれば、人々すくなく候へども大事を
と、一門の結束があれば必ず正法が弘まっていくと御指導されている。
滝泉寺の迫害の始まったこの年の十月、時光は大聖人から御本尊を授与された。この御本尊は、現在、新曾妙顕寺にあり、添え書き(別紙)に大聖人の御筆で「平の時光之を授与す」(富要八巻222頁)と記されている。
建治二年(1276年)、院主代行智は下野房日秀師らに法華経を捨てて念仏を称えるとの誓状を書くよう迫った。この時、三河房頼円は退転し、日秀・日弁・日禅の三師は寺を追放された。日秀・日弁は寺内に隠れ、日禅師は実家のある河合に帰った。
しかし日興上人を中心とする折伏弘教はやまず、弘安元年(1278年)には熱原郷の神四郎、弥五郎、弥六郎等の農民が日秀・日弁等の教化によって正法に帰依している。
三月には、日興上人、日持・賢秀・承賢の諸師が四十九院による追放処分の不当性を幕府に訴えるなど、富士郡の岩本実相寺、四十九院、滝泉寺の各寺には正法信仰の輪がますます広がっていったのである。
弘安二年(1279年)に入ると、法難はさらに激しさを増した。四月八日、浅間神社(この時は本社の大宮浅間神社が造営中のために三日市場にあった分社)の流鏑馬行事の時、見物人の雑踏の中で信徒の四郎が刀傷された。
さらに八月、弥四郎が何者かによって頸を切られるという事件が起こったが、この二つの事件はともに犯人不明のままだった。
そしてついに九月二十一日、滝泉寺の弥藤次一味、政所の役人、行智一派の武士などが武装して、日秀師の田で稲刈り中の農民信徒を急襲し、神四郎等二十人を逮捕、下方政所に連行したのである。神四郎の兄の弥藤次はかねて準備してあった訴状を幕府に提出した。
「日秀・日弁、日蓮房の弟子と号し、法華経より外の余経、或は真言の行人は皆以て今世後世叶ふべからざるの由、之を申す云云取意」(滝泉寺申状、1400頁)
「今月二十一日数多の人勢を催し、弓箭を帯し、院主分の御坊内に打ち入り、下野房は乗馬相具し、熱原の百姓紀次郎男、点札を立て作毛を苅り取って日秀の住房に取り入れ畢んぬ云云取意」(同書、1402頁)
苅り田狼藉という無実の罪をきせた卑劣な訴状によって、神四郎等の二十人は鎌倉に連行され、取り調べを受けたのである。
大聖人はこの時「伯耆殿並諸人御中」(弘安二年九月二六日)とあて名された書状を認められた。
「此の事はすでに梵天・帝釈・日月等に申し入れて候ぞ。あへて
九月廿六日 日蓮花押
伯耆殿並びに諸人御中」(御書1395頁)
神四郎達が鎌倉に連行されたのは九月下旬であろうと思われる。
この時、取り調べには平左衛門尉頼綱(~1293年)があたった。
頼綱は、執権・北条時宗、貞時の二代に仕えた北条氏得宗家の内管領(家司)であり、また、侍所の所司(次官)でもあった。
当時。執権職の安定・強化にともなって、その勢力を支えた得宗家被官達は、御内、御内人と呼ばれて、北条氏得宗家の権威を背景として次第に幕府の政治機構に入り込み、隠然たる権力を持つようになった。この御内人の最上位に内管領は立っている。内管領は所司として侍所(執権が別当(長官)であった)を統栽し、全国の御家人の統轄権と検断権を掌握し、その権勢は大変なものであった。
頼綱は、この内管領の立場を利用して大聖人および門下を迫害してきたのである。
頼綱と大聖人とのかかわりがいつから始まったかは不明であるが、文永八年(1271年)九月十日、幕府内で大聖人に見参したことが有名である。この時に、かえって厳然たる諌暁にあって不快の念をいだいた頼綱は、同十二日、桑ヶ谷の草庵を襲った。
「
同日深夜、竜の口で斬首しようとして果たせなかった頼綱は、執権時宗をたきつけて大聖人を佐渡に流罪した。また、その後、時宗の断により赦免になって佐渡から帰られた大聖人に、頼綱は再び対面して諌暁をうけている。頼綱は一貫して、大聖人に対して憎悪をもっていたことは明らかであり、とくに熱原滝泉寺のある駿河国下方庄は、北条氏得宗家の領地で「九月二十一日の事件」が得宗家の領地内で起こったことから、頼綱が直接に取り調べにあたったものと思われる。
頼綱による取り調べの模様について、五十九世日亨上人は「熱原法難史」で次のように述べられている。
「問註の頭は
こうして二十人は拷問に屈しなかったので、張本とされた神四郎、弥五郎、弥六郎の三人は十月十五日、頸を斬られ、残る十七人は追放処分となった。
大聖人はこの法難のさなかの十月一日「聖人御難事」を著された。
この御書の中で、釈尊、天台大師、伝教大師が出世の本懐を遂げるまでの年数を挙げられたうえで、
「余は二十七年なり」(聖人御難事,1396頁)
と立教開宗以来、二十七年目の今こそ出世の本懐を遂げる時がきたことを宣言されたのである。入信してわずか一、二年の熱原の農民信徒が、その権勢は飛ぶ鳥を落とす勢いだった頼綱に対して、一歩も退くことなく題目を唱え続けて不惜身命の信心を貫いたのである。大聖人はこのことから、末法万年までこの大仏法が流布していく基盤となる不退の信仰が民衆の間に確立されたことを御覧になり、本門戒壇の大御本尊の建立の時が来たと感じられたと拝される。
十月十五日殉職の模様は、直ちに身延の大聖人のもとに急報された。
「今月十五日酉時御文、同じき十七日酉時到来す。彼等御勘気を蒙るの時、南無妙法蓮華経と唱へ奉ると云云。
弘安二年十月十七日戌時 日蓮 花押」
聖人等御返事」(聖人等御返事、1405頁)
頼綱は十四年後の正応六年(1293年)四月二十三日、
このことを日興上人は弟子分帳に次のように記されている。
「此の三人(神四朗、弥五郎、弥六郎)は越後房下野房の弟子二十人のうちなり。弘安元年信じ始め奉る処、舎兄弥藤次入道の訴えによって鎌倉に召し上げられ、終に頸を切られ畢んぬ、平の左衛門入道の沙汰なり、子息飯沼判官十三歳ひきめを以って散散に射て念仏申すべきの旨、再三之を責むと雖も、二十人更に以って之を申さざる間、張本三人召し禁じて斬首せしむる所なり、枝葉は十七人は禁獄せしむと雖も、終に放たれ畢んぬ。その後十四年を軽て平之入道判官父子、謀叛を発して誅せられ畢んぬ。父子これただ事にあらず、法華の現罰を蒙れり」(歴全一巻94頁)
富士郡下方庄熱原郷の神四郎、弥五郎、弥六郎の三人が処刑され、十七人が追放処分となった熱原法難から二十日あまり、大聖人は時光が熱原法難で示した外護の功を賞められて御書を与えられた。これが有名な上野殿御返事(竜門御書、弘安二年十一月六日)である。
この法門の追伸には、
「此はあつわらの事のありがたさに申す御返事なり」(御書1428頁)
と述べられている。熱原法難に、献身的な外護を尽くした時光の慰労の御言葉と拝せされる。
時光の賜書のうち、熱原の人々への迫害に関する言及は、建治三年(1277年)五月までには見ることができない。
すでに建治元年(1275年)に日興上人によって日秀・日弁・日禅師が改宗し、翌年には滝泉寺院主代行智が日秀師等に法華経の信仰をやめて念仏を称えるとの誓状を書くよう迫るなど、熱原地方の弟子・檀那への迫害が始まっていた。
時光に対しても建治三年(1277年)五月十五日の上野殿御返事で、
「さるにては、殿は法華経の行者に
と、方人(味方)を装い、甘言で退転を勘める者がいるので用心するよう注意を促しておられる。
「殿もせめをとされさせ給ふならば、
駿河国は日興上人の弘教の中心地である。時光の一族はもちろん、外祖父由比入道、日興上人の叔母の嫁した高橋入道、時光の姉の嫁した石川新兵衛入道などが日興上人の門下となっている。
日興上人の弟子分帳六十三人中三十七人が駿河国の人であり、なかでも在家弟子十七人は、全員富士郡在住である。
時光の屋敷は富士地方の弘教の拠点の一つになっていたであろうから、時光に対して当然さまざまな迫害や中傷が加えられたことであろう。
もし少輔房、能登房、名越の尼のように、時光がそそのかされて退転してしまえば、駿河国の信徒もすべて退転してしまうであろうと、時光の存在がいかに大きいかを述べて励まされているのである。
そして、
「千丁万丁しる人も、
と、たとえ大難があろうとも法華経のために身命を捨てるのに、何が惜しいことがあろうかと仰せられている。
これらの御文からも、時光への迫害が身近に迫っていたことが推察される。
こうしたなかで弘安元年(1276年)六月、大聖人が、
「其の国の仏法は
と、駿河の中心者として弘教に励むように仰せられているのは、時光にあてたものと推定される。いまだ二十歳の若き時光は、難の中でこの御言葉にどれほどか勇気を奮いおこしたであろうか。
神四郎等の処刑の後も、法難の
富士郡下方庄の新福地の
「富士郡下方熱原新福地の神主は、下野房の弟子なり。仍って日興之を申し与う」(歴全一巻95頁)
と記されているとおり、大聖人の御本尊を授与されるほ どの強信者であった。新福地の神主は熱原の信徒の中でリーダー格の存在であったのであろう。危険が忍びよっていたので上方庄の時光の屋敷に妻子とともにかくまわれていた。
「去ぬる六月十五日の
この賜書は法難から十ヵ月後の弘安三年(1280年)七月二日のものである。この中で大聖人は時光に対して神主をかくまってくれた礼を述べられ、もしかのときは神主を身延に送られたい、しかし妻子に危難が及ぶことはないだろうから 、事態が落ち着くまであずかってもらいたいと仰せられている。時光が神主をかくまったのはいつのごろからか正確にはわからないが、弥藤次一味、下方政所の役人等が弘安二年(1279年)九月 二十一日に神四郎らの稲刈りの襲撃した後であろう。行智一味も、御家人であり地頭である時光を捕縛したり、直接迫害することはできなかったのである。
しかしさまざまな圧迫が加えられたと思われる。
「しばらくの苦こそ候とも、
大聖人は時光に、この苦しみも必ず去り、常楽我浄となっていくだろうと温かく励まされている。
そして、この法難の余波のなかで、時光は弟の七郎五郎の突然の死にあうのである。六月十五日に二人して身延山に参詣し、大聖人にお会いしたばかりだったのである。
「あはれ
と大聖人が成長を楽しみにされていた七郎五郎の急死である。時光の心中はいかばかりであったろうか。
しかし、時光の悲しみに追い打ちをかけるように迫害はつづく。弘安三年(1280年)十二月二七日の上野殿御返事に、
「其の上わづかの小郷に
と、幕府は地頭の時光に対して多くの課税・夫役の負担を強いたのである。
時光はこうした経済的苦境のなかでも、
「かゝる身なれども、法華経の行者の山中の雪にせめられ、食
とあるように、雪の中に閉じ込められている大聖人の御生活を思い、銭一貫文を御供養しているのである。これこそ御供養の精神の鏡といえよう。
「御使ひの申し候を
弘安四年(1281)九月、このとき、時光は二十二歳。病名は不明である。
父の兵衛七郎が壮年の時に病死し、弟の七郎五郎を前年9月に亡くしている南条一家にとって、惣領である時光の病は重大事であった。
大聖人は、
「
「参詣
と、人里を離れた山中とはいえ、月氏の霊鷲山にも比すべき身延山に、早く病気を治して参詣するように仰せられている。わが子のような時光の身を案じて、
「是にて待ち入つて候べし」(同1570頁)
と時光の元気な顔を見たい、身延で待っているとの温かな御言葉は、時光を奮起させずにおかなかったであろう。
このあと、時光の病状について述べられている御書がないので一応治ったものと思われるが、翌年二月に時光は再び病に臥してしまうのである。
しかもこの頃は、大聖人の御身体もすぐれなかった。
中務左衛門尉殿御返事(弘安元年(1278年)六月二六日弘安元年)
「日蓮が
八万宮造営事(弘安四年(1282年)五月二六日)
「此の法門申し候事すでに
富城入道殿御返事(弘安四年(1281)十月二二日)
「今月十四日の
上野殿母御前御返事(弘安四年十二月八日)
「このところのやう
これらの書状から建治3年(1277)十二月に起こった
弘安5年(1281)2月、時光の病が悪化、大聖人は御身体の不調から日朗に代筆させて「伯耆公御房消息」激励の書を日興上人のもとに送られた。
伯耆公御房消息(弘安五年二月二五日)
「御布施御馬一疋鹿毛御見参に入らしめ候ひ了んぬ。兼ねて又此の経文は廿八字、法華経の七の巻薬王品の文にて候。然るに聖人の御乳母の、ひとゝせ御所労御大事にならせ給ひ候て、やがて死なせ給ひて候ひし時、此の経文をあそばし候て、浄水をもってまいらせさせ給ひて候ひしかば、時をかへずいきかへらせ給ひて候経文なり。なんでうの七郎次郎時光は身はちいさきものなれども、日蓮に御こゝろざしふかきものなり」(御書1589頁)
しかし、それでも時光のことが御心配であったのであろう。大聖人は三日後の二月二十八日、病をおして自ら「法華証明抄」を認められ、日興上人を通じて時光に送られた。
この御書は他の賜書とは異なり、冒頭から「法華経の行者 日蓮」と認められて、花押をされてから本文に入られている。
「しかるにこの上野の七郎次郎は末代の凡夫、武士の家に生まれて悪人とは申すべけれども心は善人なり。其の故は、日蓮が法門をば
時光は父母に続て、幼少から大聖人に帰依し、周囲の反対の中を信心を全うし、若い身でありながら身延山中の大聖人の御不自由を思われて度重なる御供養を奉っているのである。何としても時光を病魔から救ってあげたいと、「鬼神めらめ此の人をなやますは剣をさかさまにのむか、又大火をいだくか、三世十方の仏の大怨敵となるか」と鬼神を呵責されて当病平癒を祈られる大聖人の御心が、拝読する者の心を打つ御文である。
莚三枚御書(弘安五年三月)には、
「
大聖人の御祈念によって、時光の病は平癒したようである。時光は、さっそく、莚、生和布を御供養し、大聖人もまたお元気になられた様子を拝することができる。
建治三年(1277年)の十二月に起こった大聖人の
「八年が間やせ
が続いて、ほとんど食事が進まれなかった。
弘安五年(1282年)三月、時光に与えられた莚三枚御書以後、相伝書・付嘱書を除くと大聖人が著された御書は「三大秘法禀承事」「波木井殿御報」のみである。このことからも大聖人の病状がいかに悪化していたかが察せられる。
九月八日、大聖人は御弟子の強い勧めがあって、常陸(ひたち)に湯治に向かわれた、身延を出発される前に、日興上人に血脈を付嘱あそばされ「本門弘通の大導師」に任ぜられ、「血脈の次第 日蓮日興」と日蓮一期弘法付嘱書を与えられている。門下や波木井一族の若者等に護られて 九月十五日に武蔵国池上に到着された。そして十月八日には六老僧を定められ、十月十三日、日興上人を身延山久遠寺の別当と定めた身延山付嘱書を与えられ、後事をすべて託された後、安祥として辰の時に御入滅になられた。この時、大地が震動し邸内の桜が一時に咲いたという。
日興上人が十月十六日記された「宗祖御遷化記録」によると、十四日の戌の時に御入棺、子の時に御火葬申し上げている。この時時光は御葬送に列なった。
一.御葬送次第
先火 二郎三郎(鎌倉の住人)
次大宝花 四朗次郎(駿河国富士上野の住人)
次幡 左・四条左衛門尉、右・衛門大夫
次香 富木五郎入道
次鐘 太田左衛門入道
次散花 南条七郎次郎
次御経 大学亮
次文机 富木四朗太郎
次仏 大学三郎
次御はきもの 源内三郎(御所領中間)
時光は松明を先頭に茶毘所に向かう葬列の中で、四条金吾、富木常忍、池上宗仲等の重鎮の信徒にまじって散花の役を務めている。散花とは供養のために、樒の華、蓮の花びら、蓮弁をかたどった色紙を歩きながら撒くことである。
時光が池上の御葬儀に参列できたのは、恐らく大聖人御入滅の報が届く前に、すでに上野郷を出発していたからであろう。御遷化記録から推すると六老僧のうち佐土公日向と伊与公日頂の 二人は名がなく、他国に行っていて御葬儀に列することができなかったように思われる。
当時、鎌倉から身延まで、急使で二日間はかかっており、時光は大聖人の身延御出山、池上での御様子などを聞いて、一族の四郎次郎などを伴って急いだのであろう。
「さりながらも日本国にそこばくもてあつかうて候みを、九年まで御きえ候ひぬる御心ざし申すばかりなく候へば、いづくにて死に候とも、はかをばみのぶさわにせさせ候べく候」(波木井殿御報、1595頁)
この御遺言から大聖人の御墓を晩年を過ごされた身延に建てるため、初七日の法要を終えてから、御遺骨は弟子・檀那に守護されて池上を出発した。
「元祖化導記」(行学院日朝著)には「或る記に云く、御遺骨をば御遺言に任せて、十月二十一日池上より飯田まで、二十二日湯本、二十三日車返、二十四日南条七郎宿所、二十五日甲斐国に入り玉へり」(日全書十四巻48頁)
とある。この書は、文明十年(1478年)に書かれたもので、「或る記」が何かは不明であるが、ご遺骨の身延への旅程について諸伝はおおよそこの説を用いている。
ここに記されているとおりならば、御灰骨は上野郷の時光の屋敷に一宿されたのである。東海道から身延に入るコースとしてはやや寄り道ともいえるこの一宿は、大聖人御在世の法縁と日興上人の御配慮ではなかったろうと思われる。
日蓮大聖人の御灰骨を奉持して、日興上人が身延に入山されたのは弘安五年(1282年)十月の末であった。
「身延山久遠寺の
との身延山付嘱書のとおり、日興上人は身延山久遠寺の院主別当として、また一宗の総貫首として身延山に常住されることになった。
身延の地頭は
大聖人が波木井一族に与えられた御書のなかに「南部六郎殿御書」がある。南部姓については、実長の父・南部三郎光行が源頼朝の時代に奥州南部を開いたことから南部殿と呼ばれるようになったとの説がある。
この時代の甲斐国は
実長は御家人であり、そのため鎌倉勤務も多かったようである。波木井と鎌倉を往復する間に、沿道の富士川西の四十九院で、日興上人の教化を受けて念仏を捨て法華経を帰依したといわれる。入信は文永六年(1269年)頃と伝えられる。後に大聖人から日円の法名を授けられている。
日興上人の弟子分帳には、波木井一族の名が、南部遇俟志入道、越前房、南部六郎入道、波木井藤兵衛入道、南部六郎次郎、南部六郎三郎、南部イホメノ宿ノ尼、南部弥六郎、南部矢次郎入道、南部弥三郎兵衛入道、波木井播磨公と十一名記されている。
大聖人は佐渡流罪赦免後、文永十一年(1274年)四月八日、平左衛門尉と対面され、三度目の国主諌暁を行われた、しかし、幕府はこの諌暁を容れず、
「本より存知せり、国恩を報ぜんがために三度までは諌暁すべし、用ひずば山林に身を隠さんとおもひしなり。又いにしへの本文にも、三度のいさめ用ひずば去れといふ。本文に任せて
と、大聖人は鎌倉を去られる決意をされたのである。
「延山地頭発心の根元は日興教化の力用なり、
と述べられているように、身延の地頭・実長が日興上人の弟子であり、有縁の地であることから、大聖人は身延に入山されたのである。
この地頭波木井実長の法門への信解はどのようなものであったのか。
建治三年(1277年)の四条金吾殿御返事に、
「
とある。
大聖人が身延へ入られてから三年目の御書であり、「法門の御信用あるやうに候へども…申すままには御用いなかりしかば」とあるように、実長は一応は信心があるようにみえながら、大聖人の御指南に心から従わないという傲慢な心が根強くあったようである。この信解の浅さと傲慢さが、後年、日興上人の至誠の厳誡に背いて四箇の謗法を犯す根本となったものであろう。
六老僧の一人である日向(1253年~1314年)は、佐渡公、佐渡房、または佐渡阿闍梨、民部阿闍梨と呼ばれた。安房国
しかし、日興上人が記された「宗祖御遷化記録」「墓所可番帳事」によると、日向は大聖人の御葬儀の際、また弘安六年(1283年)一月の百ヵ日忌にその名が見えず、他国に行って不参だったようである。
定 次第不同
墓所守る可き番帳の事
正 月 弁阿闍梨
二 月 大国阿闍梨
三 月 越前公 淡路公
四 月 伊与公
五 月 蓮花闍梨
六 月 越後公 下野公
七 月 伊賀公 筑前公
八 月 和泉公 治部公
九 月 白蓮阿闍梨
十 月 但馬公 卿公
十一月 佐土公
十二月 丹波公 寂日房
右番帳の次第を守り懈怠無く勤仕せしむ可きの状件の如し
弘安六年正月 日
このように日向は十一月にあたっていた、しかし五老僧のいずれもこれを守ろうとはしなかった。日興上人の門下を除いた他の弟子たちはほとんどこれを実行しなかったのである。
日興上人が身延に入られた弘安五年(1282年)十二月に、鎌倉に在った実長は日興上人に書状を送っている。
「まことに御きやうを
これは、身延で御経を聴聞できるのは、日興上人が身延においでになるからこそである、との喜びの言葉である。
弘安七年(1284年)十月、大聖人の第三回忌には、諸老僧は地頭が謗法を犯しているとか病気とかの理由で身延に登山しなかった。
日興上人はこのことを美作房に送られた書状のなかで
「地頭の不法ならん時は我も住むまじき由、御遺言には承り候へども、不法の色も見えず候」(聖典555頁)
と、地頭が不法を犯しているわけでもないのに、登山しないのはどういうわかかと諸老僧を難じられている。
また、
「師を捨つべからずと申す法門を立てながら、忽ちに本師を捨て奉り候はん事、大方世間の俗難に術なく覚え候」(聖典555頁)
と。
この御文からも、この頃に老僧達が身延に参詣していないことが明瞭である。
また、実長は、弘安八年(1285年)二月、日興上人に書状を送り、久遠寺に法華経読誦、法門談義の盛んになったことを喜び、それは日興上人が身延にいてくださるからであり、大聖人が再び身延に住まわれているようにありがたく思う、と述べている。
五老僧等は、大聖人が身延山久遠寺を日興上人に譲られたための嫉妬と、厳格な日興上人を嫌う気持ちから、登山しなかったのであろう。
弘安八年(1285年)、民部阿闍梨日向が下総から登山してきた。他の老僧が参詣しないなかでの登山であったため、日興上人はこれを喜ばれ、日向を学頭に補されたのである。
二月十九日、実長から日興上人への書状に
「
とあるとおり、この年の 二月に日向が身延に参詣する意思を日興上人に手紙で知らせたことが記されている。したがって、日向の身延登山は、弘安八年の春以降ということになる。
正応元年(1288年)十二月の原殿御返事には、
「彼の民部阿闍梨、世間の欲心深くしてへつらひ諂曲したる僧、聖人の御法門を立つるまでは思いも寄らず大いに破らんずる仁よと、此の二三年見つめ候いて」(聖典558頁)
とあり、日興上人は日向の不法が弘安9年(1286年)頃から現れていたことを指摘されている。
第五十九世
一、非安国論主義の神社参拝。
二、国禱問題
三、師敵対。
四、日興上人を外典読みと批判。
五、絵曼荼羅を書いた。
六、日向の
この「
古来、実長の謗法を四箇とするが、これは富士一門跡門徒存知の事による。
「一、甲斐国波木井郷身延山の麓に聖人の御廟あり、而るに日興彼の御廟に通ぜざる子細条々の事。
彼の御廟の地頭南部六郎入道法名日円は日興最初発心の弟子なり。此の因縁に依って、聖人御在所九箇年の間帰依し奉る。滅後其の年月義絶する条々の事。
釈迦如来を造立供養して本尊と為し奉るべし是一。
次に聖人御在生九箇年の間停止せらるゝ神社参詣其の年に之を始む、二所三島に参詣を致せり是二。
次に一門の勧進と号して南部の郷内のふくしの塔を供養奉加之有り是三。
次に一門仏事の助成と号して九品念仏の道場一宇之を造立し荘厳せり、甲斐国其の処なり是四。
已上四箇条の謗法を教訓する義に云はく、日向之を許す云云。此の義に依って去ぬる其の年月、彼の波木井入道並びに子孫と永く以て師弟の義を絶し畢んぬ、仍っ て 御廟に相通ぜざるなり。」(富士一跡門徒存知事,1868頁)
これを原殿御返事にある「三の子細」とあわせて図示すると次のようになる。
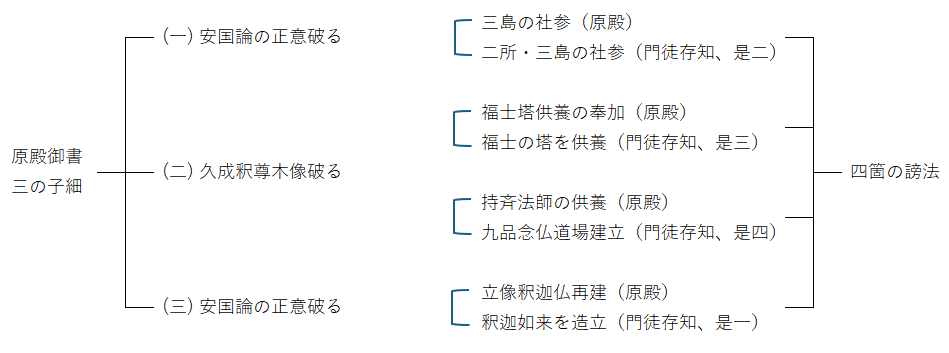
日興上人は実長に対して、あくまでも実長の過ではなく「諂曲したる僧」、すなわち日向に惑わされているのであるとして、改心を促された。しかし、すでに日向の軟風に染まった実長は、日興上人の諌暁をききいれようとせず、かえって「我は民部阿闍梨を師匠にしたる也」と不遜の返事を呈するに至ったのである。
学頭の日向と地頭の実長の四箇の謗法とによって、大聖人が九年間お住まいになった身延の地も、ついに謗法の汚泥にまみれてしまった。
日興上人の胸中には
「地頭の不法ならん時は我も住むまじき」(聖典555頁)
との大聖人の御遺言がつねに秘められていたことを拝される。
身延を去るということは、大聖人から
「身延山久遠寺の
に任ぜられた身でありながら、その地をむざむざ捨て去ることであり、日興上人には断腸の思いであったと拝される。
身延を離山される心情を、原殿御返事のなかで次のように述べられている。
「日興が波木井の上下の御為には初発心の御師にて候事は、二代三代の末は知らず、未だ上にも下にも誰か御忘れ候べきことこそ存じ候え。
日興上人の離山の決意を聞き知った波木井一族の清信の士清長は、日興上人に書状を奉った。
「
また、一族の筑前公からこのことを聞いた実長は、鎌倉から越前公あてに
「今は万事
と日興上人の引きとめを依頼する書状を送っている。
しかし、日興上人の御決心は固く、正応2年(1289)春、本門戒壇の大御本尊、生御影、御灰骨等の一切の重宝を奉持して身延を離山されたのである。
最初は外祖父由比入道の富士郡上方庄河合の養家にしばらく御滞在になり、三月には時光の請いを受けて上野郷に赴かれたのである。
日興上人が、時光の墾請を受け入れて上野郷の南条邸に入られたのは正応二年(1289年)の春であった。
そして、時光から大石ヶ原の寄進を受け、末法万年の大法興隆の礎として大石寺建立の工事が十月から開始された。
この大石ヶ原は、背面に富士山をひかえ、前方に駿河湾を望み、わきに清流が流れ、かつ原生林が残っている。まさに四神相応の地であり、大聖人の御遺命たる本門の戒壇を建立するにふさわしい最勝の地であった。
大聖人の御遺命は、
「霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等の来下して踏み給ふべき戒壇なり」(三大秘法稟承事、1595頁)
「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(日蓮一期弘法付嘱書、1675頁)
「三箇の秘法建立の勝地は富士山本門寺の本堂なり」(百六箇抄、1699頁)
等の御文に明らかである。
おそらく日興上人は時光に対して、御遺命たる本門戒壇建立の勝地の選定について御指南されたであろう。
日目上人、日華師、日禅師、日秀師、日仙師等の門下、また時光や新田信綱等の檀越等が協力して大坊の造営にかかり、正応三年(1290年)十月十二日、十二間四面の完成をみるに至った。大坊は六壺ともいわれ、仏間、住職の居間、寺務所、集会所、台所等六つに区画されていたと伝えられている。
日目上人は蓮蔵坊、日華師は寂日坊、日秀師は理境坊、日仙師は上蓮常(百貫坊)、日尊師は久住坊をそれぞれ建てて大坊を護り、ここに大石寺の基盤がなったのであった。この時、日興上人は四十五歳であられ、時光は三十五歳であった。その後、日興上人は講学に力をそそがれて若き弟子達の育成をはかり、また門下を指揮して大法弘通に励まれたのであった。
この大石寺創建にあたって、日興上人と門下のお弟子方を外護申し上げ、また領内の景勝の地・大石ヶ原を寄進し、大坊建立の費用の多くを御供養した時光の一族から、日興上人より付属を受けた第三祖日目上人(時光の甥)、第四世日道上人(時光の孫)、第五世日行上人(時光の孫)等の歴代御法主上人がでていることにも一族の純粋な信心が現れており、あげて大石寺の外護に全力をそそいでいったことがうかがえるのである。
大石寺が建立された正応三年(1290年)以後、蓮東坊(日蔵師)、乗観坊(日弁師)、観行坊(日円師)、治部坊(日延師)、浄蓮坊(日道上人)、等が続々と建立され、時光の生存中に大石寺塔中の坊は11を数えるにいたった。
大石寺建立の後の行跡については、子孫への所領の譲状のほかに文書がほとんど残っていないのでよくわからない。ただ、日興上人が、大石寺の基礎が固まった永仁六年(1298年)に、大石寺から東へ二㌔の重須郷の地頭・石河孫三郎の請によって御影堂(現在の北山本門寺)を建立して移られたが、その造営に時光が尽力していことは明らかである。
「大施主 地頭石河孫三郎源能忠 合力 小泉法華衆等
大施主 南条七郎次郎平時光 同 上野講衆中」
(本門寺棟札・歴全1巻88頁)
日興上人が重須に移られてからは、嫡弟の日目上人が大石寺を統括された。すでに日目上人は正応三年(1290年)十月に、日興上人に御座替本尊を授与されている。大石寺と重須・北山本門寺とは両寺一体の関係で区別はなかった。大石寺・重須はともに時光邸から近距離であったためか、あるいは中古の時代に紛失したためか、日興上人からの書状はほとんど伝わっていない。
大聖人の三十三回忌である正和三年(1314年)は、また時光にとっては父の五十回忌でもあった。正和五年(1316年)の文書から、時光は入道して大行と名乗っている。元亨三年(1323年)には妻の乙鶴が死去した。妙蓮寺伝によれば、時光は妻の菩提を弔うために、一周忌に自宅を寺にしようと発願し、日興上人に願い出たとされる。日興上人はそれを聞き入れられ、弟子の寂日房日華を開基として乙鶴の法号をそのままとって妙蓮寺と称された。
元弘元年(1331年)十月、大聖人五十遠忌を迎え、盛大に法要が営まれた。大聖人の高弟(六老僧)のうち、日昭、日朗、日向、日頂はすでになく、日持は海外弘教に旅立って消息不明となっており、日興上人御一人が御遠忌を奉修し大聖人に報恩の誠を尽くされた。
そのころ、鎌倉幕府も蒙古との戦いを契機として疲弊し、支配体制の基盤である御家人制が崩れだすなど、北条氏専制政治への不満は高まり、朝廷を中心とする討幕運動が盛んになるなど、幕府は急速に終焉を迎えようとしていた。
正慶元年(1332年)五月一日、時光は大聖人、日興上人に外護の赤誠を尽くした七十四年の生涯を終えた。そして、遺言によって両親の眠る上野郷内の
日亨上人の「南条時光全伝」によると、時光は九男四女の子福者であった。
左衛門太郎は長男であるが、病弱か何かの理由で、次男の左衛門次郎時忠が
左衛門次郎時忠については、第三十一世日因上人の「新田南条両家之事」に
「正中三年二月八日状に云く、故二郎云云」(富要五巻331頁)
とあることから、時忠は正中三年(1323年)に死去したことがわかる。死去の原因は不明である。
時忠の死によって、恐らく子の節丸が幼かったためか五男の左衛門五郎時綱が家督をとり惣領となっている。この時綱の子に時長、牛王丸の二人がいる。時長は時綱の跡を継ぎ、牛王丸は後に妙本寺日郷の跡を継いで、中納言阿闍梨日伝と称された。日伝は「大網深秘抄」を著している。
左衛門三郎は、延慶二年(1309年)二月二十三日、伊豆国南条の南方武正名の給田を時光から譲り渡されている。そのほかのことは不明である。
左衛門四郎、左衛門六郎、左衛門七郎については時光からの譲状も現存せず、日興上人の御遷化の御葬送に列したこと以外にはわからない。ただ古文書(富要八巻22頁)によると左衛門六郎は名が清時と記されている。
乙若丸、乙次丸は、のちに日華師の弟子となり、長じて侍従公日相、大法坊日眼と号して、それぞれ富士山妙蓮寺の第四代、第五代の住職となっている。日眼は「五人所破抄見聞」(富要四巻1頁)を著している。
正慶二年(1333年)二月七日、日興上人が八十八歳で重須で御入滅になられ、二月八日に御葬送となった。この時、日郷は「日興上人御遷化次第」をまとめている。
これによると、時光の一族は左衛門三郎、左衛門四郎、左衛門七郎、七郎若宮が花を持ち、左衛門五郎時綱は御影を奉持し、乙若丸は御輿についている。
ここで記されている七郎若宮は一族の者だが、名前からみて兵七郎の縁のある者であろうか。また、左衛門太郎の名もあるが、これが長男の左衛門太郎であるかどうかは不明である。
女子については、長女は新田頼綱夫人となり、日道上人の母となった。次女は奥州加賀野太郎に嫁して日行上人の母となっている。そのほか、乙松、乙一の二人がいたことが文章にみえる。
「南条次郎左衛門入道大行の女子乙松乙一等」(富要八巻33頁)
以上のことから、時光の子孫は大石寺、富士妙蓮寺の草創の時代に、その檀那として、また出家して住職となるなど、時光の意志を継いで大法興隆の礎となったのである。
時光の大聖人に対する外護の誠は、大聖人の身延入山後に限られるが、数々の御供養にもあらわれている。
時光は、身延と比較的近い上野郷に居住していたことからも、わずか九年間の間にたびたび自ら御供養をたずさえて身延に参詣し、また、使いを出して御供養申し上げている。御書全集に残っているだけでもその回数は 四十数回で、宗門最高数である。
ここでは時光および南条一族に与えられた六十編の御書を挙げる。
また、日興上人のもとに送られた弘安五年(1282年)二月二十五日の日朗が代筆した伯耆公御房消息、二月二十八日の法華証明抄は内容からこのなかに入れた。
時光一族への賜書の数は、富木常忍及び尼御前への四十四編、、四条金吾及びその妻への三十八編を大きく上回っている。これは文永十一年(1274年)から大聖人が住まわれた身延山と上野郷が、富木常忍の住む中山や四条金吾の鎌倉と比べて距離が近いことも関係しているだろうが、何よりも時光の純真な信仰のあらわれであることは当然であろう。
下記にて時光および南条一族に与えられた御書を整理する。
https://kid5.sakura.ne.jp/np/R/NanjoTokimitsu/index.html
以上